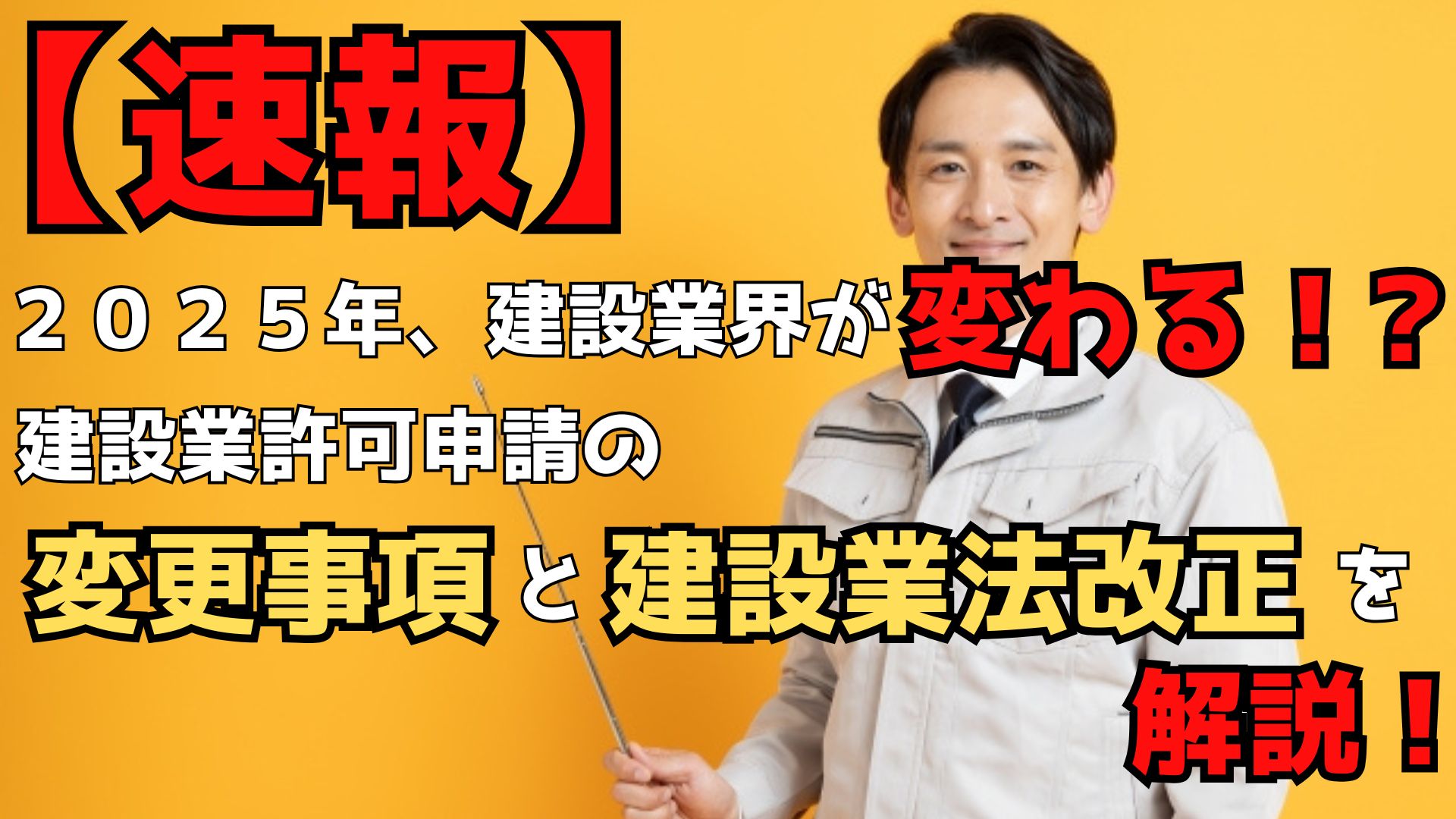令和7年度になり、建設業許可に関して申請方法や確認資料が変わります。
特に東京都知事許可では昨年度からの変更事項があり、許可業者は注意が必要です。
今回は、東京都知事許可における建設業許可申請の変更点と、2025年に改正される建設業法について詳しく解説をしていきます。
2025年4月改定!新しい建設業許可の手引きの変更点

建設業許可申請の手引きは、年度初めの4月に新しいものに変わります。
東京都も毎年4月上旬に更新され、まもなく令和7年度版が新しく公開される予定です。
建設業許可に関する手引きは、年度途中であっても法改正や修正が入るたびに改定がされますので、許可業者は常に新しい手引きを確認するように心がけましょう。
最新の手引きは東京都都市整備局のホームページにて公開されます。
では、令和7年度版手引きはどのように変わるのかを詳しく見ていきましょう。
最新!東京都知事許可の建設業許可手引
令和7年4月3日時点で東京都の新しい手引きが更新されていませんが、下記の項目で変更されると予想されます。
- 専任技術者を営業所技術者等へ呼び名が変更
- 様式の改正により記載例等が変更
- 常勤性確認書類の変更
- 特定建設業の金額の変更
- 手数料の納付方法の変更
- 営業所技術者等の資格の修正
- 注記表「国際最低課税額に対する法人税等」の項目追加
詳細は新しい手引きが公開され次第、随時更新をしていきます。
建設業許可における電子申請の推奨
令和5年1月より建設業許可の電子申請(JCIP)が導入され、これにより申請にかかる手間が大幅に軽減されるようになりました。
電子申請は従来の紙ベースの手続きに比べて、申請処理時間が30%程度短縮されるとも言われています。
紙による対面での申請においては、書類不備による差し戻しが頻繁に発生し補正の度に役所に行く必要がありました。
申請が電子化されることで、事前のチェックが強化され正しい申請が短時間でできるようになるので、許可権者・許可業者ともにメリットが大きくなります。
また、労働保険については2025年1月より一定の基準を満たす企業においては電子申請が義務化されています。
該当する建設業者は、労働保険の年度更新業務を電子申請にて行う必要があります。
将来、建設業許可の電子申請も義務づけられることになるかもしれませんね。
2025年建設業法改正の主要ポイントを解説!

建設業法の改正により、2025年度は以下の内容について変更されます。
- 労働者の処遇改善
- 資材価格高騰による労務費のしわ寄せ防止
- 働き方改革と生産性の向上
建設業界は以前より「担い手問題」が大きな課題となっています。
建設業は国民生活や経済活動を支えるために必要な存在であり、災害時においては地域の守り手として欠かすことのできない業種です。
建設業を今後も安定して持続させるためにも、担い手問題については早急な対応が求められています。
建設業法改正の背景と目的
建設業法は、発注者の保護と建設工事の品質確保などを目的として1949年に制定された法律です。
建設業界の就業人口の減少や資材の高騰など、その時代や社会の需要に応じて改正が行われています。
今回の改正はどのような社会状況で行われたのか詳しく見ていきましょう。
改正の背景
2025年の建設業法改正は、以下のような背景のもとに実施されます。
- 人手不足の深刻化
- 長時間労働の是正
- 社会的要請の高まり
建設業界は慢性的な人手不足に直面しています。
技術者の高齢化や若い年齢層の労働者不足がすすみ、このままでは業界の存続に大きな問題が発生しかねません。
建設業者、建設業従事者ともに、その数は年々減少が進んでいます。
また国土交通省によると、最新の建設業の有効求人倍率は5.8倍前後と他業界に比べて高い水準が続いています。
事務職の有効求人倍率は0.4倍程度なので、水準の高さの度合いがわかりますね。
有効求人倍率が高いということは、建設業界が他の業界に比べて人材を多く求めているにもかかわらず、その成り手がいないということです。
いくら応募をかけても人が集まらない、もしくは採用してもすぐに人が辞めてしまうので建設業者の負担はより一層大きくなります。
労働環境の改善は建設業界に早急に求められている重要な要素となっているのです。
そして最近では各地で自然被害が頻発しており、災害をうけた地域の復興に向けてより一層建設業者が社会的にも必要とされているのです。
改正の目的
改正の目的は、主に以下のものとなります。
- 労働環境の改善と適正な労働時間の確保
- 発注者・受注者間の適正な取引環境の整備
- 業界全体の健全な発展の促進
2025年の改正では、技術者の負担を軽減しより効率的な業務運営ができることを目的としています。
例えば現場監督の業務負担軽減策として、現場カメラやAIを活用した遠隔管理の導入がすすめられています。
これにより、従来は現場に常駐しなければならなかった管理者がリモートで業務を遂行できるようになります。
労働環境を改善して働きづらいといったイメージを払拭させ、若年層の参入を促すことも必要です。
また、元請業者と下請業者の関係性も是正する必要があります。
力関係により負担を強いられる下請業者を守るためにも、適正な環境の整備が求められます。
今、建設業界の透明性向上と働き方改革の推進が求められているのです。
これらの背景や目的を理解したうえで、具体的に改正のポイントを確認していきましょう。
労働者の処遇改善とは
改正の中でも特に重要なのが、労働者の処遇改善です。
この対応は賃金水準の向上や福利厚生の充実を目的として行われます。
具体的には、以下の施策が講じられます。
労働時間の適正化
労働時間の適正化に関しては、いままで常態化していた過重労働を前提とした現場運営からの脱却が求められています。
長時間労働を防ぐための時間外労働の上限規制が2024年より適用され、残業時間は月45時間、年間360時間までとなりました。
繁忙期など特定の期間に関しては、特別条項が適用され残業時間の延長が認められています。
しかし、実際にはいまだに長時間労働を強いられることもあり、これを防ぐために労働基準監督署による監視の強化や、法による強い規制が必要になっています。
決められた工期に間に合わない場合の対処法として休日出勤が常態化している現場もあり、労働者の法定休日が確保されていないのが現状です。
有給休暇の取得もできないなど、建設業界で働く人にとっては過酷な労働になっています。
労務費の確保と賃金の引き上げ
労務費については新しく基準が作成され、これに見合わない著しく低い労務費での見積もりのやりとりした場合、国土交通大臣等により勧告・指導を受けることとなります。
原価割れ契約に関しても同様の処置がされます。
また建設業は他の産業と比べて賃金が低いことも問題です。
労務費を適正に確保することで、労働者の賃金を引き上げることができます。
しかし法律で規制をしても実際の現場では守られていないこともあり、早急に改善しなくてはなりません。
建設業界で働く人々の働きやすさを向上させる動きが求められています。
資材価格高騰による労務費のしわ寄せ防止とは
資材価格高騰による労務費のしわ寄せ防止については、令和6年12月よりすでに施行されています。
昨今の物価高により、資材等の価格の高騰が問題となっています。
この事態に対応すべく、請負代金等の変更方法が契約書の法定記載事項となりました。
今回の法改正により事前通知をした場合は請負代金の変更協議ができ、それに対して誠実に応じるよう努力義務が課せられるようになりました。
また、災害などで資材の不足や運搬の遅延が生じる場合は、その情報を共有しなければなりません。
このようにリスク情報を事前に知ることで、お互いが価格交渉に適正に応じられるようになりました。
建設業法改正による働き方改革と生産性の向上とは

2019年に施行された「働き方改革関連法」では、建設業においては5年の猶予が設けられていました。
この猶予期間が終わる2024年には時間外労働の上限規制が適用され「2024年問題」により建設現場の労働環境が大きく変わることとなりました。
建設業界では長時間労働が常態化しており、統計では週60時間以上働く技術者の割合が30%を超えています。
しかしこれはあくまで表向きであり、実際にはもっと長い時間での労働が行われている可能性もあります。
このような事態を是正するためにも「働き方改革関連法」では、適正な労働時間管理が義務付けられ企業ごとに具体的な労働時間管理計画の策定が求められるようになったのです。
さらにICT(情報通信技術)等を活用することで、生産性を上げ労働者の負担を軽減することも見込まれています。
現場管理の効率化を進めるために、BIM/CIM(ビムシム:建築や土木のデジタルモデル)やドローン技術の導入も推奨されています。
建設業法改正に伴う受注者の責任と基本的義務
建設業法はその時代の背景や求められている事項を主軸にして改正が行われます。
そして受注者には、健全な事業の遂行のためにも守るべき責任と義務があります。
改正に伴う受注者の責任
上記でも解説しましたが、改正によって受注者には次のような新たな責任が求められます。
- 不当に低い請負代金の禁止
- リスク情報等の共有
- 著しく短い工期による契約締結の禁止
これらにより、より健全な建設業界を構築することができるようになるのです。
受注者の基本的義務
受注者には労働者の安全や労働環境を保証し、また工事の品質を保つために行わなければならない基本的な義務があります。
受注者がまもるべき基本的な義務とは次の通りです。
- 施工計画の事前提出
- 技能者の資格証明の適正化
- 労働安全衛生の向上
一定規模以上の工事では、工事開始予定日の14日前までに詳細な施工計画の提出が必要です。
また安全衛生の観点からも、作業員の資格確認を徹底しなければなりません。
安全対策の未実施が発覚した場合、行政指導や罰則が適用されます。
受注者には適正な管理体制を構築することが求められているのです。
労働者の処遇改善の具体策
処遇改善の具体策として、建設業者には次のような行動が求められます。
- 労働者の賃上げ
- キャリアアップ支援
- デジタル化
国土交通省の調査によると建設業の平均賃金は年々上昇傾向にあり2025年には業界平均で前年比5%以上の賃上げが見込まれています。
建設業界の努力の結果であり、継続的に上昇させることが建設業界を盛り上げることにもつながります。
また、技能者のキャリア形成を支援するため、「建設キャリアアップシステム(CCUS)」の活用もさらに求められます。
東京都においては、現在、CCUSの事業者登録している業者は約20,000社(一人親方を除く)でCCUSの普及が着実に進んできています。
企業がCCUSを導入し技術者の経験や資格といった情報を一元化することで、無駄な手間を省き、労働者のスキルアップを後押しすることができます。
また、ICTやAIを活用した作業の自動化を行うことでも施工管理者の負担軽減や施工品質が向上します。
早めに適切な対応を行うことで、今後の事業運営がスムーズに運ぶことにもつながることでしょう。
建設業法改正が建設業界に与える影響

2025年の改正では技術者の配置義務が一部緩和されます。
また、現場管理の効率化がすすみ、特に中小企業にとっては技術者の負担軽減が期待されています。
では、それらが建設業界に与える影響を詳しく見ていきましょう。
現場技術者の専任義務の合理化
これまで一定の工事には専任の技術者が必要でしたが、2025年の改正では、施工管理の合理化を図るため一定の条件下で兼任が認められるようになります。
具体的には、施工管理のICT化や遠隔管理システムの導入することで同一企業内での複数現場の管理が可能になります。
現場労働者の負担軽減になり、生産性があがることで建設業界の今までの課題が改善される可能性があります。
今回の改正により企業の負担は大きくなる部分もありますが、建設業界は大きく変わることになるかもしれません。
まとめ
建設業許可の手引きは毎年4月に新しいものに更新されます。
法改正などにより年度途中で変更されることもあり、許可業者は常に変更がないかアンテナを張っておく必要があります。
また2025年の建設業法改正は、規制強化だけではなく建設業界の持続的な発展と労働環境の改善を目的としたものです。
特に、労働時間や賃金の適正化は建設業者に早急に求められている課題でもあります。
新しい申請方法や法改正を個人で管理するのは大変ですので、早めに頼れる専門家を探しておくのもよいでしょう。
おさだ事務所は、建設業許可に関する申請代行を行っています。
許認可について不明な点がある場合は、ぜひおさだ事務所にご相談ください!
【参考サイト】