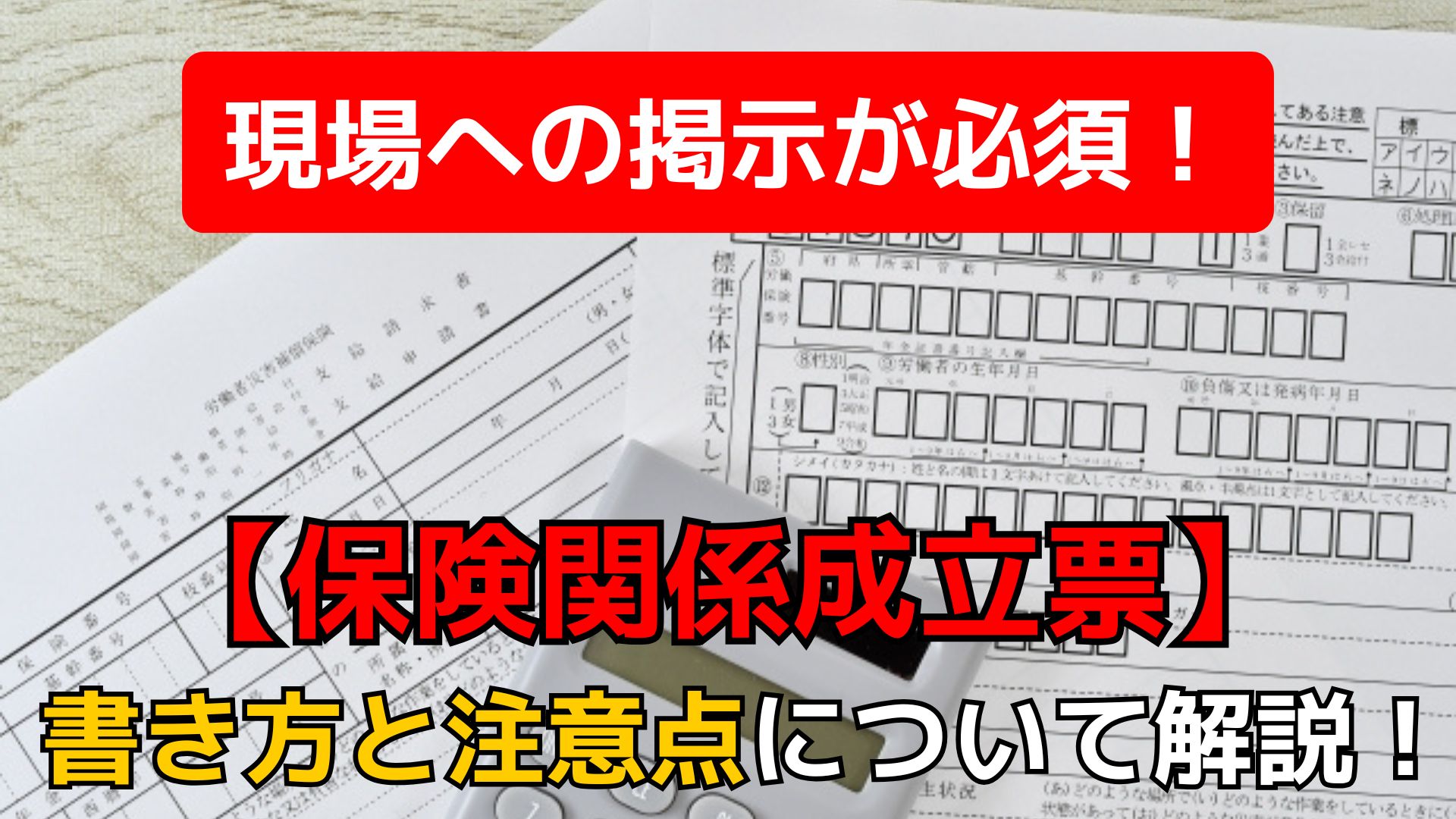建設現場でよく見かける「保険関係成立票」。
一見すると単なる掲示物に思えるかもしれませんが、実は労災保険の加入状況を示す重要な書類です。
建設業に携わる事業者は、保険関係成立票の意義を正しく理解し、掲示義務を怠らないことが求められます。
今回はこの保険関係成立票について掘り下げていきましょう。
保険関係成立票とは

保険関係成立票とは、労災保険の適用を受ける建設業者が、保険関係が成立したことを証明するために作成・掲示するものです。
法に基づき、一定の工事現場では掲示が義務付けられています。
労災保険とは
労災保険とは、正式名称を「労働者災害補償保険」といいます。
業務中や通勤途中に発生した事故や病気に対して、国が補償を行う公的制度です。
この制度は、労働者がケガをしたり、病気になったりした際に、治療費や休業中の生活、さらには遺族への補償まで幅広くカバーします。
しかも、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどの雇用形態に関係なく適用されるのが特徴です。
労災保険には、療養給付・休業補償・障害年金・遺族給付など、状況に応じた複数の支援が用意されています。
たとえば、現場で転倒して骨折した場合、指定医療機関での治療費は原則無料です。
さらに、仕事を休んだ期間には最大で給付基礎日額の約80%が支給される仕組みです。
労働者を一人でも雇用している事業主は、労災保険の加入が義務となります。
また、建設業は「強制適用事業」として法律で定められており、加入しないまま工事を進めると、後々大きなトラブルに発展しかねません。
保険関係成立票の必要性と義務
労災保険の保険関係が成立したことを示す法定標識が「保険関係成立票」です。
建設現場において保険関係成立票の掲示は、労災保険の加入状況を明示する安全の証として、現場の信頼性を支える重要な役割を担っています。
厳しく義務化されているその理由は、建設業特有の労働環境にあります。
現場では元請・下請・一人親方など、複数の立場の労働者が混在して作業を行います。
そのため、労災保険の加入状況が不明確になりやすく、事故発生時の責任の所在が曖昧になりかねません。
そこで保険関係成立票を掲示することで、現場における労災保険の適用状況の「見える化」が可能となります。
掲示しない場合のリスク
建設業において、労災保険の保険関係が成立したにもかかわらず成立票を掲示しないことは、義務違反に該当します。
まず、掲示義務は労働保険徴収法施行規則第77条に基づく法定義務です。
これを怠ると、労働基準監督署から是正指導を受けることになります。
さらに深刻なのは、労災事故が発生した場合です。
保険関係成立票の掲示がないことで、労災保険の適用状況が不明確となり、給付手続きが遅れることがあります。
また、保険関係成立票の掲示がないと、労働者や協力業者から「この現場は保険に入っていないのでは?」と不安視されることもあります。
掲示を怠ることは、事業者自身のリスクを高める行為ともなりうるのです。
保険関係成立票の掲示義務対象工事

保険関係成立票は、労災保険の加入状況を第三者に示す役割も果たします。
現場に出入りする協力業者や監督官庁が、掲示内容を確認することで、適正な保険加入がされているかを判断できるのです。
掲示が必要な工事の条件とは
建設現場で保険関係成立票の掲示が義務となるのは、「建設の事業」に該当する工事です。
労災保険の保険関係が成立している建設工事において、保険関係成立票を掲示しなければならないと法で定められています。
さらに、工期が一定期間に限定されている「有期事業」であることが条件となります。
つまり、常設の工場や事務所ではなく、期間限定で行われる現場作業が該当するのです。
「一括有期事業」として労災保険に加入している場合も、掲示義務は発生します。
そのため、個々の工事現場でも成立票の掲示が必要になるケースが多いのです。
元請・下請それぞれの責任範囲
建設現場では、元請と下請が連携して工事を進めるのが一般的です。
しかし、労災保険や保険関係成立票の掲示に関しては、責任範囲が異なります。
まず、労災保険の加入義務と保険関係成立票の掲示義務は、原則として元請業者にあります。
元請は、現場全体を一つの事業体として扱い、労災保険に加入することで、下請や孫請の労働者も補償対象に含めることができます。
この仕組みにより、現場で働くすべての労働者が一括して保護されるのです。
さらに元請には、下請の労働者が適切な労働条件で働いているか、保険加入が漏れていないかなどを確認・指導する責任もあります。
一方、下請業者は、元請が労災保険に加入している限り、個別に加入する必要はありません。
ただし、下請が単独有期工事を請け負う場合や、下請自身が別の事業場を持つ場合には加入義務が発生します。
元請が労災保険に加入していなかったらどうなるのか
元請が加入していない場合や、元請との契約がない単独工事を請け負っている場合は要注意です。
万が一事故が起きたら、損害賠償問題に発展することもあります。
元請が労災保険に未加入の場合、労働者への給付は行われますが、事業主に対して国から給付額の費用徴収が行われます。
事案にもよりますが、故意または重大な過失が認定された場合、最大で保険給付額の100%を徴収されることもあるのです。
たとえば労災事故で死亡者が出た場合、遺族補償一時金として数百万円〜1,000万円以上の給付が行われます。
このように義務を怠っていた事業者はその全額を負担する可能性があるため、注意が必要です。
下請業者は安心のために民間保険に加入しておくなど、自身で対応できるように対策しておくのがよいでしょう。
保険関係成立票の正しい書き方

成立票の掲示は、監督署で成立届を提出した時点で作成が可能です。
しかし、その際に作成方法について明確に指示があるわけではありません。
自分でその作成方法を調べなくてはなりません。
掲示場所・サイズ・材質のルール
保険関係成立票は、掲示場所・サイズ・材質に明確なルールが定められています。
まず掲示場所についてですが、「事業場の見やすい場所」に掲示することが義務付けられています。
ここでいう見やすい場所とは、現場事務所の内部ではなく、外部から第三者が容易に確認できる位置を指します。
たとえば、工事現場の出入口や仮囲いの外側、現場事務所の外壁などが適切です。
成立票のサイズも法令で規定されています。
標識の寸法は「縦25cm以上×横35cm以上」とされており、B4またはA3サイズが一般的です。
小さすぎると視認性が低く、掲示義務を果たしていないと判断される可能性もあります。
材質については、法令で明確に定められているわけではありませんが、風雨に耐えられる耐候性のある素材が推奨されています。
例えば、ラミネート加工した紙、プラスチック板、アルミ複合板などがよく使われます。
特に屋外掲示の場合は、風で飛ばされたり、雨で文字が滲んだりしないよう、しっかりと固定することが求められます。
成立年月日・工期の記載方法
保険関係成立票を作成する際、最も混乱しやすいのが「成立年月日」と「工期」の記載です。
まず「保険関係成立年月日」とは、労災保険の保険関係が成立した日を指します。
原則として、単独有期事業の場合は工事の着工日=保険関係成立日となります。
つまり、工期の初日をそのまま記載するのが基本です。
ただし、一括有期事業の場合は少し事情が異なります。
この制度では、複数の小規模工事をまとめて年度単位で保険加入するため、保険関係成立年月日は「一括有期事業として最初に届け出た日」となります。
つまり、現場ごとの着工日ではなく、会社が一括有期事業として労基署に届け出た日付を記載する必要があります。
その場合は、会社の労災保険加入履歴や、労基署に提出した保険関係成立届を確認することで、正確な日付を把握できます。
わからない場合は、労基署に問い合わせるのが確実です。
次に「工期」ですが、着工日から竣工予定日までの期間を記載します。
成立年月日とは異なり、現場ごとのスケジュールに基づいて記載します。
注意点として、工期が変更になった場合は、保険関係成立票も更新する必要があります。
掲示内容が現場の実態と異なると、労基署からの是正指導や、元請との契約上の問題につながる可能性があるため、変更があった際は速やかに対応するようにしましょう。
労働保険番号の取得と記載ルール
保険関係成立票を作成する際に欠かせないのが「労働保険番号」の記載です。
労働保険番号とは、企業が労働保険に加入した際に都道府県労働局から割り振られる14桁の番号です。
建設業の場合、雇用保険と労災保険で別々に加入する必要があります。
さらに、労災保険も現場労災と事務労災とに番号が分かれています。
保険関係成立票に記載する番号は「現場労災」の労働保険番号です。
番号がわからない、という場合は毎年の年度更新時に提出した「労働保険概算保険料申告書」の控えを確認するのが最も確実です。
東京都の事業所であれば、府県番号は「13」で始まるのが一般的です。
その他の記載ポイント
保険関係成立票の作成において、注文者・事業主・代理人の欄は誰が関与している工事なのかを明示する重要な項目です。
記載ミスがあると、監督署からの指摘や発注者との信頼関係に影響することもあるため、慎重な対応が求められます。
注文者の氏名
注文者とは、その工事を発注した企業や個人を指します。
記載するのは、法人名または個人名で、法人の場合は「株式会社〇〇」など正式名称を略さずに記載しましょう。
「施主=注文者」となるケースが多く、実際に契約を交わした発注者を記載するのが原則です。
事業主の住所氏名
事業主とは、労災保険に加入している元請業者のことです。
記載するのは、法人の本社所在地と代表者氏名が基本です。
支店や営業所で受注した場合でも、本社の情報を記載するのが望ましいとされています。
代理人の氏名:選任届がある場合のみ記載
代理人とは、事業主が労働保険の手続きを委任した人物を指します。
ここでいう代理人は“現場代理人”ではなく、労働保険に関する法的手続きを代行する者です。
記載するのは、労働基準監督署に「代理人選任・解任届(様式第23号)」を提出している場合のみです。
代理人を選任していない場合は、この欄は空欄で構いません。
保険関係成立票の注意点

保険関係成立票に関する質問は、内容に応じて適切な窓口にて行いましょう。
まず、現場の所在地を管轄する労働基準監督署では、記載方法や掲示義務、労災保険の加入状況などを直接確認できます。
制度全般の広域的な内容は、都道府県労働局の労働保険徴収課が対応しています。
次に、特に注意しておくべき点を解説します。
掲示タイミングと更新の必要性
保険関係成立票は、掲示する「タイミング」と「更新の必要性」を正しく理解しておく必要があります。
まず、掲示のタイミングですが、原則として「工事開始前」に掲示する必要があります。
つまり、現場に職人が入る前、資材搬入が始まる前に掲示しておくのが理想とされています。
特に公共工事や元請管理が厳しい現場では、掲示状況の写真提出を求められることもあります。
しかし、監督署に提出する労働保険成立届は、工事が始まってからではないと届けを出すことができません。
一括有期の場合は工事開始前に掲示できますが、単独有期工事の場合は工事が始まったら早急に成立届を提出し、労働保険番号を振り出してもらう必要があるのです。
さらに、保険関係成立票は、記載内容に変更があった場合、速やかに更新しなければなりません。
一括有期事業・単独有期事業の違いと対応
建設業における労災保険の加入形態には、「一括有期事業」と「単独有期事業」という2つの制度があります。
どちらも工期が定められた建設工事に適用されるものですが、保険加入の方法や事務負担、掲示義務の扱いが大きく異なります。
一括有期事業とは
一括有期事業とは、複数の小規模な建設工事をひとつの事業としてまとめて労災保険に加入する制度です。
対象となるのは、以下の条件をすべて満たす工事です。
- 請負金額が1億8,000万円未満(税抜)
- 概算保険料が160万円未満
- 同一事業主による工事である
- 工事の種類(労災保険率)が同一工期が重複している
- 同一の事務所で保険料納付を行う
個々の工事ごとに保険関係成立届を提出する必要はありません。
ただし、一括有期事業として届け出た場合でも、各現場には保険関係成立票の掲示が必要です。
掲示する成立年月日は、最初に一括有期事業として届け出た日付を記載するのが原則です。
単独有期事業とは
一方、単独有期事業とは、上記の条件に該当しない大規模工事に対して、工事単位で労災保険に加入する制度です。
請負金額が1億8,000万円以上、または概算保険料が160万円以上の工事が対象となります。
この場合、工事ごとに保険関係成立届を提出し、保険関係成立票も個別に作成・掲示する必要があります。
一人親方はどうする?
建設現場で活躍する一人親方は、原則として労災保険の対象外です。
しかし、「特別加入制度」を利用すれば補償を受けることが可能です。
加入は労働保険事務組合を通じて行います。
最近では元請企業から加入の有無を確認される場面も増えており、未加入だと現場に入れないこともあるようです。
また、一人親方が特別加入していても、「保険関係成立票」を掲示する義務は法律上はありません。
成立票は「事業主が労働者を使用する有期事業」に課されるものだからです。
ただし、元請の求めや慣習で掲示を求められることがあり、その場合は掲示するケースもあります。
おさだ事務所は建設業に特化した行政書士事務所です。
労働保険についても対応可です。
ご相談はぜひおさだ事務所にご連絡ください!
【参考サイト】
【こちらもご覧ください】