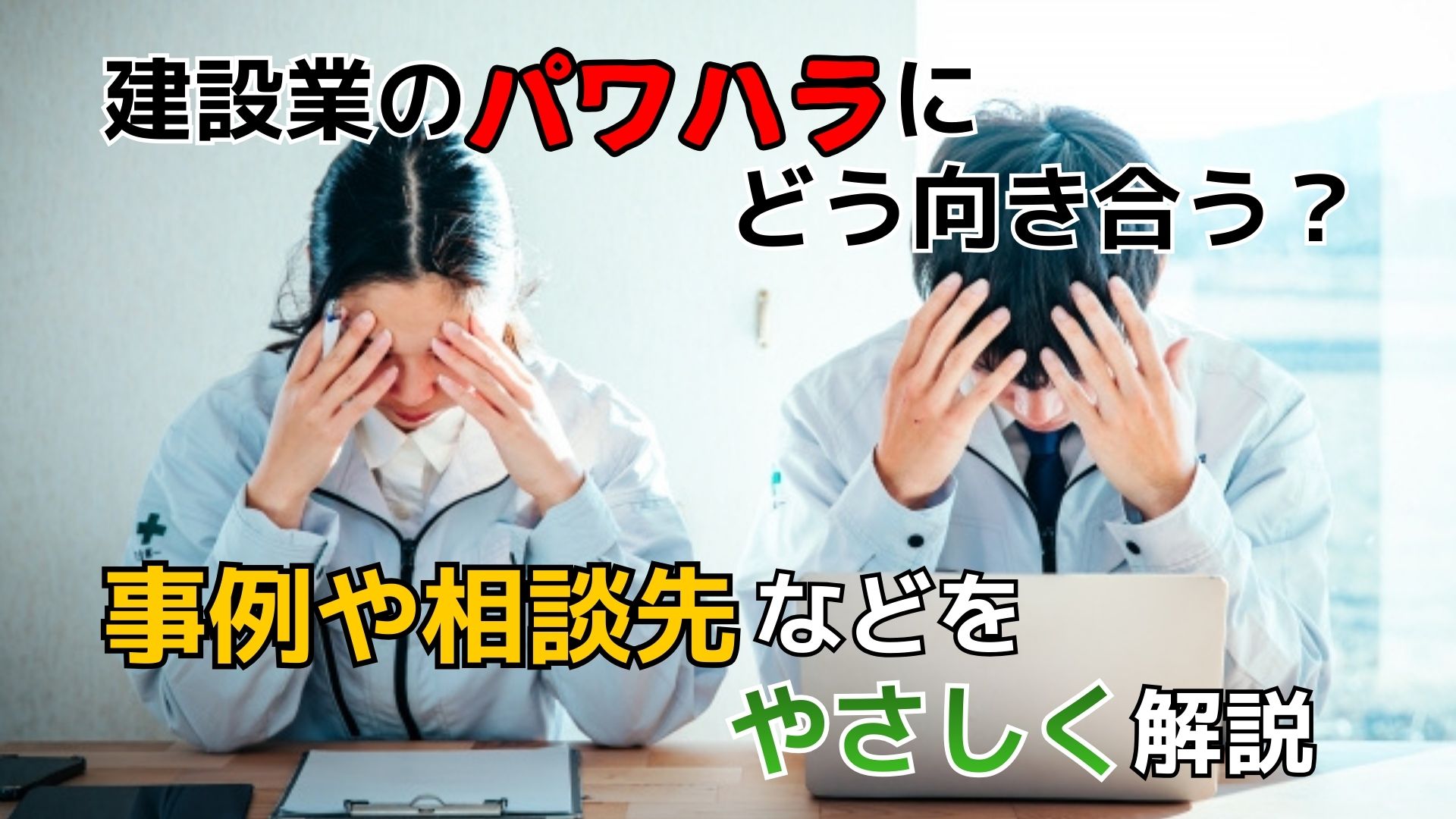建設現場は忙しく、責任も大きいため、厳しい口調や長時間労働が生じやすい環境です。
その結果、指導なのかパワハラなのか判断しにくい場面も多く、疑問を抱えたまま働き続けてしまうケースも見られます。
建設業のパワハラは業界全体の課題ですが、正しい知識を持てば、自分を守りやすくなります。
この記事では、パワハラが起きやすい背景、事例、判断基準、証拠の残し方、相談窓口、企業の防止策までわかりやすく解説します。
建設業界でパワハラが起きやすい背景

建設現場は納期や安全が最優先され、厳しい指示が日常的に飛び交う職場です。
新人や経験の浅い人は相談のタイミングを掴めず、心理的負担を抱え込みやすい傾向があります。
厚生労働省の調査でも、建設業を含む職場のパワハラ相談は増加しており、個人ではなく社会全体の問題として認識されています。
パワハラの発生率と社会的背景
パワハラは決して珍しい問題ではありません。
- 令和5年度の実態調査では企業が受けた相談のうち 64.2% がパワハラ
- 過去3年間でパワハラを受けた労働者は全体の19.3%
- 令和6年度の精神障害の労災認定は1,055件(主因はパワハラ)
厚生労働省が公表した令和5年度の「職場のハラスメントに関する実態調査」では、企業が受けた相談のうち 64.2%がパワハラ という結果でした。
また、過去3年間にパワハラを受けた経験があると答えた労働者は 約19.3% に上るという調査もあります。
さらに、精神面への影響も大きく、深刻な問題として扱われています。
令和6年度には精神障害として 1,055件 が労災認定され、その主な原因の一つがパワハラだったと報告されています。
数字を見ると、パワハラは偶発的な出来事ではなく、広く根づいた課題といえます。
建設現場特有の職場文化
建設現場では、ほかの職場とは違った独特の雰囲気があります。
- 体育会系文化による強い口調
- 男性中心でストレートな物言いが許容されやすい
- 元請け・下請けなど複雑な立場関係
- 一人親方など相談先が把握しづらい働き方
先輩や職長との上下関係が厳しく、指導と叱責の境界が分かりにくい場面も少なくありません。
こうした文化の中では、経験の浅い人や立場の弱い人が不安を抱え、声を上げにくい状況に陥りやすくなります。
元請け・下請けの関係や一人親方のような個人での働き方もあり、相談先が分かりにくい場合もあります。
現場特有の文化を理解することで、何が問題か判断しやすくなり、必要に応じて相談窓口を活用できます。
厚生労働省も、現場特有の文化を踏まえたパワハラ防止策の重要性を指摘しており、少しずつ対策が進んでいます。
建設現場でのパワハラの事例

現場は安全や納期のプレッシャーが大きく、忙しい中で指示が飛び交うため、孤独を感じやすい環境です。
パワハラは個人の問題ではなく、職場環境や働き方が影響するケースが多くあります。
建設現場でパワハラが起きやすい状況を理解すると、不安が和らぎ働きやすさにもつながります。
この章では、具体的な事例に入る前に、現場での心構えや背景を整理し、適切な対応法があるか考えてみましょう。
厚労省が定める6つのパワハラ類型
厚生労働省は、パワーハラスメントを典型的な 6つの類型 に分類しています。
- 身体的な攻撃:暴力や傷害など、体に危害を加える行動
- 精神的な攻撃:脅迫、侮辱、ひどい暴言など、心に苦痛を与える言動
- 人間関係からの切り離し:無視、仲間外し、孤立させる行為
- 過大な要求:達成困難な業務や関係のない作業を押し付ける
- 過小な要求:必要な業務を与えず、過度に簡単な作業ばかり任せる
- 個の侵害:私生活への過度な干渉や監視
これらは「職場におけるパワーハラスメント防止の指針」に基づいています。
まずこの6類型を理解することで、許される指導かパワハラかを判断しやすくなり、不安を抱える場面でも冷静に対応できます。
裁判で認定されたパワハラ事例
建設業界でも、裁判でパワハラが認定された事例があります。
養成社員事件
土木建築会社に入社した新入社員が、上司から暴言・物を投げる行為・過大な業務押し付けを受け、体重減少など深刻な健康被害を負った。裁判所は会社の安全配慮義務違反を認め、慰謝料等約150万円の支払いを命じた。典型的な暴言・暴力型パワハラ認定例。
前田道路事件
営業所長が不正経理を叱責され続け、業績検討会で「辞めても楽にならない」と発言された後に自殺。一審は過度な叱責を安全配慮義務違反と認定したが、二審は業務範囲内と判断し会社責任を否定。パワハラ認定の境界線を示す事例。
日本土建事件
日本土建の社員が上司から長時間の厳しい叱責や過重な業務を受け、精神的に追い詰められ自殺。裁判所は上司の言動が社会通念上許容される範囲を超え、会社の安全配慮義務違反を認定。遺族への損害賠償を命じた。精神的圧迫型パワハラの代表例。
これらの事例は、建設現場の叱責や長時間労働が、指導の範囲を超えて法的問題に発展し得ることを示しています。
自分が受けた言動が許容範囲かどうか迷ったとき、こうした裁判例を知っておくことで適切な判断につながる可能性が高まります。
パワハラかどうかを判断する基準

建設現場では、指導とパワハラの境界が分かりにくいことがあります。
しかし、両者には明確な違いがあります。
指導は、業務の改善やスキル向上を目的としており、相手の成長を意図しています。
言葉が厳しい場合でも、内容が具体的で建設的なら指導に該当します。
一方、パワハラは相手を萎縮させたり、精神的・身体的な苦痛を与えることを目的とする場合が多く、人格を否定する発言や過度な叱責が含まれます。
指導とパワハラの違いを見極めるポイント
判断する際には、次の項目を意識するとわかりやすくなります。
- 行為の目的:業務改善やスキル向上を意図しているか
- 内容の具体性:具体的で建設的か、漠然とした叱責か
- 頻度・継続性:繰り返し行われているかどうか
- 職場での立場の差:立場の弱い人に過度な圧力がかかっていないか
- 相手への影響:精神的・身体的に苦痛を与えていないか
- 周囲の感じ方:自分や同僚が不快や違和感を感じていないか
指導であっても繰り返し行われるとパワハラに該当することがあります。
自分や周囲の感じ方を無視せず、違和感を覚えたら社内外の相談窓口に確認することが大切です。
パワハラと認定されやすい言動とは
厚生労働省や裁判例では、特定の言動がパワハラと認定されやすいと示されています。
- 人格を否定する暴言や過度な叱責
- 他の社員の前で恥をかかせる行為
- 無視や仲間外しで孤立させる行為
- 他人の仕事を不当に取り上げる行為
- 達成困難な作業を強制する行為
- 必要な業務を与えず差別的に扱う行為
これらの言動は、被害者の心身への影響を基準に判断されます。
重要なのは、単発かどうかだけでなく、頻度・継続性・立場の差・受ける側の受け止め方も総合的に考慮される点です。
まずは記録を残し、第三者に相談をすることが大切です。
パワハラを受けたときの具体的な行動

建設現場でパワハラを受けると、「どう動けばいいのか」と不安になる方は多くいます。
特に立場が弱い状況では、声を上げること自体が負担に感じられることもあるでしょう。
ただ、そのままにしておくと心身への負担が大きくなり、問題の解決が遠のいてしまいます。
まずは落ち着いて、状況を客観的に整理することが大切です。
受けた言動を記録し事実を把握するだけでも、次の行動を判断しやすくなります。
また、一人で抱え込まず、信頼できる同僚や家族に話すことで気持ちが軽くなる場合もあります。
証拠を集めて記録を残す方法
パワハラを受けた際に証拠を残すことは、自分を守るための重要な手段です。
まず、日時・場所・状況・関わった人の名前などを具体的にメモしておきましょう。
メールやチャットの履歴、スクリーンショット、可能なら音声データなども保存しておくと役立ちます。
また、当時の気持ちや体調の変化を簡単に書いておくと、後から状況を整理しやすくなります。
記録は紙でもデジタルでもかまいませんが、第三者に改ざんされない形で安全に保管することが大切です。
信頼できる家族や同僚に共有することで、客観的な視点を得られることもあります。
証拠を集める行動は相手を攻めるためではなく、自身の権利と安全を守るための準備です。
社内外の相談窓口の活用法
パワハラを受けたと感じたときは、社内外の相談窓口を頼ることが重要です。
社内では、人事部・総務部・ハラスメント相談窓口などへ相談できます。
事前に記録を整理しておくことで、状況を正確に伝えやすくなります。
社外の窓口としては、労働基準監督署、都道府県の労働相談センター、法律相談窓口などがあります。
匿名で相談できる場合もあり、気軽に利用できます。
大切なのは一人で抱え込まず、第三者の意見を取り入れることです。
相談先は一つに限定する必要はなく、複数を活用しながらより適切なアドバイスを受けることも効果的です。
退職や転職を検討する際の判断ポイント
パワハラによるストレスが続くと、退職や転職を検討することもあるでしょう。
ただ、感情だけで判断すると後悔につながることがあるため、できるだけ冷静に考えることが大切です。
まずは、自分の心身の状態を最優先に確認しましょう。
ストレスや体調不良が長く続く場合は、環境を変える選択が有効なケースもあります。
次に、社内で改善の余地があるかを確認します。
相談窓口や上司との話し合いで状況が変わる可能性がある場合、すぐに退職する必要はありません。
転職を検討する際は、業界動向や働きやすさ、労働条件などを事前に調べ、自分に合う環境かどうかを冷静に判断しましょう。
退職にあたっては、証拠や記録を整理しておくと後のトラブル予防にもつながります。
最終的には、自分の健康と働きやすさを第一に考えることが、後悔のない選択につながります。
建設業者が行うべきパワハラ防止策

建設現場で安全に働くためには、企業が実効性のあるパワハラ防止策を取ることが重要です。
現場の指導方法やコミュニケーションの取り方次第で、パワハラと判断されるかどうかが変わります。
防止策が整っていれば、社員が安心して働けるだけでなく現場の生産性やチームワークの向上にもつながります。
重要なのはルールを掲げるだけでなく、日常的に実践できる対応や現場の体制づくりです。
企業の取り組みが社員に浸透している環境では、パワハラの早期発見や相談のしやすさにもつながります。
パワハラ防止法に基づく企業の義務
2020年の改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、企業には職場のパワハラを防止するための取り組みが義務付けられています。
主な内容は次のものです。
- パワハラ防止方針の周知
- 相談窓口の設置と適切な対応
- 再発防止策の実施
管理職や現場責任者への教育も必要で、適切な指導とパワハラの違いを理解することが求められます。
パワハラが発生した場合、企業は速やかに調査し、必要な措置を講じる責任があります。
現場で実践できる具体的な対策
建設現場でパワハラを防ぐには、日常的に実践できる具体策が大切です。
- 朝礼やミーティングで業務内容や注意点を共有
- 指導時は叱責ではなく建設的な言葉を意識する
- チームで助け合う文化をつくり孤立を防ぐ
- 相談窓口を現場でも明確に周知する
- 記録の取り方や注意点を共有しトラブルを防ぐ
こうした取り組みを日常的に行うことで、現場全体が安心して働ける職場となりチームの信頼や安全性も高まります。
よくある質問(FAQ)

パワハラについて疑問や不安を抱える方は少なくありません。
ここでは、よく寄せられる質問を取り上げ、基本的な考え方をまとめました。
パワハラを受けたらすぐに辞めるべき?
「すぐ辞めるべきか」と迷う方は多いですが、まずは自分の心身の状態を確認しましょう。
ストレスや体調不良が続く場合は、環境を変える選択も検討できます。
ただし、退職を急ぐ前に、社内窓口や信頼できる上司に相談し、改善の可能性を探ることも大切です。
相談や記録の整理を通じて、状況が良い方向に進むケースもあります。
転職を考える場合は、新しい職場の環境や条件を事前に調べて判断すると安心です。
しばらくは辛いかもしれませんが、焦らず冷静に判断することが、自分にとって最適な選択につながります。
匿名で相談できる窓口はある?
匿名で相談したい方は多く、実際に利用できる窓口があります。
たとえば都道府県の労働相談センターや、労働局の総合労働相談コーナーでは、個人情報を伝えずに相談できます。
メールや電話で匿名対応している自治体窓口もあります。
一人で悩みを抱えず、第三者の助言を得ることで、判断や行動がしやすくなります。
証拠の残し方や相談の進め方を教えてもらえる場合もあり、安心して利用できます。
加害者にどのような処分がある?
パワハラの加害者には、状況や深刻さや企業の就業規則に基づいて処分が科されます。
口頭や書面での注意、減給や出勤停止、配置転換、中には解雇に至ることもあります。
処分は企業の就業規則やハラスメント防止方針に基づいて決定され、被害者からの相談や通報を受けたうえで、適切な調査や聞き取りが行われます。
さらに、悪質なケースでは労働基準監督署や裁判所が関与し、加害者への指導や損害賠償請求が行われることもあります。
処分は被害者の安全を守り再発を防ぐことを目的としている点が重要です。
個人でできるパワハラ防止策はある?
個人レベルでも、パワハラの予防や早期発見につながる行動を起こせます。
まずは以下の項目をしっかりと意識しておきましょう。
- 自分の言動を振り返り、誤解を招かないよう意識する
- 問題が起きたら日時や内容を記録する
- 信頼できる上司や同僚に早めに相談する
- 心身の健康を守るために、必要に応じて休息を取る
- 公的窓口や社内制度を事前に把握しておく
こうした心がけが、自分の安全を守るうえで役立ちます。
建設業界でのパワハラ防止には、法令理解と現場に合った対応が欠かせません。
おさだ事務所では、労務管理や書類作成の相談に丁寧に対応し、企業と従業員の安心を支えています。
専門知識と経験を活かしたサポートで幅広く支援していますので、まずはお気軽にご相談ください。
【参考サイト】
NOパワハラ なくそう、職場のパワーハラスメント | 政府広報オンライン