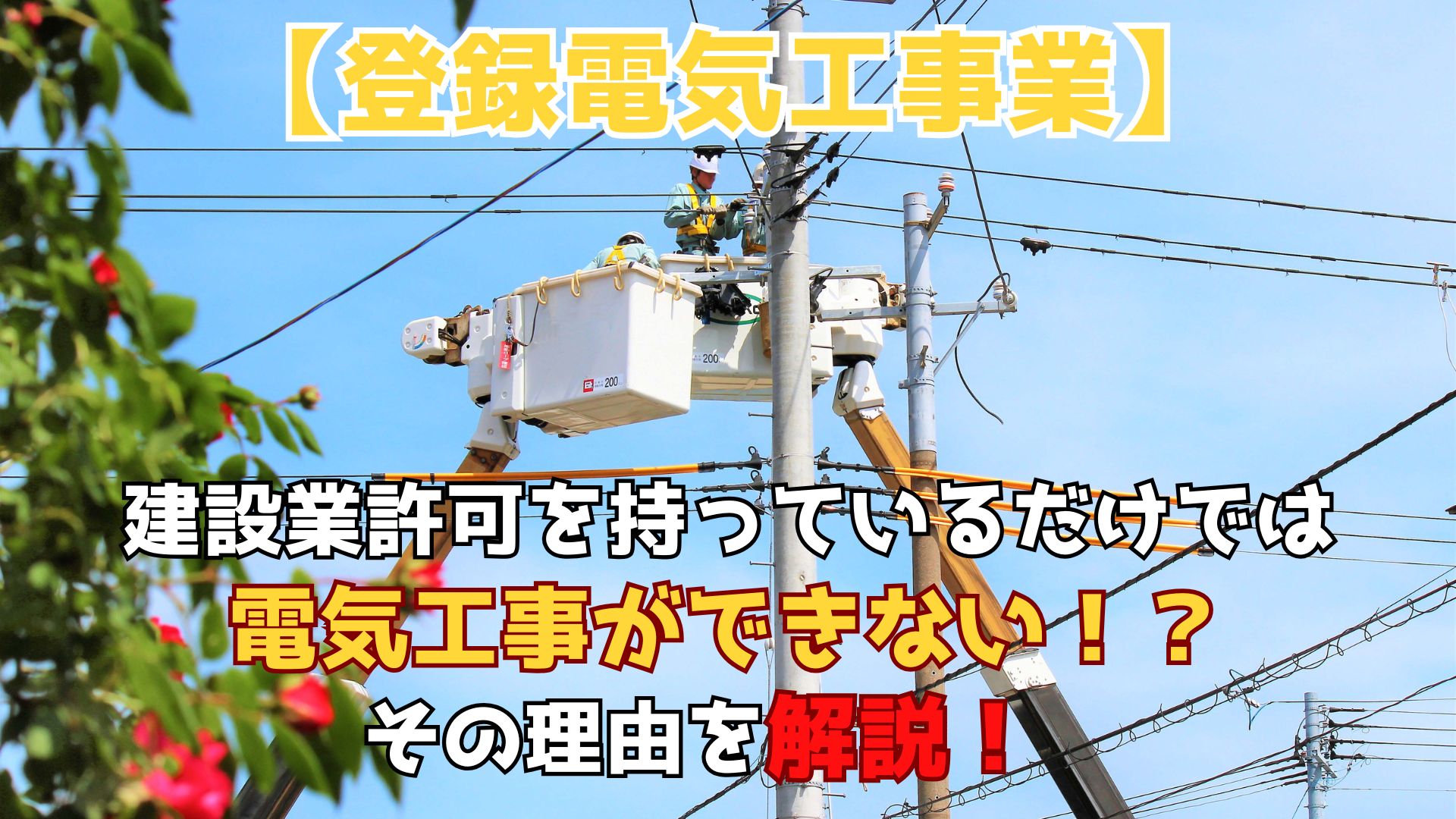電気工事と聞いて思い浮かべるのはどのような工事でしょうか。
エアコンの取付、コンセントの増設といった身近なものから、発電設備や送電線などの電気の供給、クレーンなどの大型機械の整備などの大規模な工事まで色々あります。
こういった電気工事をする際には、許可や登録が必要になる場合があります。
また、建設業許可をもっているだけでは、電気工事ができるとは限りません。
今回は複雑な電気工事の基本について、わかりやすく解説していきます。
電気工事業の基礎知識

電気工事は知識や技術があれば、誰でも行ってよいわけではありません。
電気工事に関する資格が必要であったり、ある一定の条件を満たす工事をするには登録や許可が必要であったりします。
これは、知識や技術がない状態で電気工事をすると火災や感電などの事故がおきてしまうかもしれないからです。
うっかり違反してしまうことのないように、正しい知識を持たなくてはなりません。
ただし、中には資格や許可がなくてもできる工事もありますので事前に確認をしておきましょう。
電気工事の軽微な工事とは
下記のような「軽微な工事」とよばれる電気工事は、資格がなくてもできます。
- 照明の取り付け
- 電気プラグや電球の交換
- 汎用モーターや蓄電池などのネジ留め
- ヒューズの取り付けや取り外し
- インターホンや火災報知機の二次側配線
電気工事における軽微な工事は、電気工事士法施行令第1条によって次のように定められています。
- 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
- 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)をねじ止めする工事
- 電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取りはずす工事
- 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(2次電圧が36ボルト以下のものに限る)の二次側の配線工事
- 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
- 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
これらの軽微な工事は、電気工事士法の対象ではなく「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(電気工事業法)で電気工事から除外されています。
しかし、軽微な工事の定義は複雑です。
無資格で工事を行った結果、実は資格を要する工事だったということがないようにしなければなりません。
電気工事の内容を正しく理解し、必要であれば資格を取得することがとても重要です。
電気工事業とは
電気工事業とは、電気工作物とよばれる装置の設置・変更等の電気工事を業として行うことをいいます。
電気工事業を始めるには所管の行政機関へ届け出る必要があります。
ただし、すべての電気工事が届出対象になるわけではありません。
600V以下の低電圧で使用されるコードやスイッチの接続といった軽微な工事は届出なしで施工可能です。
また、家庭用家電の設置に伴う簡易工事も届出は不要です。
届出の有無は工事の規模や対象機器によって異なっていますので、事前の確認が重要です。
電気工作物の種類
電気工作物とは、発電・変電・送電・配電または電気使用のために設置する機械・器具・ダム・水路・貯水池・電線路その他の建築物以外の人工物をいいます。
さらに電気工作物は以下のように分けられます。
- 一般用電気工作物:一般住宅・アパート・小規模店舗の屋内配線や、出力10キロワット未満の太陽電池発電設備・出力20キロワット未満の小水力発電設備等
- 事業用電気工作物:一般電気用工作物に該当しない電気工作物
電気工作物は大きく分けて、上記のように「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物」に分類されます。
一般用電気工作物とは、600V以下の低圧で受電し同一しで使用する電気工作物、または低出力の小規模発電設備をいいます。
一方、事業用電気工作物はこれに該当しないもので、さらに次のように細分されます。
- 電気事業用電気工作物:電力会社が運用している送電および配電の設備等
- 自家用電気工作物:ビル、工場、病院などで高圧電力を使用している電気設備等
電気事業用電気工作物は、電力会社が運用する発電所や変電所、配電線路などを指します。
自家用電気工作物は、一般送配電事業者または特定送配電事業者から高圧及び特別高圧で受電する事業の電気工作物をいいます。
これらの違いをしっかりと理解しておきましょう。
電気工作物の保安規制
事業用電気工作物および一般用電気工作物においてはその安全性を保証するために、様々な義務や国による命令が課せられています。
事業用電気工作物については、発電所(火力・水力・燃料電池・太陽電池・風力)、蓄電所、変電所、送電線路、配電線路、需要設備が対象となっており、下記のような保安規制があります。
- 電力会社は一定の技術基準を満たしていなければならない
- 電力会社は主任技術者を置かなくてはならない
- 電力会社は自主検査を行いそれを記録しなければならない
- 電力会社は電気工作物を設置する際には届出をしなければならない
- 国は技術基準を満たしていない業者に対し停止や変更を求めることができる
- 国は業者に対し審査を行い、問題があれば改善の指導等をする
住宅の電気設備などの一般用電気工作物においては、次のようになります。
- 電力会社は一般電気工作物が設置または変更されたときに施工調査をしなければならない
- 電力会社は一般需要家においては4年に一回以上定期調査をしなければならない
- 電力会社は特定需要家(学校や病院)においては毎年一回以上定期調査を実施しなければならない
これらの調査は電力会社または委託を受けた業者が行います。
自宅などに、数年に一度電気の検査が入るのはこのためです。
電気工事業の登録前に確認すること

電気工事業者の分類
電気工事業者には複数の種類があり、業務内容や建設業許可の有無によって必要な届出が異なります。
- 登録電気工事業者
- みなし登録工事業者
- 通知電気工事業者
- みなし通知電気工事業者
「登録電気工事業者」とは、一般用または一般用および自家用電気工作物の工事を建設業許可なしで行う事業者が該当します。
「みなし登録電気工事業者」は、建設業許可を有し同様の工事をする場合に必要です。
自家用電気工作物のみを扱う場合には「通知電気工事業者」となり、さらに建設業許可をもっていれば「みなし通知電気工事業者」に区分されます。
どの届出が必要かは、施工対象となる電気工作物と建設業の許可状況に応じて判断されます。
このように「登録」と「通知」では意味が大きく異なり誤って届け出すると違法営業になることもありますので、しっかりと確認する必要があります。
電気工事業の登録に必要な要件
- 有資格者の設置
- 必要な設備の所持・設置
- 欠格要件に該当しない
電気工事業を営むには、これらの要件を満たす必要があります。
登録電気工事業者やみなし登録工事業者の場合は、「主任電気工事士」の設置が必須です。
主任電気工事士になれるのは、第一種電気工事士または3年以上の実務経験のある第二種電気工事士のみです。
一方、通知電気工事業者は「第一種電気工事士」または「認定電気工事従事者」の設置が求められます。
第二種電気工事士であっても所定の講習をうけることで認定電気工事従事者になれますが、この場合は簡易電気工事の作業のみ従事可能となります。
また、絶縁抵抗計や検電器などの測定器の常備が義務付けられています。
このような必要器具は新品・中古は問われず、機能性が確認できれば登録可能であり、自社で所持していない場合はレンタルでも良いことになっています。
さらに、法令違反歴や過去の登録取消など、一定の欠格要件にも該当していない必要があります。
これらの基準を満たすことが登録の前提条件となっています。
電気工事業の登録方法

上記電気工事業の要件を満たしていれば、電気工事業の登録をすることが可能です。
その際には申請先や必要書類、費用など事前に確認をしておくことが重要です。
次に登録の方法について説明していきましょう。
登録電気工事業の申請・届出
電気工事業を営もうとするときは、電気工事業法に基づき都道府県知事又は経済産業大臣へ登録等が必要です。
また建設業法に基づく許可を受けた建設業許可業者であっても電気工事業を営むときは登録や届出が必要です。
登録電気工事業には更新が必要であり有効期限は5年ですが、通知電気工事業には更新がありません。
登録電気工事業の申請先
電気工事業は、営業所の所在地や数によって申請先が異なります。
1つの都道府県内に営業所がある場合はその都道府県知事に申請しますが、複数の都道府県にまたがる場合は国への申請が必要になります。
たとえば、東京都内のみで電気工事業を営む場合は東京都知事あてに申請しますが、さらに大阪にも営業所があれば申請は経済産業大臣宛てとなります。
また、東京都と神奈川県に営業所がある場合は同一管轄内となり、関東東北産業保安監督部宛てに提出します。
基本的には窓口申請若しくは郵送申請となりますが、経済産業大臣への登録・届出等は、電子申請による手続きが推奨されています。
このようにパターンによって申請先や申請の方法が違いますので、該当する行政に確認をしておきましょう。
登録電気工事業の必要書類
登録に必要な主な書類は下記のものとなります。
「登録電気工事業者」の場合
- 登録電気工事業者登録申請書
- 申請者の住民票または登記事項証明書
- 誓約書
- 主任電気工事士の雇用証明書
- 主任電気工事士の電気工事士免状の写し
- 主任電気工事士の実務経験証明書(第二種電気工事士の場合)
- 建設業許可を受けている場合は許可通知書の写し
- 器具明細書
「通知電気工事業者」の場合
- 電気工事業開始通知書
- 通知者の住民票または登記事項証明書
- 誓約書
- 建設業許可を受けている場合は許可通知書の写し
- 第一種電気工事士免状または認定電気工事従事者認定証書の写し
- 器具明細書
いずれの場合も、提出書類の不備は審査遅延や不受理につながるため、事前にチェックリストなどで確認することが大切です。
登録電気工事業の費用
電気工事業の登録には、手数料がかかります。
登録電気工事業の申請には手数料として22,000円がかかります。
通知電気工事業において登録費用はかかりません。
納入方法は収入証紙や納付書による支払いとなります。
建設業許可業者(みなし業者)は登録手数料不要です。
建設業許可との関係

建設業許可をもっているから、電気工事をしてもよいと思っている建設業者もいるかもしれません。
また、大規模な電気工事の話がきたけど、建設業許可を持っていなかったので契約できなかったなどという話も聞かれます。
電気工事の請負のために必要なものが建設業許可であり、電気工事の施工のために必要なものが電気工事業登録となります。
建設業者にとって、建設業許可取得と電気工事業登録は密接な関係となっています。
しっかりとその違いと仕組みを理解しておきましょう。
建設業許可業者の注意点
電気工事業を営む場合、工事の規模によっては建設業許可が必要になることがあります。
たとえば、電気工事の請負金額が税込500万円以上となる場合は、建設業法に基づく許可が必須です。
建設業許可の管轄は国土交通省である一方、電気工事業の管轄は経済産業省と分かれていて、登録や許可の法的根拠が異なります。
電気工事業の建設業許可は持っているが電気工事業の登録をしていない業者は、電気工事の請負の契約をすることは可能です。
しかし、その工事を自社にて施行することは禁止されており、実際の工事は下請に出すなどの対応が必要になります。
そのため自社にて電気工事を施工するのであれば、電気工事業建設業許可を取得していても別に登録電気工事業の届出が必要となるのです。
また、電気工事業以外の業種の許可をもつ建設業者であっても「みなし登録(通知)」となり、500万円未満の電気工事をするのであれば届出が求められます。
みなし登録(通知)業者は、建設業の許可が更新する度に電気工事業登録においても変更届の提出が必要となりますので、忘れずに届出しましょう。
建設業電気工事業許可の取得要件
電気工事業で建設業許可を取得するためには、いくつかの要件があります。
まず、営業所ごとに電気工事業に該当する営業所技術者等(専任技術者)を配置しなければなりません。
実務経験や指定学科の卒業、あるいは国家資格(電気工事施工管理技士、電気工事士、電気主任技術者など)を有している技術者が必要となります。
電気工学、電子工学などが指定学科であり、卒業証明書の提出が必要です。
実務経験の例としては、電気工事の施工管理、見積もり業務、施工図作成などがあげられます。
また、常勤役員等(経管)を常勤役員等として配置することも条件の一つです。
経管には一定年数以上の経営経験が求められ、法人であれば役員、個人であれば本人または支配人が該当します。
そのほか、欠格要件や財産的基礎要件、誠実性などが求められます。
これらの条件を整備し書類を用意して申請することで、電気工事業における建設業許可を取得できます。
まとめ
電気工事をするには、資格の取得や、適切な登録・許可の申請が必要となります。
しかし資格がなくてもできる電気工事、届出しなくてもできる電気工事、建設業許可がなくてもできる電気工事もあり、その判断はとても複雑です。
電気に関わる工事は、生活になくてはならない大切なものであり、安全かつ適正に行う必要があります。
電気工事をする建設業者は、建設業許可と電気工事業登録の双方の制度についてしっかりと理解しておかなくてはなりません。
おさだ事務所では、電気工事業の登録や建設業許可申請について相談を承っております。
申請や届出の際には、ぜひおさだ事務所にご連絡ください!
【参考サイト】