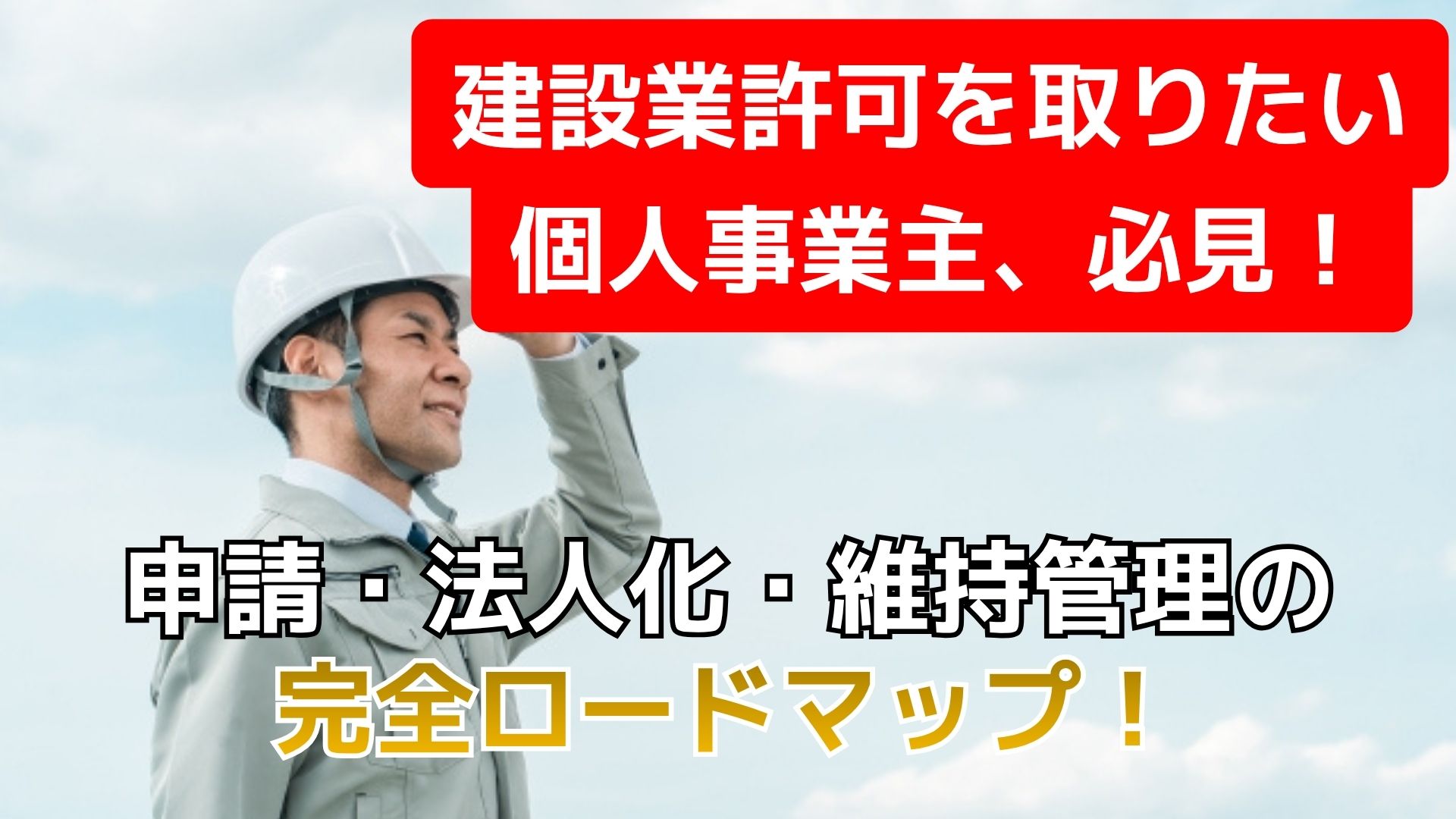建設業で独立を目指す個人事業主にとって、事業を安定させるためには「建設業許可」の取得が重要です。
特に東京都内で活動する場合は、「東京都知事許可」が必要になることもあり、制度の理解が大切です。
ただ、初めての申請では「個人でも許可は取れるの?」「何から始めればいい?」と不安を感じる方も少なくありません。
この記事では、個人事業主が東京都知事の建設業許可を取得するための流れや要件、注意点をわかりやすく解説します。
個人事業主でも建設業許可は必要?

法人ではなく個人で事業を始める場合、許可の取得が必要か判断に迷う方も多いでしょう。
初めて建設業に携わる方にとっては、制度の仕組みや対象となる工事など許可に関わる情報を整理するだけでもひと苦労です。
そこで本章では、個人事業主が建設業許可の対象になるかどうかなど制度の基本から解説します。
建設業許可が必要かどうかは、請け負う工事の金額によって判断されます。
建設業許可が必要となる工事とは
許可が必要なのは、一定の規模を超える工事に限られます。
建築一式工事であれば1件につき1,500万円以上(税込)、それ以外の工事では500万円以上(税込)の請負契約が対象です。
これらの金額を超える工事を行う場合、許可を取得していないと法令違反となる可能性があります。
500万円未満の軽微な工事では許可は不要です。
なお、金額の判定は「材料費・人件費等を含む総額」で行われるため、見積もりの段階でしっかり確認しておくことが重要です。
個人事業主であっても、これらの基準を満たす工事を請け負うのであれば、建設業許可の取得が基本的に必要になります。
東京都知事許可と国土交通大臣許可の違い
建設業許可には、「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」の2種類があります。
どちらを取得するかは、営業所の所在地によって決まります。
たとえば、東京都内にのみ営業所がある場合は「東京都知事許可」が必要です。
東京都と他県の両方に営業所を構えている場合は、「国土交通大臣許可」となります。
ここでいう営業所とは、単なる作業現場ではなく、契約や見積もりなどの事務を行う拠点を指します。
たとえば、東京都に本店、埼玉県に支店がある場合は、大臣許可が必要となる可能性があります。
個人事業主であっても、建設業の契約行為を行う営業所が複数の都道府県にまたがる場合は、知事許可ではなく大臣許可が必要になるのです。
建設業許可を取得するための要件と準備

建設業許可を取得するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
特に個人事業主の場合、法人とは異なる点があり、申請のハードルが高く感じられるかもしれません。
とはいえ、許可申請の要件を正しく理解し必要な書類を揃えておけば、申請手続きはスムーズに進みます。
この章では、建設業許可を取得するために押さえておきたい基本的な条件や、準備の進め方について整理していきます。
個人事業主が満たすべき5つの要件
建設業許可を取得するには、個人法人問わず、定められた5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 誠実性
- 財産的基礎
- 欠格要件
まず求められるのが「営業務の管理責任者(常勤役員等)」の存在です。
一定期間の経営経験があることを証明できる人物が必要になります。
ほかに「専任技術者(営業所等技術者)」の配置が挙げられます。
工事の種類に応じた資格や実務経験が求められ、個人事業主の場合は事業主本人が兼任できる場合もあります。
さらに「誠実性」も審査対象で、過去に重大な法令違反がないかが確認されます。
加えて「財産的基礎」があることも条件のひとつで、一定の自己資本や資金調達力が必要です。
最後に「欠格要件に該当しないこと」です。
暴力団関係者や禁固以上の刑を受けた人などが対象となります。
営業所の条件と自宅兼事務所の注意点
建設業許可の申請には、「営業所の設置」も必須です。
営業所とは、契約や見積もりなどの事務作業を行う拠点のことで、単なる作業場とは区別されます。
個人事業主の場合でも、業務に必要な設備が整った環境であることが求められます。
近年では、自宅を事務所として兼用するケースも増えていますが、その場合は注意が必要です。
注意すべき審査のポイントは下記のものです。
- 生活スペースと業務スペースが明確に分かれているか
- 机や書類棚、電話などの設備が整っているか
- 賃貸物件の場合は契約上事務処理用が認められているか
許可取得を考えている場合は、事務所も事前に環境を整えておくことが重要です。
東京都での建設業許可申請の流れ

東京都で建設業許可を申請する場合は、都独自の運用ルールや窓口対応があるため、事前に全体像をつかんでおくと安心です。
申請書類の準備や必要書類の収集には時間がかかるため、流れを理解したうえで計画的に進めることが大切です。
この章では、東京都における建設業許可の基本的な申請の流れを説明します。
必要書類と申請先
建設業許可の申請には、複数の書類を整える必要があります。
主な書類は以下のものです。
- 建設業許可申請書
- 営業所一覧表
- 専任技術者等一覧表
- 使用人数
- 誓約書
- 営業の沿革
- 健康保険等の加入状況
- 常勤役員等証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
- 登記されていないことの証明書
- 身分証明書
- 常勤役員等の確認資料
- 専任技術者の確認資料
- 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況を証明する書類
記載ミスや書類の不備があると、審査が長引いたり再提出を求められることがあります。
申請先は営業所の所在地によって異なります。
東京都内にのみ営業所がある場合は、東京都庁が窓口となります。
複数の都道府県に営業所がある場合は、国土交通省が管轄となる場合もあります。
東京都の公式サイトで、手引きを確認しておきましょう。
審査期間と許可取得までの目安
建設業許可の申請から取得までには、一定の審査期間が設けられています。
東京都知事許可の場合、新規申請後の審査期間は通常45日程度です。
ただし、書類に不備がある場合や追加資料の提出が必要になると、さらに時間がかかることがあります。
申請前の準備期間も含めると、全体で2〜3か月ほどを見込んでおくと安心です。
初めて申請する場合は、要件確認や書類収集に時間がかかるため、余裕を持ったスケジュールが重要です。
また、申請窓口の混雑状況や審査の進行具合によっても期間が前後するため注意が必要です。
許可取得後の義務と注意点

建設業許可を取得した後も、事業者には継続的な管理と法令遵守が求められます。
許可の取得はゴールではなく、事業運営のスタートに過ぎません。
とくに個人事業主の場合、日々の業務に追われる中で、更新手続きや報告義務を後回しにしてしまうことがあります。
しかし、こうした対応の遅れが行政指導や許可の取消につながる可能性もあるため注意が必要です。
許可を維持するには、定期的な届出や帳簿の管理、変更時の申請など、基本的なルールを守ることが欠かせません。
主任技術者の配置と許可票の掲示
現場には、主任技術者や監理技術者の配置を求められる場合があります。
主任技術者は、工事の品質や安全を管理する責任者で、専任技術者とは役割が異なります。
資格や実務経験を備え、現場に常駐できる体制が必要です。
配置が不十分だと、行政指導や処分の対象となる可能性があります。
また、許可を受けた事業者は、営業所とすべての工事現場に「建設業の許可票」を掲示が求められます。
基本的に、許可票には次の内容を記載します。
- 商号又は名称
- 代表者の氏名
- 一般建設業または特定建設業の別
- 許可を受けた業種
- 許可番号
- 許可年月日
- 専任技術者の氏名・資格
掲示場所は、第三者が容易に確認できる位置が原則です。
更新・決算報告などの維持管理
建設業許可を維持するには、「更新申請」や「決算報告書の提出」などの定期的な手続きが必要です。
更新は5年ごとに行い、引き続き許可要件を満たしているかが審査されます。
決算報告は、一般的に毎事業年度の終了後4か月以内に提出が必要で、財務状況や工事実績を報告します。
これらを怠ると、次の更新申請ができないなど事業に大きな影響を与える可能性があります。
また、商号や営業所の所在地、役員構成などに変更があった場合は、定められた期間内に変更届を提出しなければなりません。
許可を継続するためにはこのような維持管理も重要です。
個人事業主から法人化する場合の注意点

建設業を個人事業として運営している方の中には、事業の拡大や信用力の向上を目的に法人化を検討するケースもあります。
法人化には、社会的な信頼性の向上や資金調達の選択肢が広がるなどのメリットが期待されますが、制度面での注意も必要です。
とくに建設業許可を取得している場合、法人化によって許可の扱いが変わるため、事前の確認が欠かせません。
個人事業主としての実績や要件がそのまま法人に引き継がれるとは限らず、改めて申請が必要になることもあります。
この章では、法人化にあたって押さえておきたい基本的な視点や制度上の留意点を解説します。
許可の継承はできる?
建設業許可は事業者ごとに付与されるため、原則として他者へそのまま引き継ぐことはできません。
個人事業主が法人化する場合や法人の吸収合併などの場合は注意が必要です。
事業の実体が継続していると認められる場合には、「承継認可制度」が適用されることがあります。
この制度を利用するには、一定の要件を満たし所定の手続きを経る必要があります。
承継が認められれば、許可の効力を維持したまま事業を継続できますが、認可されない場合は新規申請が必要です。
法人化後の新規申請の流れ
個人事業主が法人化した場合、建設業許可は自動的に引き継がれないため、承継認可制度が利用できない場合は法人名義で新たに申請する必要があります。
まずは法人設立後、登記簿謄本や定款などの法人情報を整え、申請書類を作成します。
法人として経営業務管理責任者や専任技術者の要件を満たしているかを確認することも重要です。
法人化後の申請には、事業継続のため早めの準備が必要です。
必要書類や要件を事前に確認し、計画的に手続きを進めることで、スムーズな移行につながります。
法人化を考えている場合は、東京都に事前に相談に行くことをおすすめします。
許可取得のメリットとデメリット

建設業許可は、取得することで事業の幅が広がる一方、維持や管理の負担も伴います。
許可を得ることで、公共工事への参加や元請としての契約が可能になるなど、信用力や営業機会の向上が期待できます。
ただし、法令遵守や定期的な手続きが求められ、事務負担やコストが増える点には注意が必要です。
とくに個人事業主や小規模事業者にとっては、許可取得によるメリットとデメリットを正しく理解し、自社の事業方針に照らして判断することが重要です。
制度の仕組みを把握せずに申請を進めると、取得後に思わぬ手間や負担が生じる可能性もあります。
信頼性向上と受注拡大
建設業許可を取得すると、事業者としての信頼性が高まり受注の機会も広がる可能性があります。
許可を持つことで、法令を遵守し、一定の技術力や経営基盤があることが公的に証明されるため、元請企業や発注者からの評価が向上する傾向にあります。
とくに公共工事や大手企業との取引では、許可の有無が受注の前提条件となることも多く、営業活動の幅が広がる大きな要因となります
また、許可業者として登録されることで、入札参加資格の取得や業者名簿への掲載といった制度上の利点も得られます。
ただし、許可を取得するだけでなく、日々の業務で法令を守り、適切な管理を続けることが大切です。
費用・手続きの負担と維持管理の手間
建設業許可の取得には、申請手数料や証明書類の取得費など、一定の費用がかかります。
申請書類の作成には専門知識が必要なため、行政書士などに依頼する場合は報酬も発生します。
さらに、許可取得後も5年ごとの更新申請や、毎年の決算報告書の提出など、継続的な手続きが求められます。
商号や役員の変更があれば、速やかに変更届を提出する必要があり、日常的な情報管理も欠かせません。
これらの維持管理には時間と労力がかかるため、事業規模や体制に応じた対応が求められます。
許可を取得することで得られるメリットは大きいものの、制度の理解と継続的な管理も求められるため、負担も大きくなる場合もあります。
専門家によるスムーズな申請支援
建設業許可の申請には、複数の書類作成や要件確認が必要で、専門的な知識が求められます。
初めての申請や法人化に伴う手続きでは、内容の複雑さに戸惑うことも少なくありません。
こうした場面では、行政書士などの専門家に依頼することで、要件の確認から書類作成、提出までを一括して支援してもらえます。
専門家は最新制度や審査基準に精通しており、申請ミスや再提出のリスクを軽減できます。
期日管理も行ってくれる場合もあり、申請忘れを防ぐことも可能です。
専門家への依頼は事業者の負担軽減にもつながります。
許可取得を確実かつ効率的に進めるには、専門家のサポートを活用することが有効です。
東京都で建設業許可の申請を検討している方は、建設業専門の行政書士「おさだ事務所」への相談がおすすめです。
経験豊富な専門家が、要件確認から書類作成・提出までを丁寧にサポートします。
ぜひご相談ください!
【参考サイト】
【こちらもご覧ください】