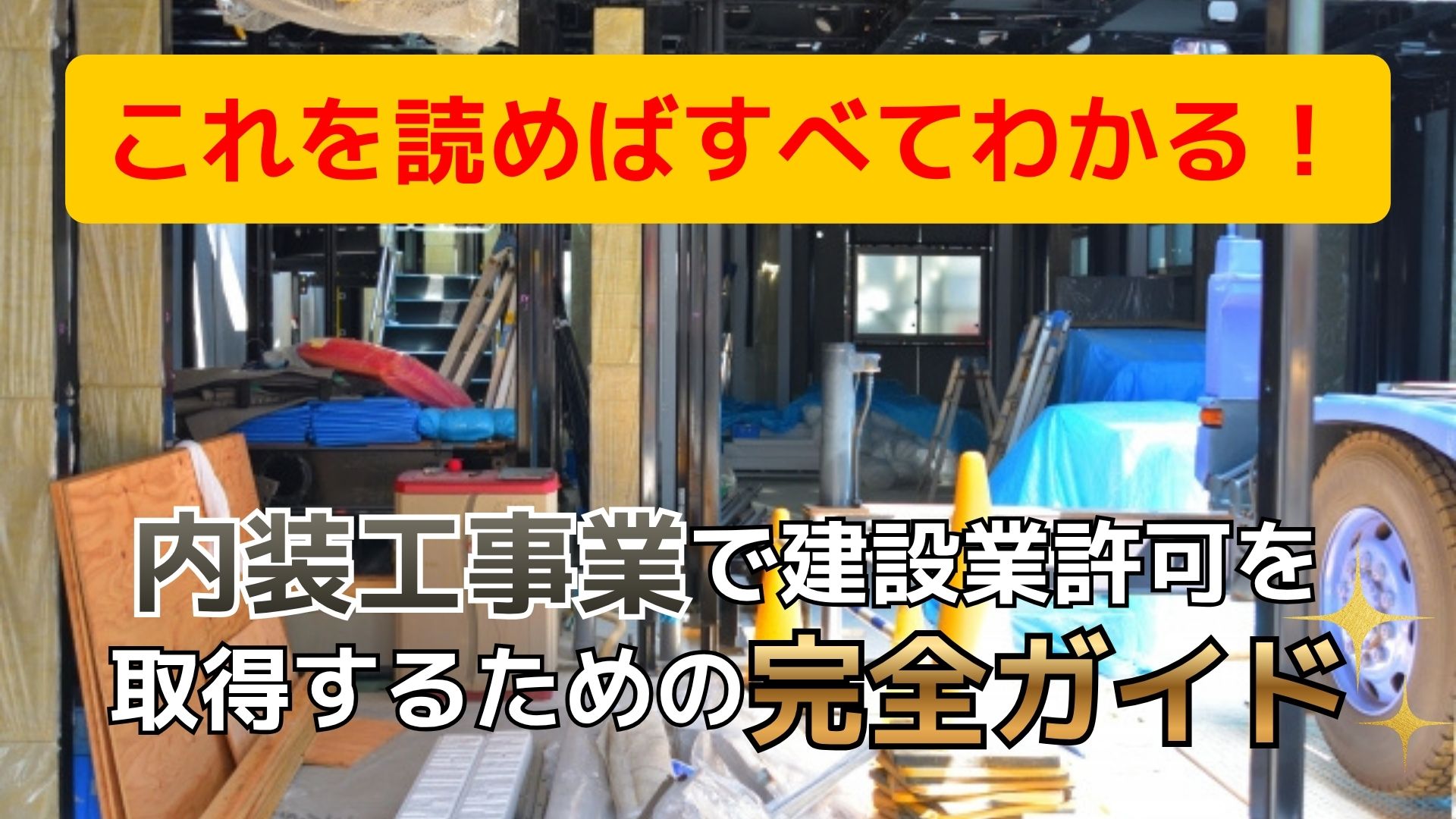内装工事業を営む際に、「建設業許可は必要なのか」「どのように取得するのか」と疑問を持つ方は多いでしょう。
特に、元請けとして案件を受注したい方や事業拡大を目指す方にとって、許可の有無は大きな判断材料となります。
本記事では、内装工事業に焦点を当て、建設業許可の基本、申請の流れ、必要な条件をわかりやすく解説します。
まずは、内装工事業の定義を確認しましょう。
内装工事業とは?

住宅や店舗、オフィスなど、さまざまな建物の内部空間を整える「内装工事」は、快適な環境づくりに欠かせない仕事です。
見た目の美しさだけでなく、使いやすさや機能性にも関わるため、空間全体の印象を左右します。
近年はリフォームやリノベーションの需要増により、内装工事の重要性が一層高まっています。
一方で、事業として始める際には、「どこまでが内装工事に含まれるのか」「他の業種と何が違うのか」と戸惑う方もいるでしょう。
まずは、内装工事業の基本的な位置づけを確認します。
内装工事業の定義と対象工事
内装工事業とは、建物内部の仕上げ工事を専門とする業種です。
主な作業は、壁や天井のボード貼り、クロス仕上げ、床材の張り替え、パーティションの設置などです。
建物の構造部分には手を加えず、完成した空間を快適で機能的に整えることを目的としています。
住宅や店舗、オフィスなどで広く求められる工事です。
ただし、家具の設置やインテリア装飾などは内装工事業の範囲外です。
内装工事の代表的な施工内容
内装工事には、建物の内部を快適で機能的な空間に整えるための多様な施工が含まれます。
具体的には次のような工事です。
• 壁紙や床材の張り替え
→ 古くなった壁紙やフローリングを新しくする
• 間取りの変更
→ 部屋を仕切ったり、広くしたりして使いやすくする
• 店舗やオフィスのデザイン施工
→ おしゃれで機能的な空間をつくる
代表的な作業としては、壁紙(クロス)の貼り替え、塗装、フローリングやカーペットなどの床材の張り替えが挙げられます。
また、天井や壁にボードを貼る作業も内装工事です。
オフィスや店舗では、パーティションの設置や間仕切りの変更といったレイアウト調整も重要な内装工事の一部です。
これらの施工は、見た目を整えるだけでなく、使いやすさや動線の改善にもつながります。
照明や什器の配置まで含めた空間設計・施工も行われ、業務の幅が広がっています。
他業種との違い
内装工事業は、建物の内部を仕上げることを目的とした業種です。
大工工事業は、柱や梁など建物の骨組みをつくる工事であり、構造部分を扱います。
内装工事は、完成した空間の仕上げや改装を行う点で異なります。
また、壁紙や間仕切りを撤去する「内装解体」は内装工事業の範囲ですが、構造に関わる解体は別途「解体工事業」の許可が必要です。
さらに、電気・空調・給排水などを扱う設備工事業は機能面の整備が目的で、内装工事は主に美観や快適性の向上を担います。
違いを理解することで、申請時の業種選択ミスを防げます。
内装工事で建設業許可が必要なケース

内装工事業を営むうえで、建設業許可が必要かどうかは、工事の内容や請負金額によって異なります。
建設業法では、一定の条件を満たす工事に対して許可取得が義務付けられており、制度を理解すれば、安心して業務を進められます。
まずは、内装工事で許可が必要となるケースを整理してみましょう。
許可が必要な金額の基準
建設業許可が必要かどうかを判断する際、最も基本となるのが「請負金額の基準」です。
建設業法では、1件の工事契約が税込500万円以上の場合、許可の取得が義務付けられています。
この金額には、材料費や下請けへの支払いも含まれるため、人件費だけで判断するのは危険です。
また、契約時点の金額で判定され、分割契約や見積もりでの回避は認められません。
内装工事でも、複数の作業をまとめて請け負うことで金額が基準を超えるケースは珍しくありません。
特に、店舗やオフィスの全面改装などでは、見積もり段階で500万円を超えることも十分に考えられます。
一方、500万円未満の工事は「軽微な工事」とされ、許可がなくても施工可能です。
ただし、金額の見誤りによって無許可工事となるリスクもあるため、契約前にしっかり確認しておくことが重要です。
許可が不要な軽微な工事の例
建設業許可が必要となるのは、税込500万円以上の工事を請け負う場合です。
それ未満の工事は「軽微な工事」とされ、許可がなくても施工できます。
内装工事で該当する例としては、壁紙の貼り替え、床材の張り替え、部分的な塗装、簡易な間仕切りの設置などが挙げられます。
これらは比較的短期間で完了し、材料費や人件費を含めても総額が基準を超えないケースが多いため、個人事業主や小規模業者でも対応しやすい工事といえるでしょう。
ただし、複数の作業をまとめて請け負う場合や、見積もりが曖昧なまま契約を進めると、知らないうちに基準を超えてしまうこともあります。
契約前には金額の確認を徹底し、制度の範囲を正しく理解しておくことが大切です。
軽微な工事でも判断を誤ると法令違反となる可能性があるため注意が必要です。
許可の有無による業務範囲の違い
建設業許可の有無によって、内装工事業者が対応できる業務の幅は大きく異なります。
許可を持たない場合、請け負えるのは税込500万円未満の工事に限られます。
壁紙の貼り替えや床材の張り替えなど、小規模な施工が中心となるでしょう。
一方、許可を取得している業者は、金額に制限なく工事を請け負うことができ、店舗やオフィスの全面改装など、大規模な案件にも対応可能です。
さらに、公共工事や法人案件では許可の有無が受注条件となるケースも多く、営業のチャンスにも差が出ます。
違いを理解すれば、自社の方針に沿った判断がしやすくなります。
内装仕上工事業としての許可取得のメリット

内装工事業を営むうえで、建設業許可の取得は単なる制度上の条件ではなく、事業の可能性を広げるためにも重要です。
とくに、今後より大きな案件に挑戦したい、元請けとしての立場を築きたいと考えている事業者にとって、許可の有無は営業活動にも大きく影響します。
許可を取得することで、受注できる工事の幅が広がるだけでなく、取引先からの信頼性も高まり、事業基盤の強化につながります。
また、制度を理解したうえで適切に許可を取得しておくことは、法令遵守の面でも安心です。
この章では、内装仕上工事業として建設業許可を取得することで得られる具体的なメリットについて解説していきます。
元請け受注や法人案件への参入
建設業許可を取得すると、内装工事業者は元請けとして大きな工事を受注できるようになります。
下請けに頼らず、自社主導で様々な案件を進められる点は大きな強みです。
特に、法人や商業施設からの依頼では、許可の有無が受注条件となることも多く、許可を持つことで選定の対象に入りやすくなります。
信頼性向上と事業拡大の可能性
建設業許可を取得することで、内装工事業者としての信頼性が高まり、事業拡大のチャンスも広がります。
行政や大手企業との取引では、許可業者であることが信頼性の証とされる場面も少なくありません。
特に法人や公共団体との契約では、許可の有無が選定基準となることが多く、営業活動の幅を広げるうえで有利に働きます。
さらに、許可業者として登録されることで、業界内での認知度や紹介の機会も増え、新規顧客の獲得にも好影響を与えます。
許可取得は将来を見据えた戦略としても検討するとよいでしょう。
補助金・融資申請での優位性
建設業許可を取得していることで、補助金や融資の申請時に有利に働く場面が増えます。
行政や金融機関は、許可業者を法令遵守や事業継続性の面で信頼できる事業者と評価することがあり、審査の際にもプラス要素となる傾向にあります。
特に、設備投資や事業拡大を目的とした補助金では、許可の有無が申請条件に含まれるケースもあるため、取得しておくことで申請の選択肢が広がります。
また、融資を受ける際にも、許可業者であることが信用力の裏付けとなり、資金調達の可能性を高める要因になり得ます。
制度活用には許可の有無が影響するため、早めに対策をしておくとよいでしょう。
建設業許可取得の要件と手続きの流れ

内装工事業として事業の幅を広げるためには、建設業許可の取得が重要です。
許可を取得するには一定の要件を満たす必要があり、申請には準備すべき書類や手続きの流れがあります。
初めて申請する方でも、ポイントを押さえて順を追えばスムーズに取得できます。
この章では、建設業許可を取得するための基本的な考え方と、申請に向けた準備の全体像を整理していきます。
まずは、制度の枠組みを理解するところから始めましょう。
経営業務管理責任者の条件
建設業許可を取得するためには、一定の経験と実績を持つ「経営業務管理責任者(常勤役員等)」の設置が必要です。
この責任者は、法人の場合は役員、個人事業の場合は事業主本人が該当します。
主な条件としては、許可を受けようとする業種または類似業種において、過去5年以上の経営業務経験があることが求められます。
経営業務とは、単なる現場作業ではなく、契約管理・資金繰り・人材管理など、事業運営に関わる実務全般を指します。
経験年数は、複数の事業所での通算も可能ですが、証明書類の整備が重要です。
なお、制度改正により、補佐的な立場での経験などによって要件を満たすケースも認められる場合があります。
申請前に自社の体制と実績を整理し、要件を満たすか確認しましょう。
専任技術者の資格・実務経験
建設業許可を取得するには、営業所ごとに「専任技術者(営業所技術者等)」を配置する必要があります。
専任技術者とは、申請する業種に関する専門的な知識と実務経験を持ち、技術面での責任を担う立場です。
専任技術者は以下のいずれかを満たす必要があり、内装仕上工事業でも同様です。
- 一級・二級の国家資格(建築施工管理技士など)を有する者(資格保有後一定年数の要件が付く場合がある)
- 指定学科卒業者+卒業後の実務経験(高卒後5年、大学卒後3年 等)
- 指定学科等に該当しない場合は実務経験10年以上
専任技術者は営業所ごとに常勤で配置し、兼任は原則認められていません。
財産的基礎・営業所・欠格要件
建設業許可を取得するには、一定の財産的基礎や営業所の整備、欠格要件に該当しないことが求められます。
財産的基礎とは、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることを指し、経営の安定性を示す要件です。
営業所については、申請業種に対応できる常設の事務所が必要で、机や電話などの設備が整っていることが確認されます。
自宅兼事務所でも認められる場合がありますが、専用スペースとして機能していることが条件です。
さらに、申請者が欠格要件に該当していないことも重要です。
具体的には、過去に建設業法違反で処分を受けた者や、成年被後見人などが対象となります。
事前に要件を確認し、書類を整えれば申請は円滑に進められます。
申請に必要な書類と準備事項
建設業許可の申請には、事前に必要な書類を整え、要件に沿った準備を進めることが重要です。
主な提出書類には、申請書、経営業務管理責任者や専任技術者の証明書類、財務諸表、営業所の写真、登記簿謄本(法人の場合)などが含まれます。
提出書類は自治体ごとに異なるため、事前に管轄窓口で最新様式を確認しましょう。
特に、実務経験や資格を証明する書類は、過去の契約書や工事台帳などをもとに整える必要があります。
また、営業所の要件を満たしているかを確認するため、事務所の外観・内部の写真も求められます。
提出書類は自治体ごとに細かな違いがあるため、事前に管轄窓口で最新の様式や記載方法を確認しておくと安心です。
丁寧に準備すれば、申請はスムーズに進みます。
許可取得後の更新・変更と注意点
建設業許可を取得した後も、継続的な管理と手続きが求められます。
許可は5年ごとの更新制で、有効期限前に更新申請を行う必要があります。
商号・役員・営業所の所在地などを変更した場合は、定められた期間内に変更届を提出します。
手続きを怠ると行政指導や許可取消の対象となるため注意が必要です。
さらに、毎年の決算終了後には「事業年度終了報告書」の提出も義務付けられています。
過去5年分の事業年度終了報告書がされていない場合は、更新申請ができません。
許可取得後も制度を理解し、適切に管理を続けることが重要です。
内装工事業で建設業許可を取得するなら、「おさだ事務所」へご相談ください。
現場経験豊富な行政書士が、申請から書類作成まで丁寧にサポートします。
【参考サイト】
【こちらもご覧ください】
建物を壊すだけじゃない?解体工事の基本・建設業許可・解体工事業登録制度まで徹底解説! | 建設業専門 おさだ事務所
【建設業許可】機械器具設置工事業の取得はなぜ難しい?基本と準備のポイントを解説! | 建設業専門 おさだ事務所
【登録電気工事業】建設業許可を持っているだけで電気工事はできない?その理由を解説 | 建設業専門 おさだ事務所