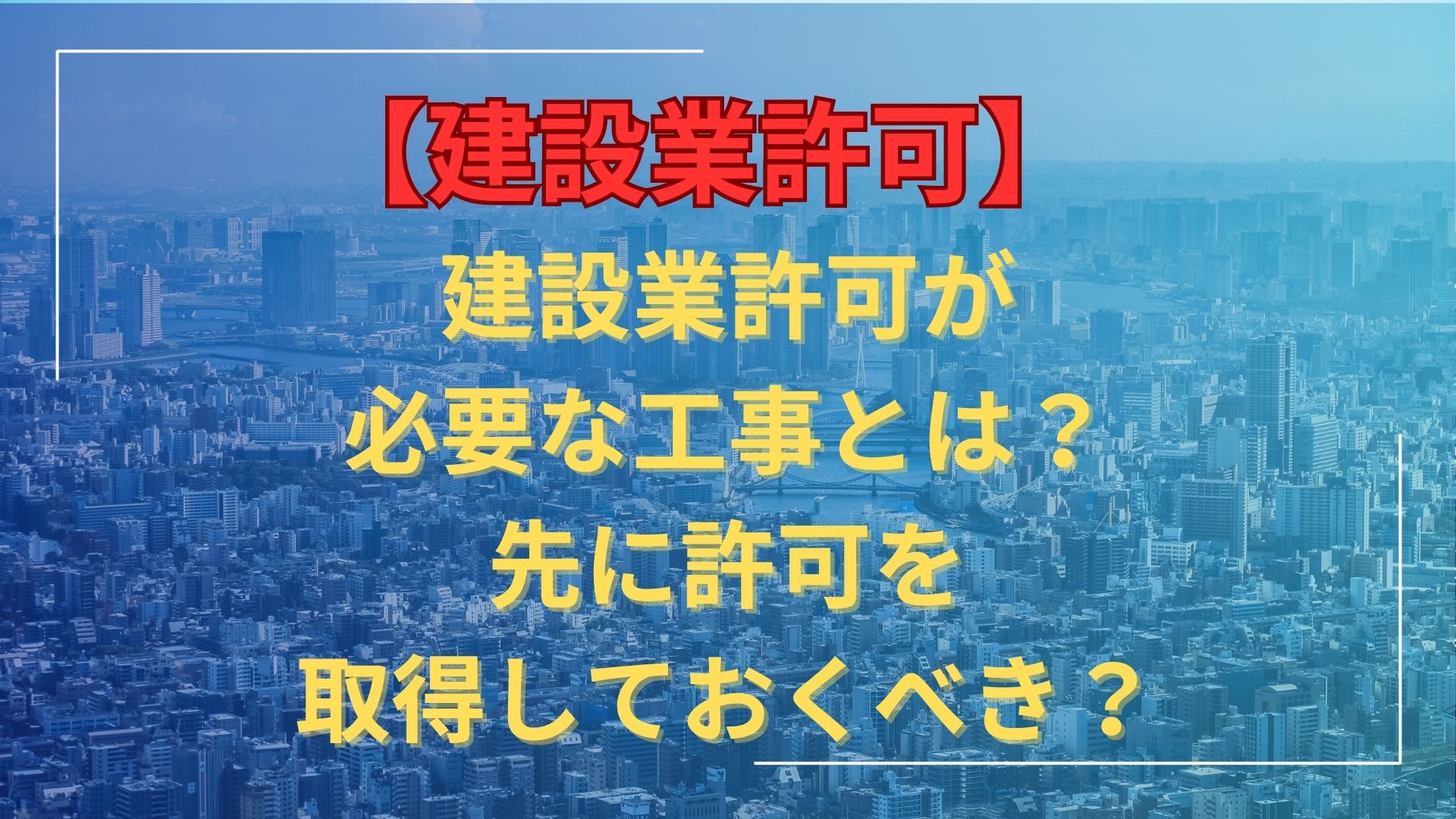建設業を営む方は取引先から建設業許可の有無を聞かれることが多いと思います。
また、大きな工事案件が入ってきそうな時に自社に建設業許可がなくて請けることができなかったという話もよくあることです。
今回は、建設業許可の基本とその必要性、取得の時期についてお話しします。
建設業許可とは?わかりやすく解説!

建設業許可を簡単に説明すると、「安全かつ適切な工事を行うことができる、国や都道府県からのお墨付きの建設業者」の証です。
国や県が保証してくれているので、建設業許可を持っている会社には安心して工事を任せられるということですね。
そのため、建設業許可を取得するには、国が決めた数々の要件をクリアしないといけません。
建設業許可の要件とは
建設業許可の要件は主に下記のものとなります。
- 経営業務の管理責任者の設置(建設業界において経営責任の経験が必要)
- 専任技術者の設置(建設工事に関する一定の資格や実務経験が必要)
- 誠実性を有していること(法律違反の経歴がない)
- 財産的基礎を有すること(一定の資本金や自己資本が必要)
- 欠格要件に該当しないこと(暴力団関係者でないなど)
難しすぎてよくわからない、という方も多いかと思います。
しかし、これらの要件を満たさないと許可を取得することはできません。
許可を申請する際には、申請先の官公庁にてこれらの要件を細かくみられます。
要件を満たすための確認書類も提出しなくてはなりません。
建設業許可はなぜ必要?
建設業許可は発注者を守るために制定されたものです。
建設業許可を持っている業者は、技術面でも資金面でも保証がされています。
建設工事は安全性や品質が求められるものです。
資格を持たない人が行った工事、適切な手順で行われていない工事では施工が問題となります。
資金繰りの良くない建設業者が工事をすれば、経営不振などにより工事が継続できなくなる危険性もあるのです。
また、建設業許可は5年に一回の更新申請が必要です。
これは建設業許可業者が、継続して要件を満たしているかの確認をするためのものでもあります。
更新の際に経営管理責任者や専任技術者が継続して在籍しているかチェックされます。
これらが建設業許可が必要な理由なのです。
建設業許可が必要な工事と不要な工事

ある一定の条件を満たす工事をする場合に、建設業許可は必ず必要となります。
このような工事を許可を持たずにしてしまうと建設業法に反してしまい、営業停止などの処分を受ける可能性もあります。
しかし、すべての工事が許可の対象となるわけではなく、許可が不要なケースもあります。
ではどういった工事に許可が必要か不要か、具体的に見ていきましょう。
請負金額が税込で500万円以上となる建設工事
許可が必要:工事の請負金額が税込500万円以上(建築一式工事を除く)
- 付帯工事、追加工事を含む
- 材料費や運送費を含む
- 下請工事についても許可が必要
建設業者は500万円という金額を目にすることが多いかと思います。
建設業許可が必要な不要化の重要な金額ラインだからです。
ここで注意が必要なのは「税込金額」ということです。
すなわち、税抜だと454万5454円(消費税10%)となります。
また一つの工事について、あえて請求書を複数に分けて金額を税込500万円未満の二つの契約とすることは認められません。
付帯工事も一つの工事として判断されることがありますので、注意が必要です。
途中で追加工事が発生し結果的に500万円以上となってしまった場合も、許可が必要な工事となってしまいます。
さらに、材料費や運送費はこの請負代金に含めなくてはなりません。
材料費がかからない工事に関しては、それに相当する金額を加算した合計で請負代金を算出しなければなりませんので注意が必要です。
許可は元請け業者のみが持っていればよいものではありません。
下請工事をする場合も、税込500万円以上の工事であれば許可が必要になります。
軽微な工事は許可が不要
許可が不要:税込500万円未満の建設工事(建築一式工事を除く)
上記の工事を、「軽微な工事」といいます。
このような工事をする際に建設業許可は必要ありません。
具体例だと、管工事であれば水道の蛇口交換や排水管の修理など、電気工事であればスイッチやコンセントの交換などです。
ここで注意が必要なのは、500万円未満という点です。
「未満」は500万円を含みません。
一方、「以下」は500万円を含みます。
中には稀に500万円以下と間違えて記載がされていることがあります。
未満と以下の定義を間違えないようにしましょう。
建築一式工事に関しては条件が異なる
許可が必要:1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事の建築一式工事
- 付帯工事、追加工事を含む
- 材料費や運送費を含む
このような建築一式工事には、建設業許可が必要です。
建築一式工事とは、いくつもの工程を一つに括って統合的に行う建築工事のことで、新築工事や大規模な増改修工事をいいます。
一式工事は元請工事のみとなります。
下請工事はなく、建築一式工事の下請はすべて専門工事に分類されます。
また建築一式工事について、軽微な工事の定義は下記のようになります。
許可が不要:建築一式工事のうち、1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事又は延べ面積150 ㎡未満の木造住宅工事
請け負った工事がどの業種に該当するか、請負金額はいくらか、付帯工事や追加工事があるのかは必ず事前に確認をしておきましょう。
建設業許可が不要な工事
軽微な工事のほかにも、許可が不要な工事があります。
許可が不要:自社施工工事(自社の建物を修繕・改修する場合など)
許可が不要:日常的な修繕やメンテナンス(小規模工事や補修工事)
自社所有の建物や設備を修繕・メンテナンスする場合は、工事の規模にかかわらず建設業許可は不要です。
ただし、他社の依頼を受けて行う場合は、請負金額によって許可が必要になることもあります。
許可が不要でも、契約内容の明確化や安全管理には十分注意が必要です。
また自社施工であっても、安全管理は徹底しなくてはなりません。
500万円未満でも届出がないとできない建設工事
届出が必要:電気工事
届出が必要:浄化槽工事
建設業者が届出をしておかないとできない工事があるのをご存じでしょうか。
電気工事や浄化槽工事がそれに該当します。
これらは工事をする際に、金額にかかわらず登録や届出を国や県にしておかなくてはなりません。
建設業許可を所有している場合でも、この届出は必要です。
電気工事業の届出
工事の種類や業務範囲に応じて「電気工事業の届出」が必要になります。
これは、電気工事士法や電気工事業法に基づき、国や都道府県に対して事業者が適切な技術基準を満たしていることを届け出る制度によるものです。
電気工事業者は大きく分けて4種類あります。
- 登録電気工事業者(建設業許可を持っていない業者)
- みなし登録電気工事業者(建設業許可を持っている業者)
- 通知電気工事業者(建設業許可を持っていない業者)
- みなし通知電気工事業者(建設業許可を持っている業者)
「登録電気工事業」とは、自家用電気工作物以外の電気工作物の工事をする場合をいいます。
「通知電気工事業」とは、自家用電気工作物の工事のみ行う場合をいいます。
浄化槽工事の届出
浄化槽工事とは浄化槽の設置又はその構造や規模の変更をする工事をいいます。
浄化槽を入れ替える工事も含みます。
浄化槽工事を請け負う事業を営もうとする業者は、営業所ごとに浄化槽設備士を設置し、実際に工事をしようとする地域を管轄する官公庁に対して、登録又は届出をする必要があります。
浄化槽工事業者は大きく分けて2種類あります。
- 登録浄化槽工事業者(建設業許可を持っていない業者、または土木・建築・管工事以外の許可しかない建設業許可業者)
- 特例浄化槽工事業者(土木・建築・管工事の許可をもつ建設業許可業者)
また、浄化槽の設置や維持管理には、電気設備が不可欠です。
特に、浄化槽のブロワー(送風機)やポンプなどを動作させるための電気工事をする場合、上記の「電気工事業の届出」が必要になることもあります。
許可が必要になってから取得するのでは遅い

建設業許可はすぐに取れるものではありません。
建設業を営む業者にとって、許可を持っているのとそうではないのでは選択の幅がかなり変わります。
しかし、許可を取るためには要件を満たさなくてはなりません。
許可を維持するには、費用も人材も必要になります。
建設業許可が必要になるタイミングとは?
- 500万円以上の建築工事を請け負うとき
- 元請けから建設業許可を求められたとき
- 公共工事の入札に参加するとき
- 事業拡大のために大きな案件を受注するとき
上記の場合、建設業許可が必要になります。
特に公共工事の入札を行いたいのであれば、建設業許可を持っているだけではできない場合もあります。
経営事項審査や入札参加資格申請といった、別の手順が必要になります。
「今は500万円未満の工事しか請け負わないから許可はいらない」と考えていても、この先に許可が必要になる可能性もあります。
建設業許可を取得しておかないとどうなるか
建設業許可を持っていないと様々な問題がでてきます。
いざというときに困らないようにしておく必要があります。
ではどのような問題が考えられるのか見ていきましょう。
急に大きな仕事が来ても受けられない
許可がないと大きな案件を逃してしまうかもしれません。
また、許可がない状態で500万円以上の工事を受注すると違法行為となり、発注者からの信用を失う可能性があります。
許可取得には時間がかかる
建設業許可の取得には、最短でも1〜2ヶ月、長ければ半年以上かかります。
申請書類は複雑で作成が難しいものです。
また必要な書類を揃えるのに時間もかかります。
行政での手続きにも時間がかかり、書類を申請してからの標準処理期間は1~2か月となっています。
「今すぐ許可が必要!」となってもすぐには取得できず、絶好のチャンスを逃してしまう可能性があります。
建設業許可の取得要件の一つに、自社に常勤かつ該当工事の業種に関する有資格者の設置というものがあります。
建設業の経営責任者として、5年以上の経験を有する役員等も必要です。
人材を育てたり確保するのもすぐにできるものではありません。
一定の財産要件も満たす必要があります。
すぐに準備できるものもありますが、これらの要件をクリアするのに何年もかかるものもあるのです。
将来を見越して、建設業許可が取得できるように早めに準備しておくのがよいでしょう。
元請け・取引先からの信頼を失う
元請け企業や取引先によっては、「建設業許可を持っている会社のみ」と契約条件を定めている場合があります。
許可がないと大手企業や公共工事案件との取引が難しくなり、取引先に迷惑をかけたり事業の成長が制限されてしまう可能性があります。
取引先から許可が必要と言われたら、まずはいつまでに許可を取得すればよいか確認しておきましょう。
建設業許可の要件が整っていたとしても、申請してから許可が下りるまでに早くても2か月程は要してしまいます。
もし許可がない状態で下請契約を結び工事をした場合、建設業法に違反します。
さらに下請業者が許可の必要な工事を無許可で行った場合、その元請会社も処罰の対象となってしまいます。
取引先との信頼を失うことになりかねませんので、無許可での工事は絶対にやめましょう。
融資や資金調達が不利になる
金融機関や投資家は、建設業許可を持っているかどうかを企業の信頼性や安定性の指標として判断します。
許可がないと、事業拡大に必要な融資や資金調達がスムーズに進まない可能性もあります。
建設業許可は建設工事を行うためだけではなく、このように社会的信頼を得るためにも必要なツールともなるのです。
まとめ
建設業許可は建設工事の安全性や品質を守るために必要な制度です。
建設工事にはこの許可が必要なものと不要なものがあります。
そして建設業許可を取得するには様々な要件をクリアしなくてはなりません。
できるものからでよいので前もって準備しておいたり、許可の知識を調べておくとよいでしょう。
とはいっても、建設業許可を取得するには費用や労力のかかるものですので、状況に併せて検討する必要もあります。
今は許可が不要であっても、500万円以上の工事を請ける可能性がある、もしくは将来受注の規模を大きくしていきたいなどという場合には、前もって建設業許可を取得しておくことをおすすめします。
東京都限定で建設業許可を専門に扱う【おさだ事務所】は多くのお客様の「困った!」に寄り添い、対応してきた実績があります。
そして、当事務所は行政書士事務所でもあり社会保険労務士事務所でもあります。ですので、許可取得後の更新や年度報告以外に、面倒な社会保険手続きもお引き受け可能です。会社のお金づくりも当事務所の強みの一つです。
力になれる自信があります。お気軽にご相談ください。