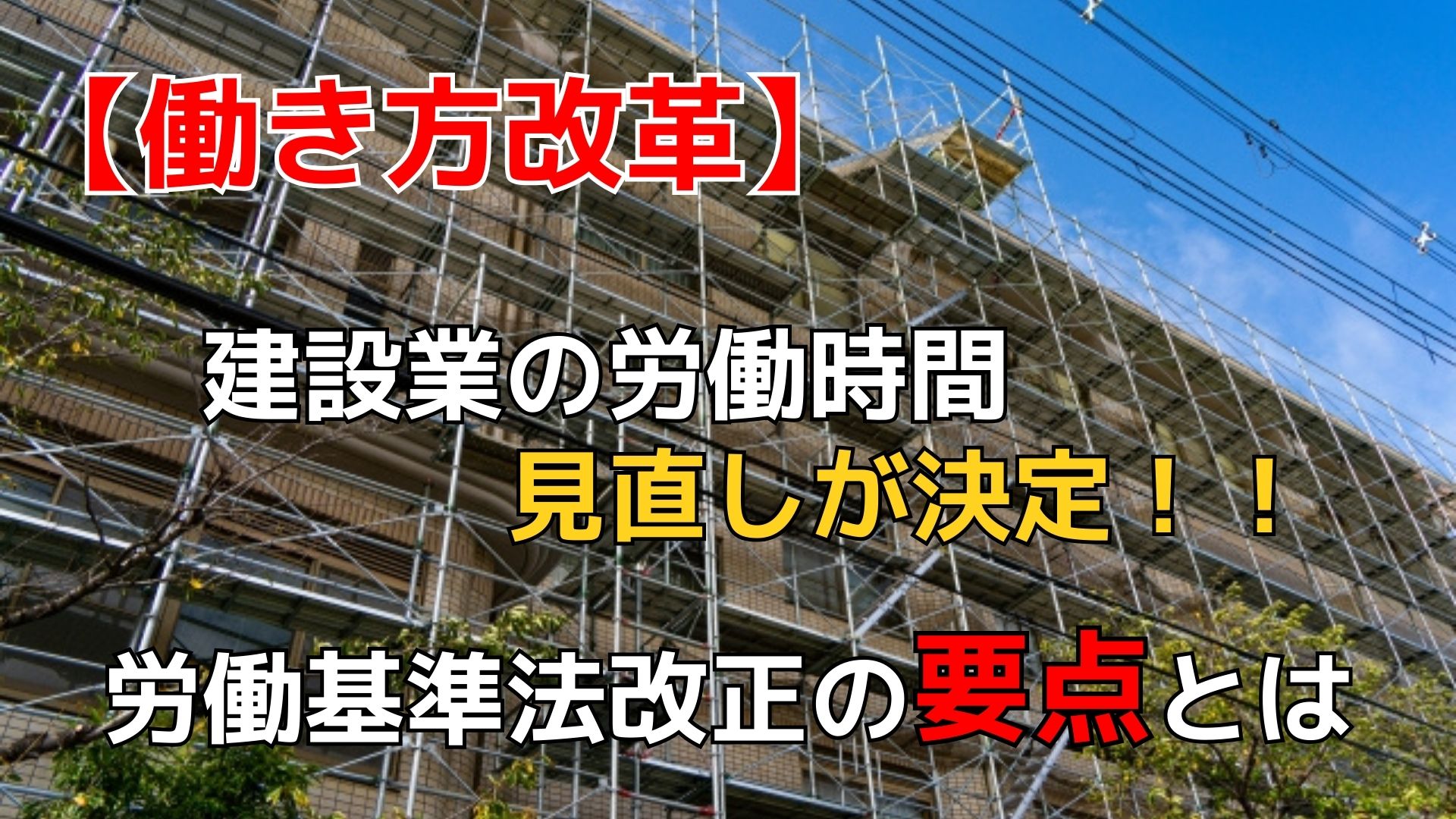建設業の現場では、長時間労働や厳しい工期が長年の課題として指摘されてきました。
こうした状況を大きく変えるために、2018年に成立した働き方改革関連法に基づき、2019年に労働基準法が施行されました。
建設業への上限規制は5年の猶予を経て、2024年4月から適用されています。
法改正は単なる制度変更にとどまらず、工期の組み立て方、人員配置、外注管理、勤怠管理の方法など、建設業の働き方そのものに大きな影響を与えます。
今回は法改正の内容から現場で起きる変化、企業が取るべき対策までをわかりやすく整理します。
労働基準法が改正!建設業における重要ポイント

建設業の働き方を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変わりつつあります。
特に労働基準法改正は、業界全体の働き方を見直すきっかけとして注目されました。
また、建設業法・入契法も段階的に導入されており、実際の契約・工期・価格のルール化がされました。
この章では、労働基準法改正についてのポイントを解説します。
労働基準法改正の主な内容
建設業にとってこの法改正は、「これまでと同じ働き方では通用しなくなる」ほど大きな転換点となりました。
まずは、どのような制度変更が行われたのか、押さえておくべき基本ポイントを確認する必要があります。
特に影響が大きい改正内容を順に見ていきましょう。
残業時間の上限規制が適用される
建設業にとって最も大きなインパクトとなるのが、残業時間の上限規制が本格的に適用されたことです。
これまで建設業は「働き方改革関連法」の一部規制が猶予されていましたが、その猶予が終了しました。
これにより、以下のような明確な残業時間の上限が適用されます。
- 原則として月45時間(年6回)、年360時間まで
- 特別条項付き36協定を結んだ場合でも年720時間以内
- 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
- 月100時間未満(休日労働を含む)
これらは一般企業と同じ基準であり、「長時間労働で工期を調整する」従来のやり方が通用しなくなります。
36協定が厳格化する
36協定とは、企業が従業員に時間外労働や休日労働をさせるために、労使で締結し、労基署へ届け出る必要がある協定のことです。
法改正により、建設業でも次のような制度上のルールが明確に求められるようになりました。
- 特別条項の発動要件が明確であること
- 特別条項の回数制限(年6回以内)を守ること
- 協定内容と実際の働き方が一致していること
- 協定の締結・届出手続きが適正であること
- 労働者代表の選出が適正であること
「36協定を結んでいれば残業させられる」時代から、「協定内容と運用が厳しくチェックされる」時代に変わったという点が最も重要です。
違反時の罰則が強化される
「上限を超えた残業」や「不適切な36協定の運用」が、明確に罰則対象になります。
具体的には次のような罰則が挙げられます。
- 違反した場合は「6か月以下の懲役」または「30万円以下の罰金」などの刑事罰の対象になる
- 労働基準監督署による是正勧告・指導の対象となる
- 悪質なケースでは企業名が公表される(企業名公表制度)
協定を出しているかどうかだけでなく、実態がルールに沿っているかが厳しく見られるようになります。
法改正が建設現場に与える影響

法改正は、制度が変わるだけでなく、建設業の現場運営そのものに大きな影響を及ぼします。
工期の組み立て方や人員配置、外注管理、さらには現場管理者の働き方まで、これまでの前提が通用しなくなる場面が増えていきます。
ここからは、現場で実際にどのような変化が起きるのかを具体的に見ていきます。
工期・工程管理の見直しが必要になる
残業時間の上限が厳しくなることで、遅れを残業で取り戻すことが難しくなります。
天候不良や資材の遅れ、外注の作業遅延など、これまで残業で吸収していた要因がそのまま工期の遅れにつながるようになります。
また、作業時間の制約が増えることで、1日の作業量を調整しづらくなります。
さらに、工程に余裕(バッファ)を持たせないと現場が回らなくなるという課題も生まれます。
人員配置・外注管理に影響する
忙しい時期だけ残業で乗り切るという調整が難しくなるため、作業量に対して人員が足りない現場では、継続的に遅れが生じます。
また、外注先の労働時間も制限されるため、元請が工程を一方的に組むことができなくなります。
さらに急な増員で対応することが難しくなるため、事前に余裕を持った人員計画を立てなければ、工期遅延のリスクが高まります。
複数現場を抱える企業では、どの現場にどれだけ人を割くかを日々見直す必要もあります。
現場管理者の負担が増える
残業時間の上限が厳しくなることで、現場管理者はこれまで以上に細かい調整や管理を求められるようになります。
現場の進捗を常に把握し、遅れが出そうな場合はすぐに対応策を検討するという負担も増えます。
さらに、外注先との作業量の調整やスケジュールのすり合わせを頻繁に行わなければ、現場が回らなくなります。
加えて、勤怠管理の確認作業が増えるという負担も生じます。
勤怠管理の見える化が求められる
現場では勤務時間を正確に把握しなければ、工期や安全管理に支障が出るようになります。
これまでのように紙のタイムカードや自己申告に頼っていると、実際の労働時間と記録がズレやすく、現場管理者が状況を把握できない場面が増えていきます。
まず、現場ごとの出退勤状況をリアルタイムで確認する必要があります。
さらに、作業員の労働時間が上限に近づいているかどうかを早めに把握しないと、急に作業を止めざるを得ないというリスクも生まれます。
これまでなら多少の残業で調整できましたが、それができないため、勤怠状況を見ながら日々の作業計画を細かく調整しなければなりません。
労働時間の見直しが必要な理由

建設業で労働時間の見直しが求められている背景には、現場の安全性や品質、企業としての信頼性、そして人材確保といった課題があります。
長時間労働を前提とした働き方では、事故や品質低下のリスクが高まり、企業としての法令遵守や人材の定着にも影響が出てしまいます。
ここからは、労働時間を見直す必要がある理由を説明していきます。
長時間労働が安全リスクを高めるため
建設現場では、長時間労働が続くと作業員の集中力や判断力が低下し、事故やヒューマンエラーが発生しやすくなります。
特に建設業は高所作業、重機操作、危険物の取り扱いなどリスクの高い作業が多いため、わずかな判断ミスが重大災害につながる可能性があります。
注意力が散漫になることで、周囲の危険に気づくのが遅れ、巻き込まれ事故や接触事故のリスクも高まります。
また睡眠不足により、反応速度の低下や判断の遅れが顕著になり、災害発生率が上昇することが知られています。
品質確保のために適正な労働時間が必要になるため
建設現場では、施工品質を安定させるために、作業員が十分な集中力と判断力を保てる労働時間で作業することが大切です。
長時間労働が続くと、細かな確認作業や丁寧な施工が疎かになりやすく、仕上がりの精度が低下するリスクが高まります。
特に建設業は、寸法の誤差や材料の扱い方ひとつで品質に大きな差が出るため、疲労による注意力の低下は直接的に施工品質のばらつきにつながります。
また、検査工程でも疲れた状態では見落としが増え、配筋の確認漏れや仕上げの不備など、後工程で発覚するミスが増加します。
施工ミスや確認漏れが原因でやり直しが発生すると、現場全体の効率が下がり、結果的に工期が圧迫されるという悪循環が生まれます。
法令遵守と企業リスクの回避が求められるため
労働時間の上限を超える働かせ方を続けた場合、行政指導や是正勧告の対象となり、改善が行われなければさらに厳しい対応が取られる可能性があります。
悪質なケースでは、罰則の適用や、企業としての信頼を大きく損なう結果につながります。
さらに、重大な違反が確認された場合には、企業名が公表されるリスクもあります。
企業名の公表は社会的信用の低下につながり、取引先からの評価や採用活動にも影響を及ぼします。
特に建設業では元請・下請の関係が密接なため、信用の失墜は事業全体に波及しやすい特徴があります。
人材確保・離職防止のために働き方改革が不可欠なため
建設業では、慢性的な若手不足や採用難が続いており、働き方の改善は人材を確保し離職を防ぐためにも重要です。
長時間労働が常態化している職場では、若手が定着しにくく、採用してもすぐに辞めてしまうケースが多く見られます。
また、ワークライフバランスを重視する傾向が強まり、長時間労働が前提の職場は敬遠されやすくなっています。
そのため、労働時間を適正化し、無理のない働き方を実現することが、採用活動においても大きなアピールポイントになります。
さらに、既存の従業員の定着率を高めるためにも、働き方改革は欠かせません。
建設業が行うべき労働時間管理

労働時間の上限規制が本格的に適用されると、建設業では従来の「現場の努力」や「長時間労働で調整する」働き方が通用しなくなります。
そのためには、勤怠の把握方法や現場管理の効率化、協力会社との連携など、複数の取り組みを組み合わせて進める必要があります。
ここからは、建設業が実際に取り組むべき労働時間管理のポイントを、具体的な方法ごとに解説します。
勤怠管理をデジタル化する
建設業で労働時間管理を適正に行うためには、紙や口頭での申告に頼る方法では限界があります。
現場が複数に分かれ、協力会社も多数関わる建設業では、誰が・どこで・何時間働いたのかを正確に把握しなければなりません。
その中心となるのが勤怠管理のデジタル化です。
- ICカードで出退勤を正確に記録する
- スマホアプリで現場ごとの勤怠をリアルタイムに把握する
- クラウドで勤怠データを一元管理する
ICカードを使った勤怠管理は、現場のゲートや事務所にカードリーダーを設置し、作業員が出入りするたびに打刻する方法です。
出退勤の記録が自動で残り、不正打刻や記録漏れが減るなどのメリットのほかに、現場ごとの労働時間を正確に把握できます。
スマホアプリを使う方法は、現場が分散している建設業と相性が良いと言われています。
GPSやQRコードで現場ごとの打刻が可能で、現場監督がリアルタイムで出勤状況を確認できます。
協力会社の勤怠も共有しやすく、現場の状況に合わせて柔軟に運用できます。
36協定を見直す
建設業で労働時間を適切に管理するためには、現場の実態に合った36協定を結び、正しく運用することが重要です。
建設現場は天候や工程の遅れなどで労働時間が変動しやすく、繁忙期が明確でないこともあります。
ここで特別条項を使う条件を「工期が迫っている」「天候で作業が遅れた」など、実際に起こりやすい状況に合わせて具体的に決めておく必要があります。
また、現場監督と作業員では業務内容や忙しくなる時期が異なるため、職種ごとに協定内容を分けるなど、実態に沿った工夫も求められます。
現場監督の負担を減らす
現場監督は工程調整や安全管理に加え、日報や安全書類の作成、勤怠確認など多くの事務作業を抱えており、これが長時間労働の大きな要因になっています。
労働時間の上限規制に対応するためには、こうした「非効率な業務」を減らし、現場監督が本来の管理業務に集中できる環境を整える必要があります。
そこで、書類のデジタル化によって転記作業や提出・回収の手間を減らし、クラウドで情報を一元管理することが求められます。
これにより、本社・現場・協力会社が同じデータをリアルタイムで共有できます。
また、出退勤状況や現場の進捗を遠隔で確認できれば、現場間の移動時間を削減でき、監督者が本来の管理業務に集中しやすくなります。
協力会社との連携を密にする
建設業の労働時間管理では、元請だけが適正化に取り組んでも十分ではありません。
実際の作業を担う協力会社の労働時間が把握できていなければ、工程管理や36協定の運用が成り立たず、結果として上限規制を超えてしまうリスクが高まります。
そのため、協力会社との連携を強化し、労働時間に関する情報を共有しながら進める仕組みを整える必要があります。
具体的には下記のものに取り組むとよいでしょう。
- 勤怠データの共有ルールを作る
- 工程会議で労働時間を議題にする
- 上限超過のリスクがある場合は作業量を調整
- 安全書類・資格情報をクラウドで共有
よくある質問(FAQ)

建設業では職種ごとに36協定を分ける必要がある?
必須ではありませんが、現場監督と作業員で繁忙期が異なる場合は分けた方が実態に合います。
労働時間の傾向が違う場合は、協定を分けることで運用しやすくなります。
協力会社の労働時間も元請が管理しなきゃならない?
元請は協力会社の「管理」をするのではなく、「把握と調整」をします。
協力会社の労働時間が上限に近い場合、工程調整や作業量の見直しを求めるようにしましょう。
36協定を結んでいれば、上限を超えて残業できますか?
残業はできません。
特別条項付き36協定を結んでいても、「年720時間」「単月100時間未満」「複数月平均80時間以内」は絶対に超えられません。
勤怠管理は紙のままでも問題ない?
法律上は禁止されていませんが、正確な労働時間の把握が難しくなるためおすすめできません。
上限規制に対応するには、ICカード・アプリ・クラウドなどのデジタル化が現実的です。
災害復旧工事は残業上限の対象になりますか?
災害復旧・復興工事は一部の規制が緩和されますが、完全に除外されるわけではありません。
主に下記の場合に限り、上限規制の一部が適用除外となります(労基法139条第1項および厚労省通知)
- 災害により被害を受けた道路・鉄道の復旧
- 仮設住宅や復興支援道路の建設
ただし、「月100時間未満」「複数月平均80時間以内」は適用なしですが、「年720時間」「月45時間超は年6か月まで」は適用されます。
工期が間に合わない場合はどうすべき?
早めに発注者へ状況を説明して工期の見直しを相談することが大切です。
そのうえで、協力会社とも作業量や人員の調整を行い、無理のない工程に組み直します。
残業で対応することは基本的にはできません。
【参考サイト】