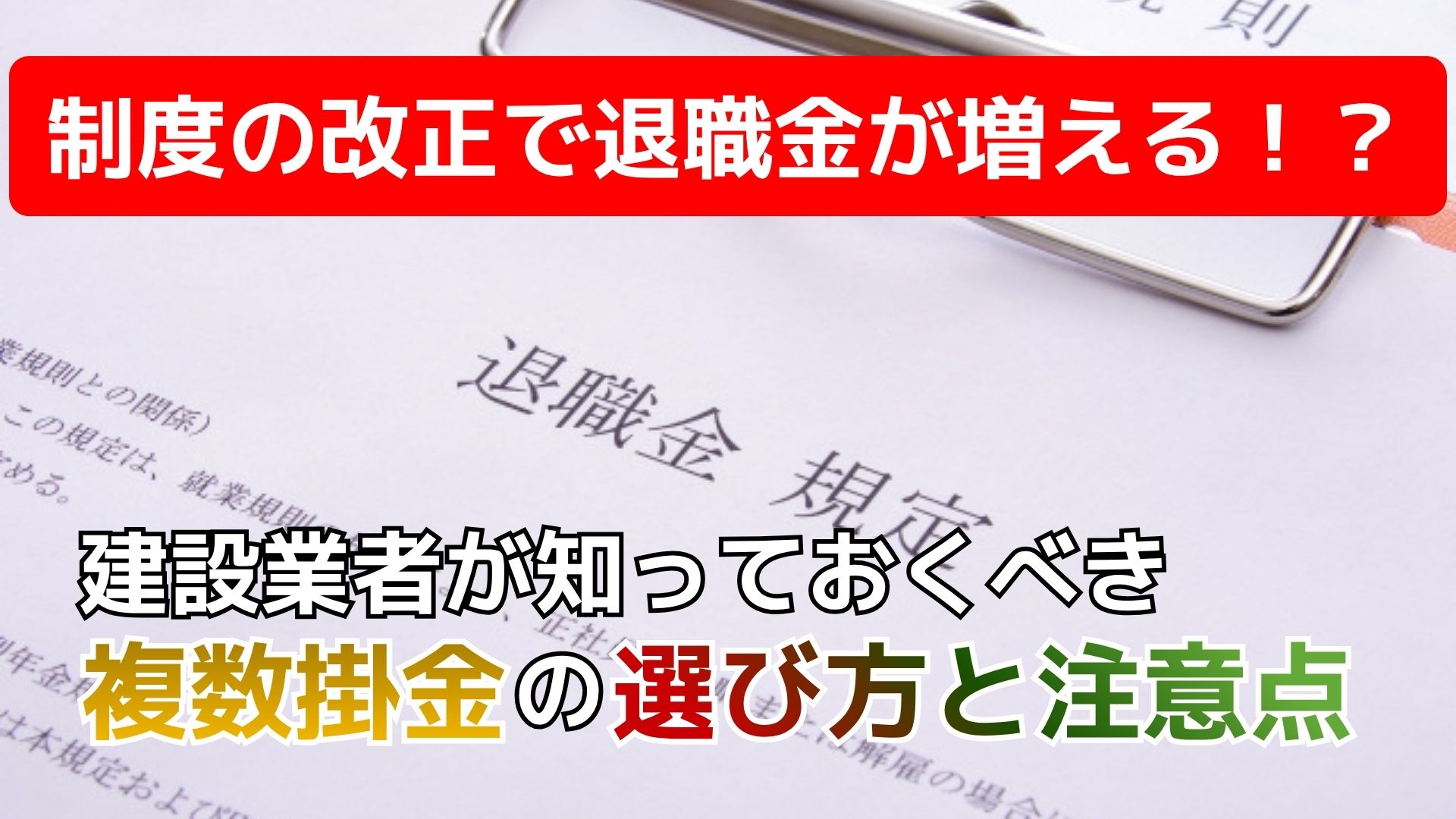建設業界における退職金制度「建退共」に大幅な改正が検討されています。
厚生労働省が建設業退職金共済制度の見直しを進めており、今後、一律だった掛金制度に複数掛金の選択肢が加わる可能性があります。
長期就労者への待遇改善や若手人材の定着を図る施策としても注目されています。
とはいえ、事業主が適切に対応するには、改正内容の正確な理解が欠かせません。
今回は、建退共制度の改正ポイントと複数掛金の仕組みをわかりやすく解説し、建設業者が押さえておくべき実務対応を紹介します。
建退共制度とは?

建設業で安心して長く働ける環境を整えるうえで、退職金制度は欠かせません。
その中でも「建退共制度」は、国が創設した制度で、勤労者退職金共済機構が運営しています。
ただ、名前は知っていても、どんな制度なのか詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか。
制度改正の話に入る前に、まずは土台となる知識をしっかり押さえておきましょう。
建退共の制度概要と仕組み
建退共制度とは、建設業で働く人々の退職金を国が支援する共済制度です。
正式には「建設業退職金共済制度」と呼ばれ、厚生労働省が所管しています。
事業者が掛金を納付することで、労働者の退職時にまとまった退職金が支給される仕組みです。
この制度では、労働者ごとに「共済手帳」が発行され、就労日数に応じて掛金証紙が貼付されます。
近年では電子申請方式も普及しており、電子申請ログイン率は26.38%(令和6年11月時点)となっています。
また、掛金は全額が損金算入できるため、事業者にとっても税務上のメリットがあります。
制度の運用は全国建設業退職金共済団が担い、公共工事では加入が推奨される場合もあります。
建退共は建設業界の雇用安定に貢献しています。
加入対象となる事業者と労働者
建退共制度に加入できるのは、建設業に従事する事業者と、その現場で働く労働者です。
具体的には、元請・下請を問わず、建設工事に直接従事する技能者が対象となります。
常用雇用だけでなく、日雇いや短期契約の労働者も含まれます。
一方、設計や事務職など、現場作業に直接関わらない職種は基本的には対象外です。
また、法人・個人事業主を問わず、建設業許可の有無にかかわらず加入できます。
なお、近年では一人親方の加入ニーズも高まっており、任意組合を通じた加入方法が整備されています。
個人でも退職金制度を利用しやすい環境が整ってきています。
このように、対象範囲は広く設定されているものの、制度の趣旨に沿った職種であるかどうかを確認することが重要です。
共済手帳と証紙の役割
建退共制度では、労働者ごとに「共済手帳」が交付されます。
この手帳は、退職金の記録台帳として機能し、就労日数や掛金の履歴を管理するために重要です。
現場で働いた日数に応じて、事業者が掛金証紙を貼付することで、退職金の積立が進んでいきます。
証紙は、掛金を納付した証明としての役割を果たします。
1日につき1枚貼付する形式が基本で、証紙の枚数が退職金額に影響します。
ただし、貼付については、深夜業務や労働時間8時間未満などの場合の取り扱いに注意しましょう。
電子申請方式の普及
近年、建退共制度では電子申請方式の導入が推奨されています。
従来の証紙貼付による運用に比べ、事務作業の効率化や記録の正確性向上といった利点があります。
しかし、電子申請による掛金納付率は、令和6年11月時点で4.74%にとどまっています。
電子申請は、複数現場を管理する事業者にとっては、手帳の回収や証紙の貼付作業が不要になるため、業務負担の軽減につながるでしょう。
さらに、就労日数の集計が自動化されるため、労働者の退職金管理もスムーズになります。
導入には事前の登録や操作環境の整備が必要です。
初めて利用する場合は、マニュアルやサポート窓口の活用がおすすめです。
建退共制度の改正

建設業界では、働き方や雇用環境の変化に伴い、退職金制度にも見直しの動きが広がっています。
とくに「建退共制度」は、国が支援する仕組みであることから、制度改正の影響が広範囲に及ぶ可能性があります。
この章では、改正に向けた議論の背景や制度見直しのポイントについて整理していきます。
まずは、どのような課題が浮上しているのかを確認してみましょう。
複数掛金制度の導入検討
建退共制度では、2025年9月に複数掛金制度の導入に関する最終とりまとめ案が報告されました。
制度改正では、複数掛金制度の導入、民間工事への普及、電子化の推進が重点項目です。
CCUSと連携し、技能レベルに応じた掛け金設定や電子ポイント方式の導入も検討されています。
さらに、未加入者向けの事務組合設立や外国人労働者への普及策も盛り込まれました。
この制度改正の目的は、建設技能者の処遇改善と退職金水準の底上げです。
また、技能レベルに応じて掛金日額を自動設定できるよう、建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携も強化される予定です。
事業者が柔軟に掛金を選べることで、従業員のキャリアや現場の規模に応じた対応が可能となります。
新制度で想定される退職金額の変化
今後の建退共制度改正では、掛金日額の選択肢が増えることで、退職金額にも大きな変化が見込まれます。
従来の320円に加え、600円・700円・800円・1000円といった複数掛金が導入される方向で検討が進んでいます。
退職金イメージ(45年勤務の場合)
- 掛金600円の場合の退職金は888万円
- 掛金700円は1021万円
- 掛金800円は1154万円
- 掛金1000円は1434万円
日額1000円を45年間継続して納付した場合、退職金は最大で約1434万円と達する試算されています。
技能者のキャリアや職種に応じて掛金を柔軟に設定できるようになることで、処遇改善や人材定着にもつながると期待されています。
今後は、事業者がどの掛金を選ぶかによって、従業員の将来設計に与える影響も大きくなるでしょう。
掛金の選択により退職金額が大きく変わるため、制度改正に備えた知識の習得が重要です。
建設キャリアアップシステムとの連携強化
建退共制度の改正にあわせて、建設キャリアアップシステム(CCUS)との連携強化も期待されます。
CCUSは、技能者の就労履歴や資格情報をデジタルで管理する仕組みです。
連携により、掛金納付の記録が正確かつ効率的に管理され、事業者の事務負担も軽減されるでしょう。
さらに、技能レベルに応じて掛金日額を設定するようになれば、処遇の透明性向上にもつながると期待されています。
制度の信頼性を高めるうえでも、CCUSとの連携は欠かせない要素といえるでしょう。
改正に伴う事業者の対応ポイント
建退共制度の改正が行われると、事業者は掛金の選択や運用方法についてこれまで以上に柔軟な判断が求められるようになります。
今後、複数掛金制度が導入されると、従業員の技能レベルや就労年数に応じた掛金設定が可能となります。
その一方で、制度理解が不十分だと、従業員の不信感や退職金額の差につながる可能性もあります。
今後は改正内容を正しく把握し、社内での説明体制を整えることが重要です。
また、電子申請やCCUSとの連携が進む中で、デジタル環境の整備も重要です。
建退共制度の仕組み

制度が改正されることで、事業者や技能者にとってより実情に合った運用が可能になると期待されています。
とはいえ、掛金の金額を選べるようになることで、どの水準を選ぶべきか迷う場面も増えるかもしれません。
選択肢が広がる一方で、それぞれの違いや影響を理解しておくことが、今後の制度活用において重要なポイントとなるでしょう。
この章では、複数掛金制度の基本的な仕組みと、選べる掛金の種類について整理していきます。
掛金の選択肢
これまでの基本額である320円に加え、今後は複数掛金の追加が議論されています。
事業者は、従業員の働き方や技能レベルに応じて、より柔軟に掛金を設定できる可能性があります。
ただし、掛金が高くなるほど事業者の負担も増えるため、現場の規模や経営状況を踏まえた判断が必要でしょう。
選択肢が広がれば、制度の使い方にも工夫が求められるようになってきます。
従業員の将来を支える制度として、掛金の選び方は非常に重要なポイントとなります。
掛金の損金算入と税務上の扱い
建退共制度の掛金は、法人の場合は損金、個人事業主であれば必要経費として計上できます。
福利厚生費として認められるので、税務上も有利といえます。
ただし、証紙を購入しただけでは損金算入できず、共済手帳へ貼付した時点で初めて経費として認められます。
未使用の証紙やポイントは資産として扱われる可能性もあるため、帳簿上の処理には注意が必要です。
税務調査に備え、納付記録や収納書は適切に保管しましょう。
公共工事における加点評価
公共工事の入札に参加する際、建退共制度への加入と履行状況は経営事項審査(経審)で加点評価の対象になります。
制度に加入し、被共済者の就労日数に応じて掛金を納付している事業者が「加入・履行証明書」を経審時に提出することで加点されます。
発注者にとっては、建退共加入の有無が選定の判断材料となることもあります。
なお、証明書の発行には建退共制度の適切な管理が必要であり、未納や記録不備がある場合は証明書が発行されない場合もあるので注意が必要です。
建退共制度の実務ポイント

建設業における退職金制度として広く利用されている建退共制度ですが、実際に加入・運用するとなると、事業者には多くの実務対応が求められます。
制度の仕組みを理解するだけでなく、現場での記録管理や申請手続き、税務処理など、細かなポイントを押さえておくことが重要です。
とくに近年は電子申請方式の普及や制度改正の影響もあり、従来の運用方法から見直しが必要になるケースも増えています。
制度を正しく活用するためには、基本的な流れを整理し、実務上の注意点を把握しておくことが欠かせません。
この章では、建退共制度をスムーズに運用するための実務ポイントを、具体的な場面ごとに解説していきます。
加入手続きの流れ
建退共制度に加入するには、まず建退共本部または各都道府県の支部へ申請を行います。
申請時には「共済契約申込書」「事業所の概要がわかる書類(登記簿謄本や開業届など)」「印鑑証明書」などが必要です。
また、法人・個人事業主ともに、事業内容が建設業であることが確認できる資料の提出が求められます。
申込後、審査を経て「共済契約者証」が交付され正式に制度へ加入となります。
その後は、従業員ごとに「被共済者手帳」を作成し、証紙の貼付または電子申請による掛金納付を開始します。
なお、電子申請を利用する場合は、事前にID取得やシステム登録が必要です。
加入手続きは一度きりですが、運用開始後も記録管理や更新対応が求められます。
一人親方の加入方法
建退共制度は、法人や従業員を雇用する事業者だけでなく、一人親方でも加入できます。
ただし、個人の場合は任意組合を通じて加入するケースもあります。
任意組合とは、同業者が集まって設立する団体で、建退共本部に登録された組合であれば制度の利用が認められます。
加入を希望する一人親方は、所属する任意組合を通じて申請を行い、共済契約者証や被共済者手帳の交付を受けます。
掛金の納付も組合が取りまとめて行うため、個人での事務負担は軽減されます。
民間工事への制度の普及
建退共制度は公共工事での活用が進んでいますが、民間工事への普及は依然として課題が残っています。
とくに、制度の存在自体が十分に認知されていない現場もあり、掛金の見積への反映が後回しになるケースも少なくありません。
そのため、制度を民間工事でも活用するには、見積段階で掛金相当額を明示する必要があります。
たとえば「退職金共済費」として項目を設けることで、認識を共有しやすくなります。
制度未加入によるリスク
建退共制度に未加入のまま事業を継続すると、さまざまなリスクが生じる可能性があります。
他の退職金制度に加入していない場合、労働者が退職金を受け取れない可能性があり、労働条件への不満や離職につながる恐れがあります。
とくに長期雇用を前提とする現場では、制度未加入が人材定着の障害となりかねません。
また、公共工事の入札においては、加入が加点評価の対象となる場合もあります。
制度を理解し、早めに対応することが重要です。
制度改正への対応や複数掛金の選び方に不安がある方は、専門家のサポートを受けるのが安心です。
建設業許可・建退共制度に精通した「おさだ事務所」では、現場実務に即したアドバイスと手続き支援を行っています。
制度の活用を通じて、従業員の定着や経営力の向上を図りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。
【参考サイト】