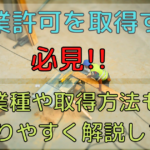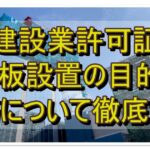令和8・9年度の千葉県入札参加資格申請が、令和7年9月16日からスタートしています。
初めて申請を検討する事業者にとっては、「何から始めればいいの?」「電子申請って難しいのでは?」と不安を感じる場面もあるかもしれません。
そこで今回は、千葉県共同入札制度の仕組みから、ちば電子調達システムの使い方、提出書類のポイントまでをわかりやすく解説します。
千葉県入札参加資格申請とは

入札参加資格申請をすると、入札参加資格者名簿に登載されるようになります。
名簿に載ると、千葉県内の市町村が実施する入札案件に広く参加できるようになります。
まずはこの制度の概要から確認していきましょう。
千葉県共同入札制度の仕組み
千葉県共同入札制度とは、県内の複数自治体が連携して物品購入や業務委託などの契約を行う仕組みです。
個別の市町村がそれぞれ入札を実施するのではなく、千葉県電子自治体共同運営協議会が一括して参加資格審査を行い、共通の名簿に基づいて入札が進められます。
これにより、事業者側は複数の自治体に対して個別申請を繰り返す必要がなく、申請業務の効率化が図れるのが大きなメリットです。
さらに、自治体側にとっても、審査基準の統一や事務負担の軽減につながるため、双方にとって合理的な制度といえるでしょう。
入札参加資格申請の対象業種と事業者
千葉県共同入札制度における参加資格申請の対象となるのは、県内自治体が発注する「物品の購入」「業務委託」「建設工事」などの契約に関わる事業者です。
法人・個人事業主を問わず、該当業種での実績や許認可を有していれば申請可能です。
ただし、契約区分ごとに求められる条件が異なるため、事前確認をしておきましょう。
たとえば、物品契約では製造・販売業者が中心となりますが、委託契約では清掃・警備・システム開発など多岐にわたる業種が対象です。
建設工事に関しては、建設業許可の有無や格付け審査の結果が参加資格に直結します。
千葉県電子自治体共同運営協議会が公開している申請マニュアルには、対象業種一覧や必要書類の詳細が明記されています。
なお、複数業種での申請も可能ですが、申請区分ごとに書類が分かれる点には注意が必要です。
令和8・9年度の申請の流れ
次に令和8・9年度の申請の流れについて説明していきます。
特に申請のスケジュールは、申請準備の起点となりますのでとても重要です。
申請受付期間
令和7年9月16日(火)〜令和7年11月17日(月)17時まで【必着】
この期間内に、電子申請と紙書類の提出を完了する必要があります。
郵送の場合も「必着」が条件で、消印有効ではありません。
申請方法
①「ちば電子調達システム」での電子申請
②申請書類(申請書+添付書類)の郵送または持参
電子申請だけでは完了しません。
紙書類の提出も必須です。
提出先
千葉県電子自治体共同運営協議会 共同受付窓口(千葉県庁南庁舎2階)
持参の場合は受付時間に注意が必要です。
また、郵送の場合は余裕を持って発送しましょう。
有効期間(名簿登載期間)
令和8年4月1日〜令和10年3月31日
この期間中、名簿に登載された事業者は千葉県内の自治体が実施する入札案件に参加できます。
もし当初申請に間に合わなかった場合は、令和8年4月以降に随時申請を行うことで名簿登載が可能です。
ちば電子調達システムの基本
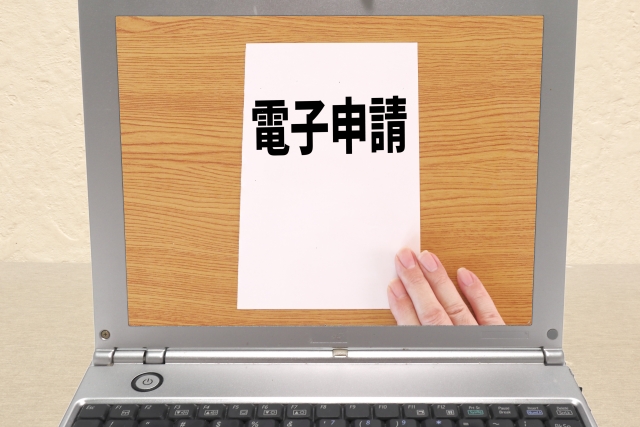
ちば電子調達システムは、千葉県内の自治体が共同で運用する入札・契約関連の電子申請プラットフォームです。
入札参加資格申請をはじめ、契約情報の閲覧や公告の確認など、調達業務に必要な機能が一通り揃っています。
システムの役割と機能
システムを通じて、申請者は利用者番号の取得から申請書類のアップロードまでをオンラインで完結できます。
紙ベースの手続きと比べて、時間や手間が減るのが特徴です。
とはいえ、電子申請だけで完了するわけではなく、紙書類の提出も並行して求められる点には注意が必要でしょう。
加えて、システム上では申請状況の確認や提出済みデータの修正も可能です。
利用者番号の取得とログイン方法
とはいえ、細かな入力ルールやファイル形式の指定など、見落としがちなポイントもあるため、事前にマニュアルを確認しておくと安心です。
ちば電子調達システムを利用して入札参加資格申請を行うには、まず「利用者番号」の取得が必要です。
これは、申請者ごとに割り当てられるIDのようなもので、電子申請の入口となる重要な情報です。
取得手続きは、システム上の「利用者登録」画面から行います。
法人・個人事業主を問わず、必要事項を入力すれば、原則として数日以内に利用者番号が発行されます。
ログインは利用者番号とパスワードを入力することで可能です。
ログイン後は、申請書類の作成や提出状況の確認など、各種機能が利用可能になります。
パスワードは初期設定のままにせず、必ず変更しておきましょう。
なお、利用者番号の取得は早いうちに済ませておくのが理想です。
申請開始直後はアクセスが集中し、思わぬトラブルが起きることもあるため、早めの準備が肝心です。
電子申請の流れと必要な事前準備
利用者番号を取得したら、申請期間内にマイページへアクセスし、申請区分ごとの入力フォームに必要事項を入力していきます。
途中で保存も可能なので、慌てずに進められます。
次に、添付書類をアップロードします。
提出する書類はPDF形式で準備し、ファイル名や容量のルールに従って登録します。
ここで注意したいのは、紙書類の提出も並行して必要になる点です。
電子申請だけでは完了しないため、郵送または持参による提出も忘れずに行いましょう。
事前準備としては、申請マニュアルの熟読が欠かせません。
特に、申請区分ごとの必要書類や提出方法の違いは見落としがちなポイントです。
入札参加資格申請に必要な書類一覧と提出方法

千葉県入札参加資格申請では、すべての申請区分に共通して必要となる書類と団体別に必要な書類があります。
申請の際にはマニュアルをしっかりと確認しましょう。
共通書類(紙・データ)の種類と注意点
書類には「紙で提出するもの」と「電子データとしてアップロードするもの」に分かれており、両方を揃えて初めて申請が完了します。
紙提出の書類には原本が必要なものもあり、提出先に期限までに必着で届くようにしなければなりません。
主な紙書類は、使用印鑑届兼委任状、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、決算書類などです。
一方、電子データとしては、申請書類一式をPDF形式で準備し、ちば電子調達システム上にアップロードします。
ファイル名のルールがあるので事前に確認しておきましょう。
団体個別書類の確認ポイント
千葉県入札参加資格申請では、共通書類に加えて「団体個別書類」の提出が求められます。
これは、申請先となる各自治体や契約区分に応じて異なる内容が指定されており、申請者ごとに必要書類が変わります。
そのため、まずは申請予定の団体と契約区分を明確にしたうえで、該当する提出書類を一覧で確認することが重要です。
団体個別書類は電子申請とは別に紙で提出する必要があります。
また、提出先によっては独自の様式や記載ルールが定められている場合もあります。
マニュアルには団体ごとの提出要領が掲載されているので、見落としを防ぐためにも丁寧に読み込んでおきましょう。
提出方法(郵送・持参)と送付票の扱い
千葉県入札参加資格申請では、電子申請に加えて紙書類の提出が必須となります。
提出方法は「郵送」または「持参」のいずれかを選べますが、いずれの場合も申請期間内に窓口へ“必着”で届くことが条件です。
消印有効ではないため、特に郵送の場合は余裕を持った発送が求められます。
持参する場合は、千葉県庁南庁舎2階の共同受付窓口へ直接提出します。
受付時間は平日の午前9時から午後5時までで、昼休みや閉庁日には対応していないため、訪問前に確認しておくと安心です。
提出時には受付印が押されるため、控えを残しておくと後日の確認にも役立ちます。
また、提出書類には「送付票」の添付が必要です。
これは申請者情報や提出内容を整理するための書類で、マニュアルに定められた様式を使用します。
送付票がないと受付処理が滞ることもあるため、忘れずに同封しましょう。
審査基準と格付けの仕組み

建設工事区分においては「格付け」が重要な要素となります。
申請者の経営状況や施工実績などをもとに、A・B・C・Dの4等級に分類されます。
この格付けは、提出された書類をもとに千葉県電子自治体共同運営協議会が審査を行い、等級ごとの名簿に登載されることで確定します。
審査基準日
申請書類の「審査基準日」はシステム入力を完了した申請日となります。
ただし、客観的事項(経審の点数)の審査基準日は令和8年1月1日です。
この日を起点として、直近の決算内容や実績が評価対象となります。
なお、格付けの結果は後日郵送で通知され、名簿登載の等級が明記されます。
格付けによって参加できる案件の幅が変わるため、申請前に自社の状況を整理しておくことが肝心です。
評価対象となる項目
審査では、事業者の「経営状況」「過去の実績」「保有する許認可」が総合的に評価されます。
まず経営状況については、経審結果をもとに、財務の健全性や資本構成などがチェックされます。
次に、実績の評価では、過去に受注した工事や委託業務の内容・金額・発注者などが審査対象となります。
単に件数が多ければ良いというわけではなく、公共性や継続性、契約履行の確実性なども見られる傾向があります。
さらに、許認可の有無も審査項目のひとつです。
建設業許可や産業廃棄物収集運搬業など、業種に応じた法的資格を保有しているかどうかが確認されます。
格付結果の通知と名簿登載の流れ
審査が完了すると、申請者には「格付結果通知書」が郵送で届きます。
これは、申請内容に基づいて判定された等級(A〜D)や名簿登載の可否が記載された正式な通知文書です。
通知は令和8年3月頃に発送される予定で、名簿登載の有効期間は令和8年4月1日から令和10年3月31日までとなります。
そして格付けされた等級に応じて、千葉県電子自治体共同運営協議会が管理する「入札参加資格者名簿」に事業者情報が登録されます。
この名簿は、県内の各自治体が入札案件の参加者を選定する際の基準として活用されるため、登載されること自体が入札参加の前提条件となります。
申請後の注意点と変更届の提出方法

当初申請が終わったあと、変更事項が生じた場合は「変更申請」が必要です。
また、業種を追加したり団体を追加したい場合は「随時申請」を行います。
ただし、令和8・9年度の名簿については、いずれも令和8年度が開始してからとなります。
スケジュールはマニュアルにて確認をしましょう。
申請後に必要な変更届の種類と提出タイミング
変更申請は、代表者の交代、所在地の移転、営業所の追加・廃止などが該当します。
こうした変更があった際は、変更が確定した日から概ね30日以内を目安に申請が必要です。
とはいえ、契約や入札に影響する内容であれば、できるだけ早めの対応が望ましいでしょう。
また、変更内容によっては、添付書類の提出も必要です。
建設工事については、受付印のある許可変更届の写しが必要になる場合がありますので、早めに変更届を提出しておきましょう。
委任先営業所についても届が必要
千葉県入札参加資格申請では、委任先営業所の登録が可能です。
委任先とは本社以外の営業所に申請・契約業務を委任する場合の拠点を指します。
この営業所が名簿に登載されるには、実態のある事業所であること、かつ継続的な業務運営が確認できることが条件です。
営業所の所在地が確認できる書類や、常駐する職員の配置状況などの審査が行われます。
また、委任先として登録するには「使用印鑑届兼委任状」の提出が必須で、代表者印と委任先責任者の押印が揃っていることが求められます。
さらに、委任先営業所の情報に変更があった場合も、速やかに変更申請をしなければなりません。
提出期限の「必着」ルールとよくあるミス
千葉県入札参加資格申請では、提出書類の締切が「必着」である点に注意が必要です。
つまり、令和7年11月17日(月)17時までに、申請書類が受付窓口へ到着していなければ申請は無効となります。
ここで誤解しがちなのが、「消印有効」と勘違いしてしまうケースです。
実際には、発送日ではなく到着日が基準になるため、郵送の場合は特に余裕を持った手配が求められます。
また、よくあるミスとしては、送付票の未添付や書類の不備が挙げられます。
送付票は受付処理をスムーズにするための重要な書類で、これが抜けていると確認作業に時間がかかり、場合によっては差し戻しの対象になることもあります。
さらに、提出書類の中に署名漏れや押印忘れがあると、審査が進まず再提出を求められることもあるため要注意です。
また、処理の効率化のために、書類はゼムクリップ等でとめないようにしましょう。
首都圏の入札参加資格申請にお困りの場合は、ぜひおさだ事務所にご相談ください。
入札参加資格申請だけでなく、経営事項審査、建設業許可についても対応可能です!
【参考サイト】
令和8・9年度入札参加資格審査申請関係(建設工事等)/千葉県
【こちらもご覧ください】
東京都許可業者必見!首都圏の入札参加資格申請についての徹底ガイド【最新版】 | 建設業専門 おさだ事務所
【建設業】入札参加資格申請とは?名簿に登載される方法、定期・随時の違いを詳しく解説! | 建設業専門 おさだ事務所