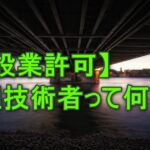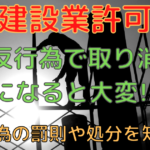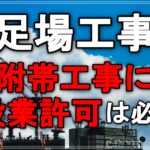事業者にとって、毎年6月にやってくる「労働保険の年度更新」は欠かせない重要な手続きです。
この作業は毎年大変で、その申請方法に悩む方がとても多いです。
しかし「労働保険ってそもそもなに?」「建設業は“二元”といわれるけど、どういうこと?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
今回は建設業における「労働保険」について、6月の年度更新に備えて確認しておきたい基本事項を解説していきます。
建設業における「労働保険」とは?

まずは、「労働保険」とは何でしょうか。
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の2つをあわせた総称です。
労災保険:仕事中や通勤中にケガをしたり病気になったりしたときに補償してくれる保険で休業補償や通院の費用請求などをいう
雇用保険:労働者が失業したときに給付を受けられる保険で、失業保険などをいう
労災保険は、事業主が労働者を1人でも雇った場合、その日から必ず加入しなければならない保険です。
雇用保険は、その労働者が週20時間以上勤務をするなど一定の条件を満たした場合に入らなければならない保険です。
建設業でも同じく、労災保険と雇用保険の両方に加入する必要がありますが、ほかの業種と大きく違う点があります。
それが「二元適用(にげんてきよう)」と呼ばれる制度です。
労働保険の「二元適用」とは

労働保険の「二元適用」という言葉を初めて聞く方も多いかもしれません。
これは建設業に特有の制度で、労災保険と雇用保険の扱い方が別々になるという仕組みです。
建設業の労働保険二元適用制度とは
小売業や製造業などの一般的な業種では、「労災保険」と「雇用保険」を一括して1つの事業所単位で処理します。
これを「一元適用(いちげんてきよう)」といい、一元適用される事業を「一元適用事業」といいます。
一つにまとめて管理するので、労働保険番号は一つだけ振り出されます。
一方で、建設業ではこのようには扱われず、次のようになります。
雇用保険:会社単位で処理
労災保険:現場(工事)ごとに処理。事務方は別に処理
建設業においては労働保険と雇用保険の二つを分けて考えます。
これを「二元適用(にげんてきよう)」と呼びます。
そのため、建設業は「二元適用事業」と呼ばれているのです。
なぜ建設業だけ「二元構造」なのか
建設業の元請けと下請けが同じ現場で仕事をするなど、労働形態はとても特殊です。
それに対応するために、建設業においては特別に労災保険の仕組みを整える必要があるのです。
詳しく見ていきましょう。
例を挙げると、建設業では1つの現場に複数の会社や職人が集まり一定期間だけ一緒に働くという形をとります。
次の工事が始まれば、その構成員は全く別の人たちになります。
そのため、ケガや事故が起きたときに「誰が責任を持つのか」がわかりづらくなってしまいます。
そこで、建設業の労災保険は現場ごとに加入し、保険料も現場ごとに支払うように制度が整えられました。
ただし、事務方においては上記の扱いはされません。
事務の人は営業所に常駐し、現場とは全く違う環境での労働になりますので労災事故の発生率も低くなります。
事務業務の指示は常に自社において行われ、責任の所在も固定しています。
そのため、現場と事務とでは労災保険を別にする必要があるのです。
これが「二元構造」と呼ばれる理由です。
また、元請(もとうけ)と下請(したうけ)の関係が複雑な建設業界では、元請業者が労災保険の加入や保険料納付の責任を持つことが原則とされています。
よって、下請しか行わない事業者は自社に労働者がいて現場の労災保険の加入義務はありません。
また、労災保険は事業主が保険料を支払い、労働基準監督署で加入の手続きを行います。
建設業の雇用保険とは
雇用保険は退職後の失業に関する保険なので、事故の発生度合いは関係ありません。
よって、現場の人も事務の人も同じように一括して雇用保険に加入します。
雇用保険は事業主と労働者自身が折半して支払い、加入する場合の手続きはハローワークで行います。
年度更新に建設業者がやるべき手続きとは

「年度更新」とは、毎年6月に行う労働保険に関する大切な手続きです。
前年度の実績に基づいて保険料を確定させ精算し、次年度の概算保険料を申告・納付する手続きが年度更新です。
3月分の給料が確定したら準備を始めるとよいでしょう。
年度更新の概要と提出時期
年度更新の提出期間は、毎年6月1日から7月10日までです。
この期間内に、基本的に以下の申告・納付を行います。
前年度の確定保険料(実際に労働者に支払った賃金に基づく保険料)
今年度の概算保険料(一年間に支払うであろう見込みの賃金に基づく保険料)
年度更新の提出先は、労働基準監督署(労災保険)もしくはハローワーク(雇用保険)です。
毎年5月になると、労働局より申告書と記載要領の書かれたパンフレットが送られてきます。
前年度の確定保険料は、前年4月1日から3月31日までの一年間の賃金の合計を基に算出します。
今年度の概算保険料はおおよその賃金合計額で出します。
よくわからない場合は前年度と同額で計算するとよいでしょう。
概算で出した賃金合計が実際と違う場合は、次の年度更新時に実際の賃金額にて確定させることで清算できます。
建設業の労災保険のポイント
建設業では、労災保険が工事現場ごとに適用されますので管理が大変です。
建設業における労災保険のポイントを挙げてみましょう。
- 元請として1億8000万円以上の現場を請け負った場合は、その現場の労災保険を新たに加入する必要がある
- 下請が労働者を雇っていても元請が保険加入していなければ、労災保険は支払われなくなるので事故時にトラブルになる
- 下請しか行っていない建設業者は労災保険の加入義務はない
- 労働者を雇っていない役員のみの建設業者、もしくは一人親方の建設業者は労災保険に単独で入れない
1億8000万円以上の元請工事を「単独有期」と呼びます。
単独有期の工事は、その工事ごとに労災保険に加入しなければなりません。
一方、1億8000万円未満の小さな元請工事については、工事ごとに労災保険に加入していたら莫大な手間がかかります。
このような工事は、年度更新の時期に年間の工事を一つにまとめて労災保険に加入する「一括有期」の方法がとられます。
労働保険の保険料の計算方法
基本的に保険料は、賃金額をもとに算出します。
送られてきた年度更新用の申告書にはすでにその業者コードや保険料率が印字されていますので、それに従って申告書を作成します。
年間の確定および概算賃金合計は、自身で計算する必要があります。
労働保険が成立したばかりの業者は、その成立時期によっては年度更新の書類が送られてきません。
成立届を提出した際に申告書が渡されているはずですが、もしわからなければ管轄の監督署やハローワークに確認をするようにしましょう。
建設業の労災保険の計算方法と注意点
建設業の場合、労働者の賃金はその工事現場ごとに計算されるわけではありませんので、保険料の計算はどうすればよいのかと疑問に思われることでしょう。
建設業において労災保険の基となる賃金は、年度更新の際に年間で行った元請工事の合計額を算出し、その金額に決められた労務費率をかけ賃金を算出します。
また、1億8000万円以上の元請工事(単独有期)は個別に取り扱います。
単独有期の場合は、工事が始まってから契約金額を基にして賃金額を算出し「概算申告書」を提出、保険料を支払います。
そして工事が完了したあとに、最終的な請負代金をもとに計算を行い「確定申告書」を提出します。
支払った保険料に不足があれば追加で保険料を納め、多かった場合は還付をうけます。
建設業の雇用保険の計算方法と注意点
雇用保険は会社単位で一括処理され、工事の請負金額ではなく実際に支払われた賃金の合計で保険料を算出します。
賃金台帳や出勤簿、出面表をもとに前年の総賃金額を正確に計算しなければなりません。
賃金には交通費や手当、賞与も含まれます。
建設業の労働保険の具体例とQ&A

建設業の現場では、労働保険に関する誤解やトラブルも多く見られます。
よくある質問をまとめてみました。
現場労働者が事務作業も行う場合はどうすればよい?
建設業においては、労災保険は現場の人が入る現場労災と事務の人が入る事務労災に分かれます。
下請しか工事がない会社であれば現場労働者は労災保険に入れません。
しかし、中には現場の労働者が事務所でも事務仕事を行う人もいます。
このような人に対しては、労働時間のうちどれくらいの割合で事務作業を行うかを考えます。
そしてその割合で事務労働分の賃金を算出し、事務労災に含め計算します。
これらを証明する書類の添付は求められていないので、割合や事務労働に関する金額は自社判断となります。
労働保険料は誰が支払うの?
労災保険は請負工事の金額から算出し会社が保険料を支払いますが、雇用保険は会社だけではなく労働者も保険料を支払わなくてはなりません。
労働者を雇った場合、現場ごとの労働者名簿や出面簿などは必ず整備しましょう。
これらは、保険料計算だけでなく、事故発生時の確認資料としても重要です。
一人親方や外注先は保険に入れる?
原則として、一人親方や外注業者は労災保険の対象外です。
しかし現場に入る人であれば、いつ事故にあうかわかりません。
一人親方は労災保険特別加入制度を活用すれば、労災保険に入れます。
特別加入に入るには、労働保険事務組合に加入し手続きをします。
もしくは、労災保険と同等の保証のある民間の保険に入るのもよいでしょう。
民間の保険であれば誰でも入ることができますので必ず何かの保険には入っておくようにしましょう。
工事現場で労災事故が起きたら?
労災事故が発生した場合、元請が労災保険に加入していないと大変な問題になります。
建設業において、基本的に現場労働者は元請の労災保険を使います。
下請業者が労災事故を起こした場合も、元請の労災保険で費用請求や給付申請を行います。
下請業者はその工事に関しての労災保険に入れません。
元請が労災に入っていなかったりして労災保険請求ができない時は、元請責任が認められれば損害賠償や見舞金などを請求できる可能性があります。
安全管理や保険加入の責任は、基本的に元請が負うと理解しておきましょう。
年度更新に向けて事前準備をしておこう

6月の年度更新前に、以下のポイントをチェックしておくとスムーズに進みます。
- 前年度の賃金総額を集計しておく
- 工事台帳を整理しておく
- 必要書類を準備しておく
- 建設業における労働保険の概要を理解しておく
年度更新の書類は5月末までに郵送で送られてきます。
算出に使用する労務費率や保険料率は年度によって変わることもありますので、事前に確認しておくのもよいでしょう。
また、最近ではe-Gov(イーガブ)を使った電子申請も推奨されています。
書類を郵送・持参しなくてもオンラインで完了できるので、忙しい建設業者にもおすすめです。
まとめ
- 建設業は雇用保険と労災保険をわけて考える二元適用事業
- 一定額以上の工事については現場ごとに労災保険に入る必要がある
- 保険料は元請工事の施工金額に基づいて計算される
- 下請のみの建設業者は労災保険に入れない
- 建設業の労災保険は現場労災と事務労災がある
建設業における労働保険の手続きは、その趣旨と背景を理解すればそれほど難しいものではありません。
特に「労災保険は現場ごと」「雇用保険は会社単位」という二元構造の基本を押さえておけば、保険料の申告・納付でのミスやトラブルを防げます。
年度更新の時期は毎年6月1日~7月10日頃ですが、7月に入ると労働基準監督署やハローワークは大変混雑しますので、早めに準備して提出するようにしましょう。
おさだ事務所では建設業に関する申請や手続きを行っています。
建設業許可や労災保険に関してもご相談を承りますので、ぜひご連絡ください!