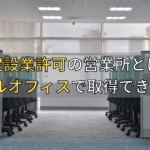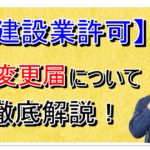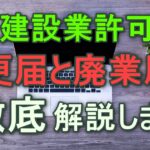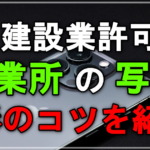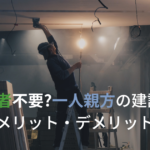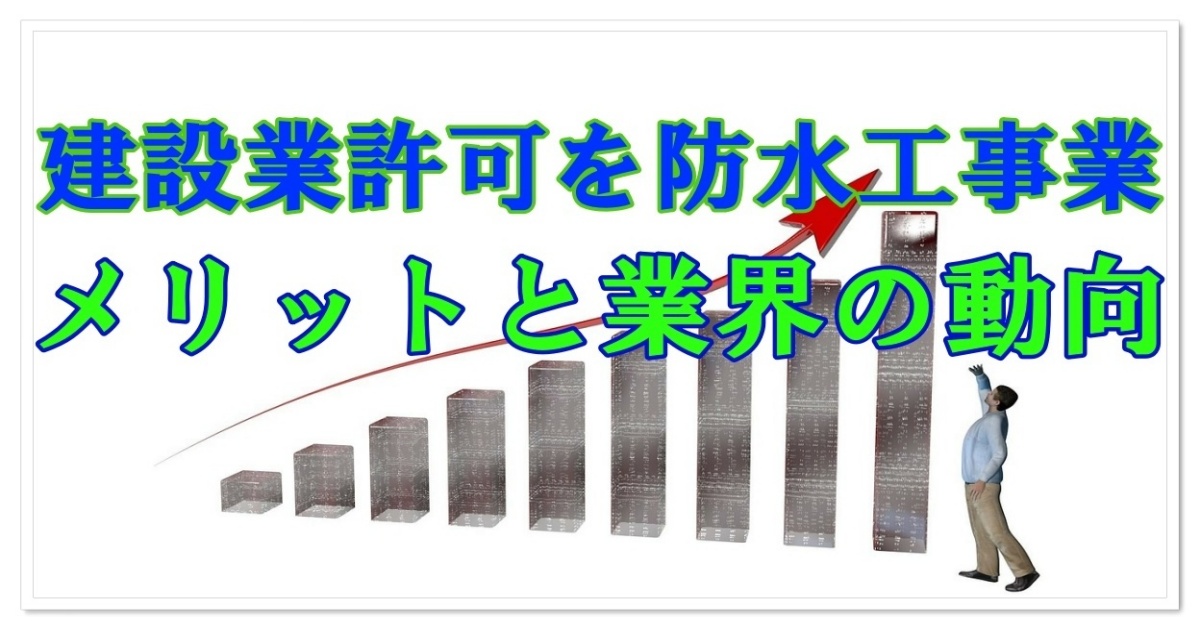近年ますます増加した大雨で、雨漏りや腐食に対する防水工事の需要が高まっています。防水工事業で建設業許可を取得することで、業務の幅が大きく広がるはずです。
とは言え、建設業許可の取得は難しいイメージがありますよね。ご自身の事業所で許可をとることは可能なのか、何が必要になってくるのか、ということは気になるところです。
また、せっかく苦労して防水工事業の建設業許可を取得したのに、あまり活かされなかった…ということになっても悲しいものです。取得時の手間やコストに見合った利益が見込めるかということもしっかり検討しておきたいですよね。
この記事では、防水工事業で建設業許可を取得する条件と、防水工事の内容と注意事項、将来性についても解説していきます。
防水工事業で建設業許可をとる方法

防水工事業で建設業許可を得たい場合、まずはご自身の事業所が次の要件を満たしているか確認してみましょう。
- 経営業務の管理責任者
- 誠実性
- 欠格要件
- 専任技術者
- 財産要件
4以外の要件に関しては一般的な建設業許可の要件と共通です。ただし、1の要件にある「建設業に関する経営者としての経験」が7年に満たない場合は、「許可を受けようとする業種による経験」が5年必要になるので、注意が必要です。この場合、防水工事業に関する経験が5年以上必要になります。
建設業許可を取得するための一般的な条件や、一般建設業と特定建設業の違いについてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてみてください↓
4の専任技術者とは、工事の方法・工事の仕様の検討や決定などをする技術者のことです。その業種の専門家のような役割を担うため、業種ごとに必要な要件が指定されています。

防水工事業で建設業許可をとるには、「防水工事業の専任技術者」が必要ということですね!
それでは、防水工事業の専任技術者には、どのような資格や実務経験が求められるのでしょうか。
防水工事業の専任技術者の要件
防水工事業の専任技術者が必要な場合、要件を満たす人材を新しく雇うか、ご自身や既に雇用している従業員が専任技術者になる必要があります。
専任技術者になるには、次のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 必要な資格を保有している
- 高校や大学の特定の学科を卒業し、一定期間の実務経験がある
- 防水工事業に関する10年以上の実務経験がある
ひとつずつ見ていきましょう。
①必要な資格を保有している
次のいずれかの資格を保有していることが条件です。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
- 技能検定 防水施工技能士(2級の場合は3年以上の実務経験が必要)
- 基幹技能者:登録防水基幹技能者または登録外壁仕上基幹技能者
- 大臣特別認定者(現在は実施なし)
- 指定建設業7業種の特定認定講習の効果評定または考査に合格(現在は実施なし)
以上の資格を保有している場合、高卒以上の学歴や実務経験は基本不問で専任技術者になれます。
②高校や大学の特定の学科を卒業し、一定期間の実務経験がある
高校や大学で土木工学または建築学に関する学科で学び、卒業後に防水工事に関する実務経験を積んだ方があてはまります。必要な実務経験の長さは高卒と大卒で異なります。
- 大卒:防水工事に関する3年以上の実務経験
- 高卒:防水工事に関する5年以上の実務経験
③防水工事業に関する10年以上の実務経験がある
防水工事業に関する10年以上の実務経験がある方は、学歴や資格は不問で専任技術者になれます。
防水工事業にはどんなものがある?

ここまで防水工事業で建設業許可を取る方法、専任技術者の要件を見てきましたが、防水工事業に関する実務経験が必要な場合も多いことがわかりました。それでは、防水工事業とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。
その名の通り、防水工事業とはアスファルトやモルタル、シーリング材などを使用して、建物内部への水の侵入を防ぐ工事の事です。しかし、「とび・土工工事業」や「塗装工事業」と関連性が高く、区別しにくいので注意が必要です。
- とび・土工・コンクリート工事との違い
- トンネル防水工事など、土木関係の防水工事→とび・土工・コンクリート工事
- 建築関係の防水工事→防水工事業
- 左官工事との共通点
- 防水モルタルを用いた防水工事→「左官工事業」「防水工事業」どちらの業種の許可でも施工可能
6種類の防水工事
それでは、防水工事には具体的にどのようなものがあるのでしょうか。防水工事は、使用する材料などによって次の6種類に分類されます。
- アスファルト防水工事
- モルタル防水工事
- シーリング工事
- 塗膜防水工事
- シート防水工事
- 注入防水工事
ひとつずつ見ていきましょう。
①アスファルト防水工事
アスファルトでコーティングした合成繊維不織布のルーフィングシート(屋根用の防水シート)を貼り重ねる工事です。施工不良が起こりにくく、防水工事の中で最も歴史が長いため、信頼性の高い方法です。
実際、他の防水工事と比べて高い防水性能をもち、耐用年数も15~25年程度と長くなっています。ただし工事には大掛かりな設備が必要なため、おもにマンションやビルの屋上に施工されます。
②モルタル防水工事
「モルタル防水」は、おもに「防水モルタル」で仕上げた防水層のことを指します。
モルタル防水だけでは、確実な防水機能は期待できません。そのため、雨漏りが起こっても問題ないような場所への施工に限られ、地下・鉄筋コンクリートの庇(ひさし)などにモルタル防水が使われます。
また、築年数の古い建物では「モルタル防水」で仕上げている部位が多く見られます。メンテナンス時期は10年前後と言われているため、症状に応じて塗装工事(塗り替え)や張り替え工事する必要があります。
③シーリング工事
「建物の外壁ボード間のつなぎ目」や「外壁とサッシの隙間」など、動きの多い目地または隙間などをシーリングで埋める工事です。外壁目地にシーリング工事を施すことで、外壁材の内側に雨水が入りにくくなり、外壁の劣化を防止できます。
高度の防水性・機密性等を確保することを目的として行われます。
④塗膜防水工事
塗料を塗り重ねることで「防水層」を作り、雨水などの水分が下地になっている建材に浸透するのを防ぐ施工のことです。
「ウレタン樹脂」「ポリエステル樹脂」を使用し工事現場で仕上げるため、凹凸の多い形状などにも「塗り」で対応でき、どこでも施工できることがメリットです。施工も簡単で、安価なうえ、条件や施工方法によっては、既存の防水層を撤去する必要もありません。
塗膜防水工法は現在、一般家庭や商業ビルなど幅広い場所で採用されています。
⑤シート防水工事
塩化ビニルやゴム製のシートを接着剤や機械で施工箇所に固定し、水の侵入を防ぐ工事です。
耐用年数(15年程度)と工費とのバランスが良く、コストパフォーマンスが高い工事になることが特徴です。また、厚みが均一なため一度に広範囲でムラなく仕上げられます。
下地の撤去が不要で、調整の必要もほとんどありません。初めて防水工事する場合はもちろんのこと、先に施工した防水工事がシート防水以外の方法だった場合でも、シート防水での施工が可能です。
⑥注入防水工事
壁内部の浮いている隙間に対し、樹脂系の注入剤を圧入して隙間を硬く埋める工事です。
建築物の外壁コンクリートのモルタル仕上げやタイル壁の下地が浮いた状態の場合に行い、軽度なクラック・浮きの漏水問題を解消できます。
こちらは、防水工事の種類・特徴を徹底解説した動画です。宜しければご覧ください。
建設業許可における防水工事業の未来とは


でも、防水工事業の建設業許可ってどれくらいメリットがあるのでしょうか?
現在の防水事業は過去に行われた維持管理がメインになっていますが、建物がある限りメンテナンスには需要があります。また、日本は地震大国で台風も多いため、防災の観点からも防水工事には必要価値があります。
生活の安心安全を守るという観点から、防水工事の需要は今後も増えていくことが予想されます。

今後の防水工事業について見ていきましょう!
防水工事業の需要は増加傾向にある
専門性の高いスキルをもつ防水工事業者は、特に次の2つの分野での需要が見込まれます。
- インフラ維持・整備
- リフォーム・リニューアル事業
ひとつずつ見ていきましょう。
①インフラ維持・整備
インフラは高度経済成長期の1960年代から1970年代に集中的につくられました。この頃に作られたインフラのメンテナンスサイクルが回ってくることで、維持修繕工事比率が増加傾向になっています。
下記の表をご覧ください。

維持修繕工事比率
- 民間部門:1999年の20.5%から2014年の27.5%に増加傾向
- 公共部門:1999年の16.0%から2014年の28.7%に増加傾向
②リフォーム・リニューアル工事
現在は建物をリノベーションして売り出すことも多く、新型コロナウイルス感染症が一気に拡大した2020年度を除き、リフォーム・リニューアル市場は右肩上がりに伸びています。
さらに、かつては増改築がメインだったリフォーム・リニューアル事業ですが、現在は大地震・大型台風の影響から耐震・防水に不安を感じて補強するケースが増えています。

リフォーム・リニューアル工事の分野でも、防水工事業の需要は高まっているんですね!
防水工事業で建設業許可を取得するなら、おさだ事務所へ

おさだ事務所は、取得困難な東京都の建設業許可に特化しています。
ご相談は無料!さらに許可が下りなかった場合、全額返金保証をいたします。



まずはお気軽にお問い合わせください!

まとめ
防水工事は、人々の生活を守るために必要不可欠な工事です。建物やインフラがある限り、その需要はなくなることはありません。防水工事業の建設業許可はこれからも取得する価値があるでしょう。
しかし、忙しい現場仕事の合間をぬって慣れない申請手続きをするのは大変ではないでしょうか。そんな時は、おさだ事務所にぜひお気軽にご相談ください。