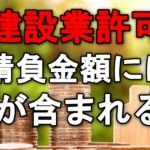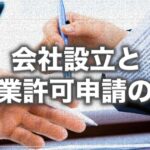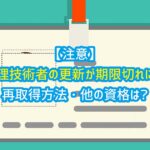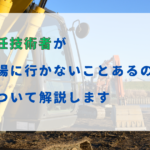東京都で建設業許可を取得している事業者にとって、公共工事への参加は安定した受注につながります。
とはいえ、実際に入札へ参加するには、まず各自治体や省庁が定める名簿に登載される必要があります。
申請方法や時期は自治体ごとに異なり、初めての方には少し複雑に感じられるかもしれません。
今回は東京都をはじめ、23区・神奈川県・千葉県・埼玉県、さらにインターネット一元受付や全省庁統一資格まで、首都圏の主要な申請先の申請の流れや注意点をわかりやすく解説します。
東京都

東京都が発注する契約に参加するには、定められた期間内に入札参加資格申請を行う必要があります。
この申請はすべて「東京都電子調達システム」を通じて行われます。
申請受付期間とスケジュール
建設工事については2年度ごとに行われ、次の定期申請は令和9・10年度分となり、令和8年秋頃に実施される予定です。
令和7・8年度については随時申請にて申請しましょう。
随時申請は申請月によって名簿登載のタイミングが変わるため、工事案件への参加時期を逆算して申請するのが望ましいでしょう。
電子調達システムの登録手順
東京都では紙での申請を原則受け付けていません。
登録手順は以下の通りです。
- 電子証明書の取得
- パソコン環境の確認と設定
- 電子調達システムへの事業者登録
初回の申請時は不備が起こりやすいため、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。
電子証明書の準備
まずは、国や自治体が指定する「認証局」より電子証明書を購入します。
電子証明書とは、インターーネット上で本人確認を行うためのデジタルの身分証です。
電子証明書を購入する際には、名義は法人もしくは個人事業主となります。
また、利用者の氏名は東京都と契約をする権限のある人(代表取締役、支店長などの代理人)となります。
入札においては、電子証明書を格納した「ICカード」が必要です。
ただし、商業登記している法人が取得できる「電子認証登記所の電子証明書」はICカードに格納することができず、入札資格申請には対応していません。
カードリーダーを持っていない場合は、ICカードの申請時に同時に購入もできますので準備をしておきましょう。
書類を揃えて提出をすると、2週間ほどで電子証明が格納されたICカードが届きます。
本人限定受取となりますので、しっかりと受け取れるようにしておきましょう。
他の人が受け取る場合、事前に代理人受取申請が必要な場合もあります。
パソコン環境の整備
電子証明書を準備できたら、次にパソコンの環境を整える必要があります。
まず、電子証明書を使うための専用ソフトをインストールします。
各認証局によりこの方法は異なりますので、調べておきましょう。
次にパソコン環境の設定を行います。
パソコンに詳しくない場合は、公式サイトで詳細を確認をしながらしっかりと設定を進めましょう。
電子調達システムにて申請をする
東京都電子調達システムの「資格審査」画面から入札参加資格申請をします。
申請後、東京都が審査を行い結果は後日通知されます。
承認されると「競争入札参加有資格者名簿」に登録され、入札に参加できるようになります。
審査基準と等級の決まり方
随時申請の場合、毎月20日が締め切りとなります。
20日までに申請完了すると翌月1日から資格が適用されます。
21日から月末までに申請完了した場合は翌々月1日からとなります。
審査は「客観審査」と「主観審査」に分かれており、それぞれ異なる観点から評価されます。
客観審査:財務状況、施工実績、技術者数などの数値的評価
主観審査:過去の契約履行状況、法令遵守、社会的信用などの定性評価
これらの審査結果に基づき、事業者には「等級」が付与されます。
東京都では客観等級と主観等級のいずれか低い等級を格付等級とされます。
東京都内の区市町村

東京都内の区市町村の建設工事に参加するには、各自治体が定める「競争入札参加資格」を取得しなくてはなりません。
申請は「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス」から行い、受付期間は自治体ごとに異なる場合があります。
申請受付期間とスケジュール
基本的には、審査基準日(決算日)より「1年8か月」の有効期間が設定されており、継続申請は毎年必要です。
たとえば、12月決算の事業者は翌年8月が申請期限となり、締切は月末ではなく「20日頃まで」となっています。
「東京都と23区や市町村って同じじゃないの」などと思われがちですが実は申請先も制度も別になります。
混同しないよう注意しましょう。
電子調達サービスの登録手順
申請は「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス」から行います。
紙での申請は認められておりません。
登録の流れは以下の通りです。
- 電子証明書の取得
- パソコン環境の整備
- 電子調達サービスへの事業者登録
- 審査申請フォームの入力
- 必要書類のアップロードと郵送
電子証明書の購入やパソコン環境の設定は、東京都とほぼ同様です。
なお、複数の自治体に同時申請する場合でも手続きは一括で行えます。
審査基準と等級の決まり方
郵送書類が到着してから約1週間で審査は終了します。
毎月、25日までに承認が行われた場合は適用年月日は翌月1日となります。
26日から月末までの場合は、翌々月の1日からとなります。
審査は「客観審査」と「主観審査」の2軸で行われますが、自治体ごとに評価基準が微妙に異なる場合があります。
埼玉県

埼玉県の市町村への入札参加資格申請は「埼玉県電子入札共同システム」を通じて行います。
一部の自治体は参加していませんので、申請先のサイトで事前に確認するようにしましょう。
申請受付期間とスケジュール
埼玉県では、令和9・10年度の建設工事に関する入札参加資格申請の定期受付が、令和8年秋に実施の予定です。
令和7・8年度の申請は、随時申請となります。
随時申請は定期的に行われていますので、名簿登載を希望する際には公式サイトを確認しましょう。
なお、申請はすべて電子申請で行われ、書類の郵送は不要です。
電子システムの登録手順
登録手順は以下の通りです。
- 電子証明書の取得
- パソコン環境の整備
- 事業者申請ポータルへのアクセス
- 申請フォームの入力と書類のアップロード
電子証明書の設定、環境設定は公式サイトにて方法を確認しましょう。
複数自治体の同時申請が可能で、手続きは一括で行えます。
審査基準と等級の決まり方
埼玉県の建設工事の格付は、大きく分けて「客観点」と「県評価点」の2つで成り立っています。
県評価点は、埼玉県独自の基準によって加点される評価項目です。
そのほか、社会貢献や環境への取り組みも格付に反映されます。
SDGsや環境宣言の実施、女性活躍や子育て支援の制度、若手人材の育成やCCUS登録なども加点項目です。
神奈川県

神奈川県と県内29市町村、および広域水道企業団への入札参加資格申請は、一括申請が可能です。
申請受付期間とスケジュール
神奈川県の定期申請は2年に1度実施されます。
令和9・10年度の定期申請は、令和8年秋頃に受付が開始される予定です。
令和7・8年度の申請は随時申請となります。
毎月、月初に申請の締め切りとなり、問題なく受理されると翌月1日から名簿に登載されます。
資格申請システムの登録手順
申請は「かながわ電子入札共同システム」を通じて行います。
登録手順は以下の通りです。
- 電子子証明書の取得
- パソコン環境の整備
- 資格申請システムへのログイン
- 申請データの作成と送信
- 提出書類の郵送
申請は専用システムから行い、申請データの送信後、印刷した提出書類一覧表に基づいて必要書類を各団体へ郵送します。
申請前には必ず「申請の手引き」や「操作マニュアル」を確認し、事前準備を整えておくことが重要です。
審査基準と等級の決まり方
認定通知は郵送されず、システム上で結果はダウンロードします。
神奈川県が共通部分の審査を実施し、その後、市町村等が団体ごとの固有審査を行います。
格付けは「客観点数」と「主観点数」を合算した総合点数で判定されます。
主観点数には、以下のような県独自の評価項目が含まれます。
- 社会的取組:障害者雇用、女性活躍推進、環境配慮など
- 地域貢献度:県内に本店・支店があるか、地域への密着度など
- 過去の施工実績:県発注工事の履行状況や表彰歴など
単なる財務体質や技術力だけでなく、神奈川県の行政方針に沿った企業姿勢が評価されます。
千葉県

千葉県発注の建設工事や関連業務に入札参加するには、県の資格者名簿に登載される必要があります。
共同システムにより、千葉県および54の市町村、北千葉広域水道企業団とかずさ水道広域連合企業団への参加資格申請を行えます。
申請受付期間とスケジュール(定期申請)
千葉県では、定期申請は2年ごとに実施されています。
令和8・9年度の当初申請は、令和7年9月16日から始まります。
最新のマニュアルを参考にして、期間内に申請が完了するようにしましょう。
電子システムの登録手順
申請は「ちば電子調達システム」を通じて行います。
登録手順は以下の流れで進みます。
- 電子証明書の取得
- パソコン環境の整備
- 入札参加資格申請システムへのログイン
- 申請データの作成と送信
- 申請書類の印刷・郵送
千葉電子調達システムを初めて利用する事業者は、システム利用申請が必要です。
申請は専用画面から行い、申請者情報を登録します。
すでに利用者番号を持っている場合はこの申請は不要ですが、番号が不明な場合は再交付申請が必要です。
審査基準と等級の決まり方
当初申請をした事業者には、申請翌年の3月1日付けで「資格者名簿登載通知書」がはがきで送付されます。
千葉県が共通部分の審査を実施し、その後、参加団体ごとの個別審査が行われます。
等級は、申請者の施工能力を「客観点数」と「主観点数」により評価し、その合計点で格付けを行います。
主な加点項目は下記のとおりです。
- 環境配慮:ISO14001やエコアクション21の取得など
- 社会的取組:障害者雇用や女性活躍推進など
- 優良工事表彰の実績
- 企業との連携や合併履歴
- 担い手確保:若年者雇用など
これらの点数を合算し、基準によりA〜D等級などに格付けされます。
インターネット一元受付

測量・建設コンサルタント業務、建設工事を対象に、複数の省庁・機関に対して入札参加資格の一括申請が可能です。
これは「定期競争参加資格審査インターネット一元受付」と呼ばれています。
国土交通省をはじめとした各省庁、及び下記の独立行政法人等が対象です。
東日本高速道路(株)
中日本高速道路(株)
西日本高速道路(株)
首都高速道路(株)
阪神高速道路(株)
本州四国連絡高速道路(株)
独立行政法人水資源機構
独立行政法人都市再生機構
日本下水道事業団
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
申請受付期間とスケジュール
令和9・10年度の定期申請は、令和8年12月から令和9年1月中旬ころまでの期間で実施される見込みです。
申請には事前の「パスワード発行申請」が必須で、これを済ませていないと定期申請そのものができません。
なお、随時申請についてはインターネット方式は利用できません。
電子システムの登録手順
申請は「国交省インターネット受付専用サイト」から行います。
登録手順は以下の通りです。
- パスワード発行申請
- 申請書データの作成
- 添付書類の送信
- 申請データの送信と確定処理
- 郵送書類の提出
なお、共同企業体(経常JV)など一部の申請はインターネット方式では対応しておらず、文書郵送方式が必要です。
審査基準と等級の決まり方
審査は、提出された申請書類と経営事項審査結果をもとに行われます。
評価項目および審査基準は各省庁等により異なります。
インターネット一元受付は申請が難しいので、行政書士などの専門家に依頼するのもよいでしょう。
全省庁統一資格

全省庁統一資格制度とは、国の各省庁が発注する物品の製造・販売、役務の提供等の業務に関して参加するための資格審査です。
建設工事については全省庁統一資格に対応していませんので注意が必要です。
申請受付期間とスケジュール
全省庁統一資格の申請は、3年に一度の定期申請が基本となります。
次回の申請対象期間は令和10年度から令和12年度までの3年間で、申請受付は令和9年秋頃から開始される予定です。
また定期申請とは別に、年度途中で新たに事業を開始した企業や資格の有効期限が切れた場合などには「随時申請」も可能です。
随時申請は通年で受け付けられており、審査後に資格が付与されると入札参加が可能になります。
電子システムの登録手順
全省庁統一資格の申請は、「調達ポータル」上での電子申請となります。
紙での提出は原則不要で、すべての手続きがオンラインで完結します。
まずは調達ポータルに事業者情報を登録し、ログイン後に申請画面へ進みます。
申請完了後は、審査機関による内容確認が行われ、問題がなければ資格が付与されます。
審査結果はポータル上で通知され、資格証明書も電子データで発行されます。
審査基準と等級の決まり方
全省庁統一資格では、、申請者の経営状況や業務履行能力を数値化し、A〜Dの等級に格付けします。
審査は年間平均売上高、流動比率などから点数が算出されます。
単に売上高だけで決まるものではなく、複数の評価項目を点数化した総合評価によって決定されます。
入札参加資格申請は申請先によって時期や方法が異なります。
初期設定や電子証明書の導入など、特に初めての方にはつまずきがちなポイントが多くなります。
おさだ事務所では、各自治体への入札参加資格申請を代行で行っていますのでぜひご相談ください!
【参考サイト】
埼玉県電子入札総合案内トップページ(システム入口) - 埼玉県
令和7・8年度定期競争参加資格審査インターネット一元受付(測量・建設コンサルタント等業務)
【こちらもご覧ください】
【建設業】入札参加資格申請とは?名簿に登載される方法、定期・随時の違いを詳しく解説! | 建設業専門 おさだ事務所