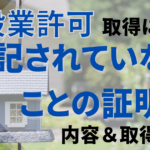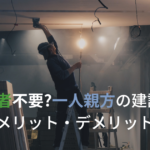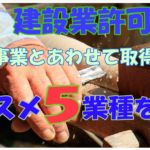東京都で産業廃棄物収集運搬業を始めるには、まず「許可申請」をする必要があります。
廃棄物の適正な処理は環境保全や地域の安全に直結するため、この許可申請には厳格な審査基準が設けられています。
とはいえ、制度の仕組みを理解し必要な準備を整えれば、初めての方でも着実に許可取得を目指すことができます。
今回は、申請の流れや注意点をわかりやすく整理しながら、許可取得の「成功の秘訣」を解説していきます。
産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬業とは、工場や建設現場などの事業活動によって出る廃棄物を、決められた処分場まで安全に運ぶ事業のことです。
たとえば、建物の解体で出るコンクリートがらや、工場から出る汚泥などが対象になります。
これらの廃棄物は、家庭ゴミとは違い、法律に従ってきちんと管理・運搬しなければなりません。
対象となる産業廃棄物
産業廃棄物収集運搬業で取り扱う廃棄物は、事業活動に伴って発生するものに限られます。
代表的な種類としては、廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、木くず、汚泥、燃え殻などが挙げられます。
これらは、製造業や建設業、医療機関など、業種ごとに排出される廃棄物の性質が異なるため、分類と取り扱いには注意が必要です。
たとえば、建設現場から出るコンクリート破片や木材の切れ端は、見た目は一般廃棄物に似ていても、法的には産業廃棄物として扱われます。
また、廃油や廃酸などの液状物は、漏洩リスクがあるため、運搬容器や積載方法にも厳格な基準が設けられています。
そのため、収集運搬業者は、廃棄物の種類ごとに適切な処理ルートを確保し、安全かつ確実に運搬する体制を整えることが求められます。
許可が必要な理由と法的根拠
産業廃棄物収集運搬業を営むには、法律に基づいた「許可」が必須です。
これは、廃棄物の不適切な処理による環境汚染や健康被害を防ぐため国が定めた制度です。
根拠となるのは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」であり、第14条において、都道府県知事の許可を受ける義務が明記されています。
そのため、収集・運搬を行う事業者には、法令遵守と安全管理が強く求められます。
無許可で業務を行った場合、罰則の対象となるだけでなく、社会的信用を大きく損なう可能性もあります。
東京都における業界の特徴と動向
東京都の産業廃棄物収集運搬業は、都市型産業の集積という特性から、他地域と比べて多様な廃棄物が発生する点が特徴です。
特に建設業や製造業、医療・研究機関などが密集しているため、廃棄物の種類も複雑化しており、事業者には高度な対応力が求められます。
また、都内では法令遵守や環境配慮への意識が高く、優良業者認定制度の活用や電子申請の導入など、制度面でも先進的な取り組みが進んでいます。
さらに、近年では脱炭素や資源循環の観点から収集運搬業者にも環境負荷の低減が求められるようになっています。
業界全体としては、単なる運搬業務にとどまらず、持続可能な社会づくりに貢献する役割が強まっていると言えるでしょう。
東京都で許可申請を行うための流れ

産業廃棄物収集運搬業を始めるには、都道府県知事から「許可」をもらう必要があります。
東京都で申請する場合は、講習の受講や書類の提出など、いくつかの条件をクリアしなければなりません。
東京都で許可を取るための方法や申請の注意点などを解説していきましょう。
申請の種類
東京都で産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う際には、「新規」「更新」「変更」の3つの申請区分を正しく理解しておくことが大切です。
まず新規申請は、これまで許可を取得していない事業者が初めて業務を開始する際に必要となります。
申請には、講習修了証や車両情報、財務書類など、一定の要件を満たす資料の提出が求められます。
一方、更新申請は、既に許可を取得している事業者が有効期限を迎える前に行う手続きです。
東京都では、許可の有効期間は通常5年間とされており、期限の4か月前から申請が可能です。
更新を怠ると許可が失効する可能性があるため、早めに準備を進めましょう。
変更申請は、許可内容に変更が生じた場合に必要です。
例えば、収集運搬する廃棄物の種類を追加する場合や、使用する車両を入れ替える場合などが該当します。
いずれの申請も、内容に応じた書類と手続きが異なるため、事前に確認しておくと安心です。
申請方法と提出先
申請の受付・審査を担当するのは、東京都環境局の「資源循環推進部 産業廃棄物対策課」です。
東京都内で産業廃棄物を運搬する際には、東京都の許可が必要です。
他の都道府県で運搬する場合は、その都道府県の担当部署が窓口になります。
申請方法は、窓口持参または郵送のいずれかを選択できますが、来庁時の混雑緩和を目的に「申請予約制度」も導入されています。
なお、申請内容によっては、事前相談が推奨されるケースもあります。
特に初めて申請する場合や、変更点が複雑な場合には、担当部署に確認を取ることで手戻りを防げます。
申請に必要な書類一覧
東京都で許可申請を行う際には主に以下の書類が必要です。
- 講習会修了証の写し
- 申請書(様式第1号)および添付書類一覧表
- 登記事項証明書(法人の場合は履歴事項全部証明書)
- 定款の写し(法人のみ)
- 住民票抄本(申請者・役員・5%以上の株主等)
- 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
- 誓約書(講習修了証未提出時は受講票の写しも添付)
- 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表(直近3年分)
- 法人税納税証明書「その1 納税額等証明用」(直近3年分)
- 車両の車検証記録事項の写し(IC車検証対応)
- 車両写真(許可番号表示・ナンバープレートが確認できるもの)
- 運搬容器の写真(必要に応じて)
- 使用権原を証明する書類(リース契約書など)
- 事業計画の概要書経理的基礎を有することの説明書(必要に応じて)
- 許可証返送用のレターパックプラス
新規申請の場合、まず重要な書類が「講習会修了証」です。
これは、申請者が法令や業務内容を正しく理解していることを証明するものです。
次に、事業の実態を示す「登記事項証明書」や「定款」、そして財務状況を確認するための「決算書類」も必要となります。
加えて、運搬に使用する車両の情報を記載した「車検証の写し」や、車両に許可番号を表示していることを示す「車両写真」も提出対象です。
更新申請では、基本的に新規申請と同様の書類が求められます。
変更申請の場合は、変更内容に応じた書類のみを提出すればよく、必要書類はケースごとに異なります。
事前に東京都の申請要領を確認しておくと安心です。
申請時に注意すべきポイント
まず注意したいのは、申請書類の不備です。
記載漏れや添付忘れがあると、受付が保留されたり、再提出を求められることがあります。
そのため、提出前には必ずチェックリストを活用し、書類一式を丁寧に確認しましょう。
次に、申請のタイミングにも気を配る必要があります。
更新申請の場合、有効期限の6か月前から受付が可能ですが、期限を過ぎると無許可状態となるため、余裕を持ったスケジュールで動くことが望まれます。
講習会の受講
産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「収集・運搬課程」の講習修了証が必要です。
初心者がまず注意すべきなのは、講習の申し込み方法と日程の確保です。
講習は定員制で、開催地や時期によってはすぐに満席になるため、早めの予約が欠かせません。
申し込みはJWセンターの公式サイトから行います。
講習は「収集・運搬課程」と「処分課程」に分かれており、収集運搬業の許可申請には前者を受講します。
受講後、修了証が発行されるまでに時間がかかるため、申請スケジュールに余裕を持たせることが大切です。
車両・容器の写真
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、車両写真と容器の写真の提出が求められます。
撮影時に注意すべきなのは、「構図」と「確認すべき項目」です。
車両写真では、ナンバープレートと許可番号の表示がはっきりと写っていることが必須です。
許可番号は車両の左右両側に表示し、文字の大きさや色も基準に沿っている必要があります。
撮影時は、車両全体が見える角度から撮ることが望ましく、背景が暗すぎたり、反射で文字が読めない場合は再提出になることもあります。
一方、容器の写真では、廃棄物の漏洩や飛散を防ぐ構造が確認できるよう、フタの有無や材質が分かるように撮影します。
また、写真はカラーで印刷し、鮮明さを保つことが重要です。
スマートフォンでの撮影も可能ですが、画質や明るさに注意しましょう。
許可取得に必要な要件と審査基準

産業廃棄物収集運搬業を始めるには、都道府県から「許可」を受ける必要があります。
そのためには、いくつかの条件を満たしていることが求められます。
さらに申請者がきちんと法律を守り、安定して事業を行えるかどうかを書類や計画書をもとに審査されます。
人的要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、申請者が一定の人的要件を満たしていることが前提となります。
まず必要なのが、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「収集・運搬課程」の講習会を受講し、修了証を取得することです。
さらに「誓約書」の提出も必要です。
これは、申請者が法令上の欠格事由に該当しないことを誓う書類で、成年被後見人や破産者でないことなどが確認されます。
人的要件は、事業者としての信頼性を示す基本的な条件です。
財務要件
さらに事業者が一定の財務的な安定性を有していることが求められます。
特に重要なのが「自己資本の保有」と「納税実績の証明」です。
自己資本とは、事業を継続するための基盤となる資金であり、債務超過に陥っていないことが審査のポイントとなります。
申請時には、直近3期分の貸借対照表や損益計算書などを提出し、経営状況を客観的に示す必要があります。
これにより、事業の継続性や収集運搬業務を安定して遂行できるかどうかが判断されます。
また、納税証明書の提出も必須です。
法人税の納付状況を証明する「納税証明書(その1)」を3期分提出することで、法令遵守の姿勢を示すことができます。
これらの財務要件は、単なる形式ではなく、事業者としての信頼性を裏付ける重要な要素です。
初めて申請する場合は、税理士など専門家の確認を受けると安心です。
車両要件
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、使用する車両に関する要件も審査対象となります。
まず、車両は申請者が「所有」しているか、または「リース契約」により使用権限を有していることが必要です。
リースの場合は、契約書の写しなどで使用権原を証明する必要があります。
次に重要なのが「表示義務」です。
許可を取得した後は、車両の左右両側に許可番号をみやすく表示する必要があります。
表示は見やすい位置に、定められたサイズと色で行うことが求められます。
表示が不十分な場合、行政指導や業務停止の対象となることもあるため注意が必要です。
事業計画書の作成と審査の視点
事業計画書は、申請者が業務を適正かつ継続的に遂行できるかを判断するための重要な資料です。
まず、収集運搬の対象となる廃棄物の種類や数量、運搬ルート、処分先との契約状況などを具体的に記載する必要があります。
また、業務に使用する車両や人員体制、安全管理の方法なども明記します。
審査では、計画の内容が現実的かつ継続性のあるものか、地域の環境保全に配慮されているかが重視されます。
不安な場合は行政書士など専門家の助言を受けながら、丁寧に作成するようにしましょう。
東京都での許可申請における最新ルール

産業廃棄物収集運搬業の許可申請をめぐる制度は、時代の変化や行政の運用見直しにより少しずつ更新されています。
東京都でも、申請者の利便性や審査の効率化を目的とした新しいルールが導入されており、従来の手続きとは異なる点が増えています。
次に最新の運用方針や申請時の注意点について整理していきます。
電子車検証への対応と提出方法の変更
令和5年6月より、東京都では自動車検査証の電子化に伴い、産業廃棄物収集運搬業の許可申請時に提出する車検証関連書類の取り扱いが変更されました。
従来は「電子車検証の写し」と「自動車検査証記録事項の写し」の両方が必要でしたが、現在は「記録事項の写し」のみで提出が可能となっています。
これにより、書類準備の負担が軽減され、申請手続きの効率化が図られています。
また、提出方法についても見直しが進んでおり、窓口提出に加えて郵送申請が可能です。
ただし、東京都環境局の公式サイトから申請予約を行ったうえで、チェックリストを添付して送付する必要があります。
予約なしの郵送は受付されない場合があるため、注意が必要です。
優良産廃処理業者認定制度の概要
東京都の優良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物の適正処理や資源化、環境負荷の低減に積極的に取り組む事業者を評価・認定する制度です。
申請は任意で、都知事の許可を受け、都内で1年以上の実績がある業者が対象となります。
認定は第三者評価機関である公益財団法人東京都環境公社が実施し、「遵法性」「安定性」「先進的な取組」の3つの観点から審査されます。
認定区分は「産廃エキスパート(第一種)」と「産廃プロフェッショナル(第二種)」の2種類があり、それぞれ評価基準の達成度に応じて認定されます。
認定を受けることで、排出事業者からの信頼性向上や、許可更新時の添付書類の一部省略などのメリットがあります。
申請予約制度の導入
東京都では、産業廃棄物収集運搬業の許可申請において「申請予約制度」が導入されています。
対象となるのは、新規・更新・変更の各許可申請で、積替え保管やPCB、優良申請を除く一般的な申請がオンライン予約の対象です。
予約は東京都環境局の公式サイトから行い、希望日時を選択して申請枠を確保します。
窓口提出の場合は予約が必須で、予約なしでは受付されないことがあるため注意が必要です。
郵送申請を希望する場合も、事前に予約を行い、チェックリストを添付して送付する必要があります。
おさだ事務所では建設業許可のほか、産業廃棄物収集運搬業に関する申請もお手伝いしております。
ぜひご相談ください。
【参考サイト】
産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出等|産業廃棄物処理業者の方|東京都環境局
講習会・研修会を申込む | 講習会・研修会 | 日本産業廃棄物処理振興センター