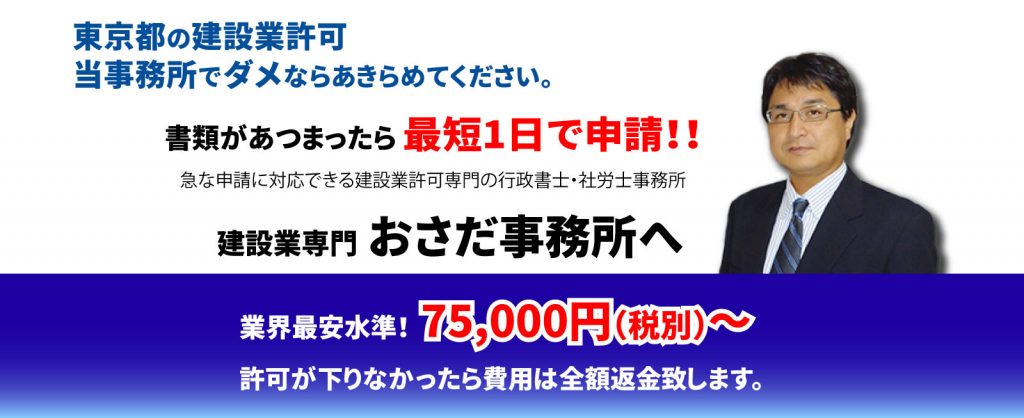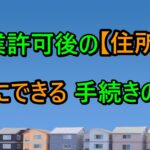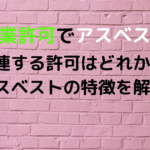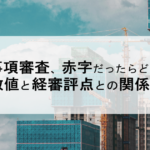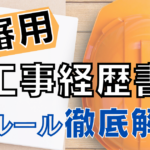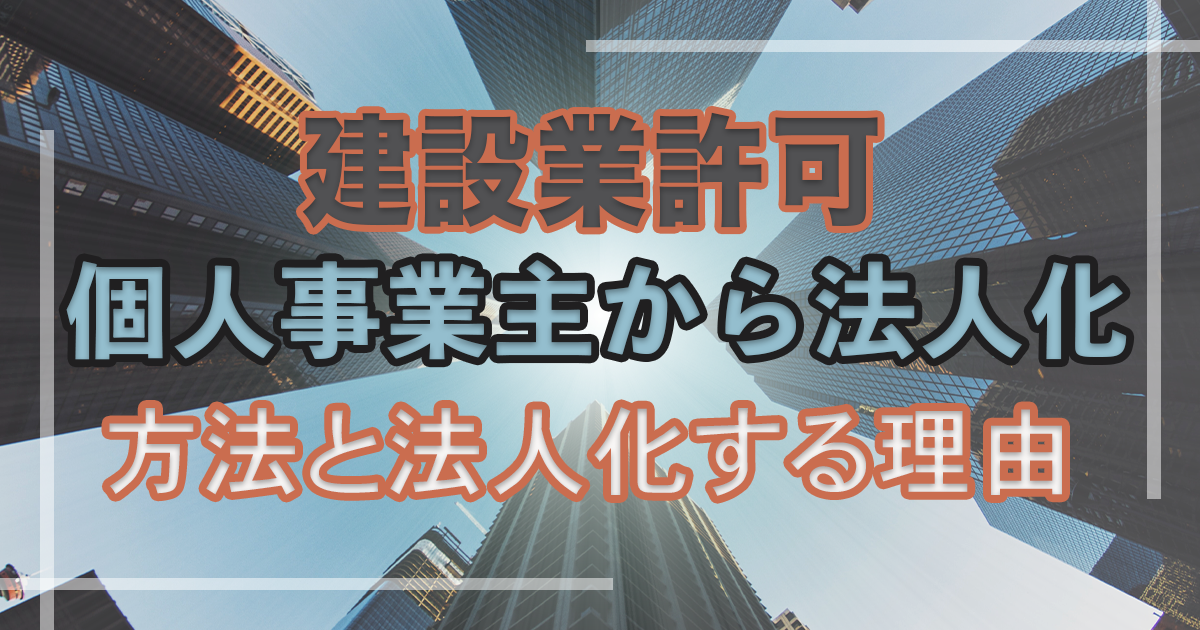「建設会社に勤めているが、いつかは独立して自分の会社を立ち上げたいと思っている」
「建設業許可の取得も含めて考えた時、個人事業主から法人化するにはどういった方法があるか知りたい」
このように考えられている方の為に、今回は『建設業許可の取得を考慮した、個人事業主から法人化する方法』について解説していきます。
許可の取得を含めて考えた場合、個人事業主から法人化する方法にはいくつかのパターンがあります。
また、なぜ個人事業主ではなく法人化するのかーーその理由についてもまとめました。
この記事を読み終える頃には、個人事業主から法人化する方法を理解し、「法人化」という目標に向かうきっかけを掴む事が出来るでしょう。
建設業許可の取得を考慮した個人事業主から法人化する方法とは

はじめに、「個人事業主から法人化する方法にはいくつかのパターンがあります」とお伝えしましたが、その方法は3パターンあります。
- パターン1:無許可の個人事業主から法人化して許可を取得する
- パターン2:個人事業主から許可取得、法人化で許可を取得し直す
- パターン3:個人事業主から許可取得、法人化で許可を引き継ぐ
3つ目は2020年の建設業法改正で、個人事業主から取得した許可の引き継ぎが可能になった事により誕生したパターンです。
法改正前は、個人で取得した許可は法人へ引き継ぐ事は出来ませんでした。
その為、せっかく個人で許可を取得しても、法人化するタイミングで取得し直す必要が生じるなら『法人化して許可を取得した方が良い』と考える方も少なくありませんでした。

許可の取得にかかる労力や時間を考えると、法人化で許可の取り直しはやるせないですよね。
許可が引き継げるようになって本当に良かったです。
許可を引き継げるようになったとはいえ、どの方法で法人化するのかは状況によりますよ。


更なる事業発展の為により良い選択をしたいものですね。
次に、それぞれのパターンについて解説していきます。
パターン1:無許可の個人事業主から法人化して許可を取得する

個人事業主の間は無許可の建設業者として営業し、法人化してから許可を取得する方法です。
建設業許可の取得には、6つの要件「①経営業務の管理責任者等を設置する事」「②専任技術者を設置する事」「③誠実である事」「④財産的基礎等を有する事」「⑤欠格要件に当てはまらない事」「⑥適正な社会保険へ加入する事」全てを満たす必要があります。
「①経営業務の管理責任者等を設置する事」では、『一定の経営経験があるか』を問われます。

6つの要件の中で最もハードルが高いと言っても過言ではありません。
この一定の経営経験に該当するケースを以下にまとめました。
| 項 | 概要 | 備考 |
| 1 | 常勤で建設業の役員経験が5年以上ある | |
| 2 | 常勤で建設業の役員に次ぐポジションの業務経験(執行役員など)が5年以上ある | |
| 3 | 常勤で建設業の役員に次ぐポジション(建築部長など)におり、経営者を補佐した経験が6年以上ある | |
| 4 | 常勤で建設業の役員経験が2年以上あり、その年数と合わせて役員もしくは役員に次ぐポジションの業務経験(財務管理or労務管理or業務管理経験に限る)が5年以上ある+役員を補佐する者を置く | 役員の補佐は「財務管理」or「労務管理」or「業務管理」を5年以上経験している者 |
| 5 | 常勤で建設業の役員経験が2年以上あり、加えて他業種での役員経験が3年ある+役員を補佐する者を置く | 役員の補佐は「財務管理」or「労務管理」or「業務管理」を5年以上経験している者 |
建設会社に勤めていた経験があったとしても、上記の条件をクリア出来る人物は限られています。ただし、個人事業主としての経営経験も一定の経営経験として認められます。
つまり、上記の条件に全く該当しないのであれば、建設業を営む個人事業主として経営経験を5年間積まなければならないという事です。
しばらくは無許可で建設業を営むことになりますが、許可取得に向けての準備を念頭において経営者としての経験値を上げていくのが良いでしょう。もちろん他の要件を満たす準備も必要です。
なお、無許可で建設業を営むとなると、税込500万円以下(建築一式工事の場合は1,500万円未満)の軽微な建設工事の範囲内で受注しないといけません。
この金額を超えた工事を請け負ってしまうと建設業法違反となり、『3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第47条)』という罰則が科されます。罰金刑に処されると許可取得の要件にある“欠格要件”に該当しますので、そこから5年間は許可を取得する事が出来なくなります。
建設業法を守って営業を行わなければならない点は、無許可業者も同じ事なのです。
パターン2:個人事業主から許可取得、法人化で許可を取得し直す

個人事業主の間に許可を取得して許可業者として営業し、法人化でもう一度許可を取得し直す方法です。
法人化する場合、法改正前は個人事業主で取得した建設業許可は法人の方で引き続き使用することは出来ませんでした。その為、建設業許可の廃業届を提出した後、法人として改めて許可を取得する必要がありました。
建設業許可の廃業届を提出すると、行政庁は許可の満了日(許可は5年間有効)を待つ事なく許可の取り消しを行います。なお、この場合の“許可の取り消し”とは、違法行為を行なって許可を取り消されるのとはまた異なるものです。
個人事業主から法人へ許可を引き継げるようになった今は、この方法を好んで選択する人はいないように思います。
しかし、個人事業主から法人へ許可を引き継ぐ為の手続きは、ボリューム的には新規で取得する時とさほど変わらないのにも関わらず、時間は新規で取得するよりも掛かります。
許可の取得を急いでおり、必要書類が揃っていて、要件も全て満たしているのであれば、やむを得ずパターン2の方法を選ぶ事もあるでしょう。
また、経営事項審査(以下、経審)の実績を法人へ引き継ぐには、個人事業主の許可を廃業する必要があります。
個人事業主時代に経審を受けており、これから法人化するとなれば、経審の実績もそのまま法人へ引き継ぎたいと考えるはずです。ところが、パターン3の方法で許可を引き継ぐと、経審の営業年数がゼロになってしまいます。

経審は営業年数が長いほど加点される仕組み。営業年数が長いという事は、それだけ続けてきた歴史の重みがあります。その歴史がゼロになってしまうとあっては、パターン2の方法を迷わず選択する業者もいるでしょう。
パターン3:個人事業主から許可取得、法人化で許可を引き継ぐ

個人事業主で許可を取得し、法人化でそのまま許可を引き継いで使用する方法です。
引き継ぐには行政庁へ事前相談を行い、認可申請をします。認可申請の前に事前相談は必須です。

いきなり認可申請をしても受け付けてもらえませんので注意しましょう。
認可申請にはお金はかからないので、新規で許可を取得するよりも金銭面でお得に感じます。
しかし、前述した通り、手続きのボリュームは新規で許可取得する時とあまり変わらず、且つ時間はかかります。
また、個人事業主本人が「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」を兼ねている場合、事業を譲渡する日までは個人事業で常勤勤務し、譲渡日からは新設した法人の方で常勤勤務するというように社会保険の移行手続きを行わなければなりません。
この社会保険の手続きが上手く出来ていないと、許可要件である「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」が不在という事になり、許可の取り消し処分を受ける羽目になります。代表者が取り消し処分を受けますと、欠格要件に該当しますので、5年間は許可の取得が出来ません。
個人事業主から法人化する理由とは

独立を考えられる場合、まず個人事業主から始められる方は多くいらっしゃいます。もちろん法人化せず、ずっと個人事業主のまま事業を継続していく事は可能です。
しかし、新規で法人を設立する事業者は増加傾向にあります。なぜ、最終的には法人として経営する道を選ぶのでしょうか。
ここでは、法人化する理由について迫っていきます。
節税出来るから
個人事業主が納める所得税は所得額によって高くなっていきます。売り上げが1000万円を超えると、消費税の納税義務が生じ、翌々年から納税しなければいけません。
ですので、納税する直前のタイミングで法人化すれば、納税せずに済むのです。更に、新規の法人は2年間消費税の納税が免除されます。タイミング良く法人化する事で、実に4年間は消費税の納税が免除となります。
この4年間が過ぎ、納税義務が生じたとしても、法人の持つメリットを発揮し、節税に取り組む事は可能です。
その節税方法については、各々会社によって違いがありますので、詳しくは税理士に相談する必要があります。
銀行から融資を受けやすくなるから
事業を継続・拡大していく為に、どうしても避けて通れないのが『資金調達』です。
その資金を調達してくる先といえば、真っ先に銀行を多くの人が思い浮かべるのではないでしょうか。
公的金融機関であれば、個人事業主に対しても融資をしてくれます。しかし、基本的に銀行からの融資は法人でなければ望めません。
融資を申し込んだところで、保証人や担保等が必要になり、結果なかなか融資を受けるに至らない事もあります。ですので、個人事業主が事業を拡大する為に銀行から多額の融資を受けるというのは困難なのです。
それに比べ、法人は融資が受けやすいのは勿論の事、誰か保証人を立てなければならないという負担もありません。
優れた人材を集める事が出来るから
法人企業の方が個人事業主に比べ、圧倒的に優れた人材を集めやすいと言えます。
それに対し、個人事業主では、求人を出しても求める人材を雇うのは難しいでしょう。そう言うのも、雇われた先が個人事業主だとどうしても「給料は決められた日に支払われるのか」や「社会保険は完備されているのか」といった不安感がつきまとうからです。
それが法人企業であれば、上記のような問題はまずクリアできます。
多くの会社と取引が出来るから
事業を行なっていくにあたり法人には、民法や商法以外に会社法や役員の責任等、細かい規定があります。
ですが、個人事業主は会社ほど細かい規定は必要ありません。建設業許可の取得においても、個人事業主は会社ほど提出しなければならない書類はないので、その分負担は軽いのです。
しかし、法人には様々な規定があるからこそ、それらの規定が働いて社会的信用を確立させてくれます。
社会的信用があると、前述の通り銀行から融資を受けやすく、また他の会社から見ても安心して取引が出来る相手だと認められます。
ですので、これから事業をどんどん拡大していきたいと考えているなら、法人化は必須です。
まとめ
ここまで建設業許可の取得を含め、個人事業主から法人化する方法と理由について解説させていただきました。
個人事業主から法人化となると、今までよりずっと事業は拡大していきます。事業の拡大とともに、ビジネスチャンスにも恵まれますが、同時に責任も重くなっていきます。
そして、そんな状況の中で許可の取得や引き継ぎの申請等、慣れない書類手続きまで自分で行うのは負担の大きいものです。
そんな時は無理せず、専門の行政書士に相談するのがおすすめ。
東京都限定で建設業許可を専門に扱う【おさだ事務所】は多くのお客様の「困った!」に寄り添い、対応してきた実績があります。
そして、当事務所は行政書士事務所でもあり社会保険労務士事務所でもあります。ですので、許可取得後の更新や年度報告以外に、面倒な社会保険手続きもお引き受け可能です。会社のお金づくりも当事務所の強みの一つです。
力になれる自信があります。お気軽にご相談ください。